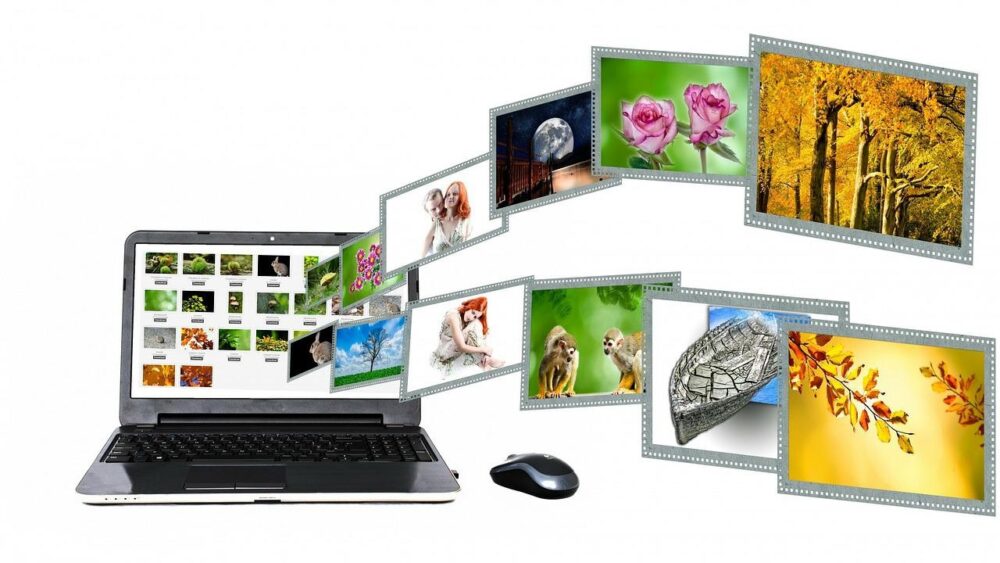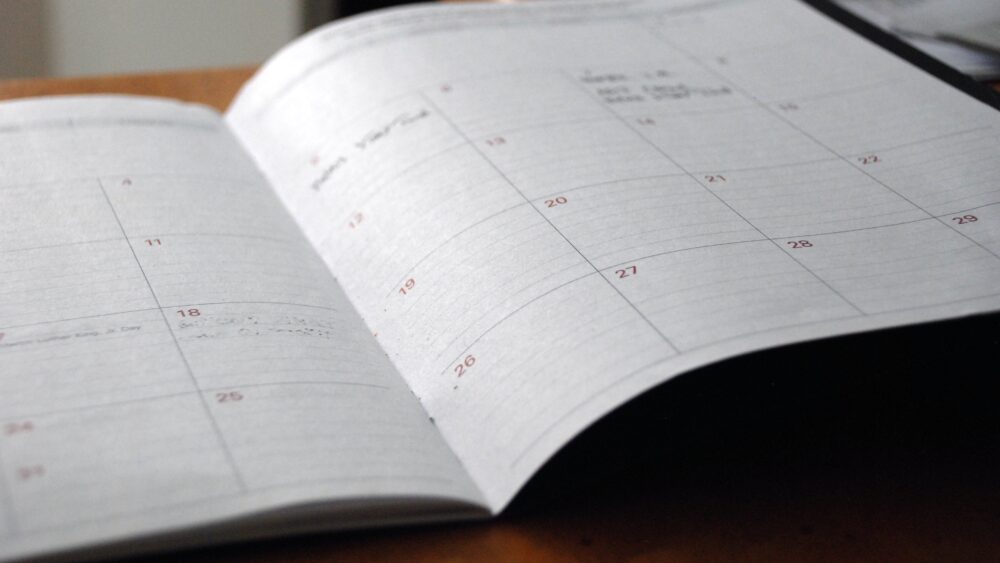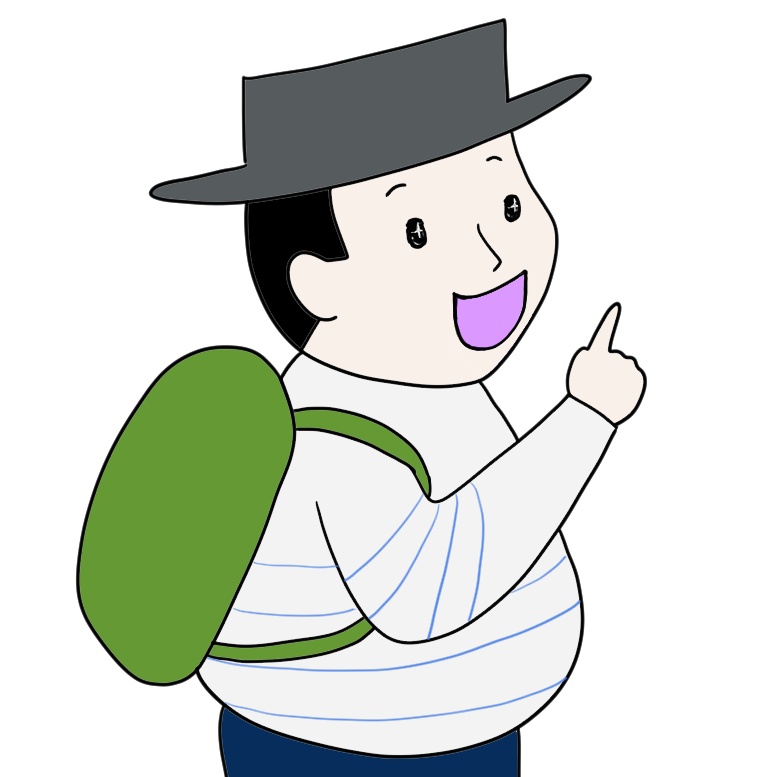8月のお祭りをまとめました。
詳細記事はリンクをクリックしてご覧ください。
目次
狸まつり 北海道札幌市のお祭り
北海道で最古の商店街で行われる夏の風物詩。コロナウイルス蔓延時の今年は残念ながら装飾のみの実施。
| 狸まつり | |
 | |
| 【場所】 〒060-0062 北海道札幌市中央区 南2・3条西1-7丁目 | |
| 【時期】 7月中旬-8月中旬 | |
| 【種類】 人形・装飾 | |
| 【概要】 140年以上の歴史を誇る北海道で最古の商店街、札幌狸小路商店街で実施される夏の風物詩。期間中はアーケードに提灯が飾られ、夜には狸小路が幻想的な雰囲気に包まれる。 特に人気なのは、狸小路の各店が趣向を凝らした露店を出す「狸小路ナイトバーゲン」で、多くの人で賑わう。他にも「狸神輿」の巡行や、子ども向けのイベントなども行われ、老若男女問わず楽しめる。狸小路商店街全体が一体となって盛り上がる、活気あふれるおイベント。 |
観蓮会 神奈川県横浜市のお祭り
三溪園で楽しむ朝限定の蓮の観賞会。1,700㎡の蓮池にピンクの蓮が咲き誇る。
| 観蓮会 | |
 | |
| 【場所】 三溪園 〒231-0824 神奈川県横浜市中区本牧三之谷58−1 045-621-0634 | |
| 【時期】 7月中旬-8月中旬 【2023年】 7月21日(金) 22日(土) 23日(日) 28日(金) 29日(土) 30日(日) 8月4日(金) 5日(土) 6日(日) 11日(金・祝) 12日(土) 13日(日) | |
| 【種類】 花見 | |
| 【概要】 泥の中から清らかな花を咲かせることから徳の高い花として原三溪が愛した蓮を鑑賞する夏の恒例イベント。 蓮は明け方から咲き始め、午前7時から9時頃に見頃を迎えるため、期間中は開園時間を午前7時に早め、咲いたばかりの美しい蓮を早朝のすがすがしい空気の中で楽しむことができる。 また、蓮の葉を使った「蓮の体験コーナー」や「うちわづくり」のワークショップなど、蓮にまつわる様々な体験イベントも開催され、園内の茶店では観蓮会限定の朝食メニューも提供される。 |
八戸三社大祭 青森県八戸市のお祭り
龗神社、新羅神社、神明宮の三社の合同例祭。豪華な山車が行列を組んで市内を巡行する。
| 八戸三社大祭 | |
 | |
| 【場所】 青森県八戸市中心街 | |
| 【時期】 7月31日-8月4日 | |
| 【種類】 山車・だんじり | |
| 【概要】 7月31日の前夜祭、1日の「御通り(神幸祭)」、2日の「中日」、3日の「御還り(還幸祭)」、4日の後夜祭という日程で行われる。 おがみ神社、新羅神社、神明宮の三社の神輿渡御に加えて、各町内が制作する27台もの巨大な山車が市内を練り歩く。これらの山車は、歌舞伎や神話を題材にした精巧な人形で飾られ、夜には提灯でライトアップされ幻想的な雰囲気を醸し出す。 国の重要無形民俗文化財に指定されており、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている、東北を代表する夏祭り。その歴史は290年以上に及び、毎年100万人以上の観光客が訪れる。 |
鉄砲洲納涼盆踊り 東京都中央区のお祭り
鉄砲洲児童公園で行われる盆踊り。大人にも子供にも優しい雰囲気が魅力。
| 鉄砲洲納涼盆踊り | |
 | |
| 【場所】 中央区立鉄砲洲児童公園 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目5−1 | |
| 【時期】 7月下旬-8月上旬 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 東京都中央区の湊一丁目、二丁目、入船一丁目、二丁目の4つの町会が合同で開催する盆踊り。中央区立中央小学校横の鉄砲洲児童公園を会場とし、特に小学生の参加が多いのが特徴。各町会がテントを出店しており、アットホームな雰囲気で安心して楽しめるのが魅力とされている。 定番の盆踊り曲のほか、中央区ならではの曲もかかることがあり、地域に根差したお祭りとして親しまれている。中央区民は盆踊り好きが多く、事前に小学校で練習会が開かれるほど熱心に取り組まれている。提灯の色も赤だけでなく、青や緑、ピンクなどカラフルで可愛らしい演出も見られる。 2023年鉄砲洲納涼盆踊り |
築地本願寺納涼盆踊り大会 東京都中央区のお祭り
国の重要文化財を背にして踊るフォトジェニックな盆踊り。築地場外の名店が支えるグルメも見逃せない。
| 築地本願寺納涼盆踊り大会 | |
 | |
| 【場所】 築地本願寺 〒104-8435 東京都中央区築地3-15-1 | |
| 【時期】 7月下旬-8月上旬 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 都内最大級の盆踊り大会で、国の重要文化財であるエキゾチックな本堂を背景に多くの人が櫓の周りで踊りの輪を形成する。 この大会の最大の特徴は、「日本一おいしい盆踊り」と称されるほど、築地場外市場の名店が出店する屋台グルメの充実ぶり。築地ならではの新鮮な海鮮や、伝統的なB級グルメなどが楽しめる。 伝統的な盆踊りの曲目に加え、近年は「おだいどこ音頭」のような新しい曲も取り入れられている。また、最終日には仮装大会も行われ、ユニークな衣装で踊る参加者で賑わう。地域住民やオフィスワーカー、観光客など、誰もが自由に参加し、踊りと食を通じて夏のひとときを満喫できる、東京の夏の風物詩となっている。 |
さっぽろ夏まつり 北海道札幌市のお祭り
湿気の少ないカラっとした気候で楽しむ北の大地の食道楽まつり。片手に持つのはサッポロクラシック。
| さっぽろ夏まつり | |
 | |
| 【場所】 北海道札幌市中央区大通 大通公園5丁目-8丁目、10丁目、11丁目 | |
| 【時期】 7月下旬-8月中旬 | |
| 【種類】 酒 | |
| 【概要】 大通公園をメイン会場に開催される大規模なイベントで、期間中はビアガーデン、盆踊り、狸小路での夜店など、様々な催しが行われる。 特に「さっぽろ大通ビアガーデン」は、約1ヶ月間大通公園が巨大なビアホールと化し、国内外のビールやフードが楽しめる。また、「北海盆踊り」では、やぐらを囲んで多くの市民が踊り、祭りの賑わいを一層盛り上げる。 他にも、札幌狸小路商店街では「狸まつり」が同時開催され、各商店街が趣向を凝らしたイベントで賑わう。札幌の短い夏を存分に楽しめる、市民にとっても観光客にとっても魅力的な祭り。 |
人形町せともの市 東京都中央区のお祭り
海路交通の拠点だった江戸時代の面影を今に残す、夏の風物詩。仕事帰りに手軽に立ち寄れるせともの市。
| 人形町せともの市 | |
 | |
| 【場所】 水天宮交差点から人形町交差点までの歩道全域 | |
| 【時期】 8月の第1週の月火水の3日間 | |
| 【種類】 市 | |
| 【概要】 江戸時代、人形町一帯は、海路交通が便利だったことから、酒、砂糖、醤油、穀物など、生活物資の集積所として、たいへん栄えた。それらといっしょに陶磁器問屋が関東一円の家庭のうつわをまかなったことから由来している。 通りには全国各地の窯元や陶器店が軒を連ね、多種多様な陶磁器が販売される。 普段使いの食器から美術品まで、幅広い品揃えが特徴で、掘り出し物を求めて多くの来場者で賑わう。 初日の午後には、せとものへの感謝と将来の発展を祈願する神事が執り行われる。期間中は周辺店舗での協賛セールやイベントも開催され、人形町全体がお祭りムードに包まれる。 |
くっちゃんじゃが祭り 北海道虻田郡倶知安町のお祭り
じゃがいもの美味しい街で、うまいものを頂く北の大地のお祭り。片手に持つのはクラフトビール。
| くっちゃんじゃが祭り | |
 | |
| 【場所】 北海道虻田郡倶知安町 駅前通り周辺 ※2022年はくとさんパーク駐車場 | |
| 【時期】 8月上旬 | |
| 【種類】 食 | |
| 【概要】 じゃがいもをテーマにしたお祭りで、倶知安町は「じゃがいも王国」として知られ、男爵いもの発祥地であることから、じゃがいもへの感謝と収穫を祝う目的で始まった。 祭りの目玉は、その名も「じゃがねぶた」。じゃがいもをかたどった巨大なねぶたが町を練り歩き、その迫力は見ごたえがある。他にも、じゃがいもを使った料理の屋台が多数出店し、ホクホクのフライドポテトやじゃがバターなど、様々なじゃがいもグルメを味わえる。 また、じゃがいもの無料配布やじゃがいも掘り体験、さらにはじゃがいもを使ったゲームなど、じゃがいも尽くしのイベントが盛りだくさん。子供から大人まで楽しめる、倶知安町最大の夏祭りとして地域に愛されている。 |
住吉神社例大祭 東京都中央区のお祭り
佃煮発祥の地の由緒ある祭り。3年に1度の本祭りでは獅子頭の宮出しや八角神輿の渡御が行われる。
| 住吉神社例大祭 | |
 | |
| 【場所】 住吉神社(佃) 〒104-0051 東京都中央区佃1丁目1−14 | |
| 【時期】 8月上旬 | |
| 【種類】 獅子 | |
| 【概要】 毎年8月6日・7日に行われる「蔭祭り」と、3年に一度行われる「本祭り」があります。 本祭りでは、八角神輿や龍虎・黒駒などの勇壮な獅子頭が町内を練り歩き、特に神輿を船に乗せて氏子地域を巡る「船渡御(ふねとぎょ)」は、かつて隅田川に神輿を担いで入る「海中渡御」の名残とも言われ、見どころの一つ。 また、高さ18メートルにも及ぶ大幟が立てられ、江戸の祭礼における「町神輿」「水かけ」「掛け声」という特徴を色濃く残している。 地域の住民が一丸となって盛り上げる活気あふれる祭りで、中央区の無形民俗文化財にも指定されている。 住吉神社例大祭2023_行事日程 |
阿佐ヶ谷七夕まつり 東京都杉並区のお祭り
阿佐ヶ谷の商店街が七夕飾りで彩られる。巨大なハリボテを見上げながら食べ歩きを楽しむ。
| 阿佐ヶ谷七夕まつり | |
 | |
| 【場所】 阿佐谷パールセンター商店街 | |
| 【時期】 8月上旬 | |
| 【種類】 人形・装飾 | |
| 【概要】 1954年(昭和29年)から始まり、毎年80万人以上が訪れる一大イベント。 最大の特徴は、各商店が趣向を凝らして制作するハリボテ。その年の流行や人気キャラクターなどをモチーフにした巨大なハリボテが商店街のアーケードを埋め尽くし、訪れる人々を楽しませる。色とりどりの七夕飾りや吹き流し、くす玉なども商店街を華やかに彩り、多くの屋台も出店して賑わう。 商店街の店が提供する飲食物はリーズナブルで、その味も評判。アーケード内なので、天候に左右されずに楽しめるのも魅力の一つ。 |
八王子まつり 東京都八王子市のお祭り
精巧な彫刻が施された山車が勢揃い。八王子を熱くする山車の辻合わせ。
| 八王子まつり | |
 | |
| 【場所】 東京地八王子市 八王子駅周辺 | |
| 【時期】 8月上旬 | |
| 【種類】 山車・だんじり | |
| 【概要】 江戸時代からの伝統を受け継ぐ「山車まつり」を基盤とし、約80万人もの来場者で賑わう。 祭りの主役は、豪華絢爛な彫刻が施された19台の山車で、その多くは八王子市の有形文化財に指定されている。夜になると灯火に照らされた山車が甲州街道を巡行し、その美しさは「動く芸術品」と称される。見どころは、山車がすれ違う際に囃子を競い合う「ぶっつけ」や、交差点に山車が集結する「辻合わせ」。 他にも、約3トンもの巨大な多賀神社の宮神輿「千貫みこし」の勇壮な渡御や、約4000人の浴衣姿の踊り手が甲州街道を舞い踊る「民踊流し」(ギネス世界記録認定)、郷土芸能の獅子舞、関東太鼓大合戦、八王子芸妓による「宵宮の舞」など、多彩な催しが繰り広げられ、八王子の伝統文化と活気を存分に味わえる祭り。 八王子まつりpamphlet2023_p1 八王子まつりpamphlet2023_p2_3 八王子まつりpamphlet2023_p4_5 八王子まつりpamphlet2023_p6_7 八王子まつりpamphlet2023_p8_9 八王子まつりpamphlet2023_p10_11 八王子まつりpamphlet2023_p12 |
天草伊勢えび祭り 熊本県天草市のお祭り
天然新鮮!ぷりっぷりの伊勢えびを頂ける天草市の食のお祭り 。漁の解禁時期に合わせて設定される宿泊プランを利用して大満足の旅。
| 天草伊勢えび祭り | |
 | |
| 【場所】 熊本県天草市内 | |
| 【時期】 8月中旬-12月 | |
| 【種類】 食 | |
| 【概要】 天草の5つのエリアで、天然新鮮なぷりっぷり伊勢えびが楽しめる祭り。 祭りの期間中、天草市内の旅館や飲食店では、刺身、鬼瓦焼き、具足煮、味噌汁など、伊勢えびの旨みを最大限に引き出した様々な料理が提供される。新鮮でぷりぷりの伊勢えびは、その濃厚な甘みと弾力のある食感が特徴で、まさに海の恵みを堪能できる。 また、伊勢えび料理だけでなく、天草の特産品が並ぶ物産展や、郷土芸能の披露など、様々な催しが行われ、訪れる人々を楽しませる。美しい天草の自然と美味しい海の幸を同時に楽しめるため、多くの観光客で賑わう。 地元の人々にとっても、秋の訪れを告げる風物詩として親しまれており、天草の魅力を国内外に発信する重要なイベントとなっている。 |
盛岡さんさ踊り 岩手県盛岡市のお祭り
からだの芯にまで鳴り響く太鼓の音。「サッコラチョイワヤッセ」の掛け声とともに続く踊りと太鼓の大パレード。
| 盛岡さんさ踊り | |
 | |
| 【場所】 岩手県盛岡市中心地 | |
| 【時期】 8月1-4日 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 太鼓、笛、踊り手が一体となって街を練り歩くのが特徴で、ミスさんさ踊りの演舞のあとには、一般参加の踊り集団や伝統さんさ踊り団体が続く。「サッコラチョイワヤッセ」の掛け声とともに勇壮な踊りが披露される。 その起源は、盛岡城下に羅刹(らせつ)という鬼が現れ人々を苦しめていた際、三ツ石神社の神様が鬼を捕え、二度と悪さをしないという誓いの証として三ツ石に手形を押させ追放したことに由来すると伝えられている。鬼がいなくなり喜んだ人々が、三ツ石の周りを踊りながら「さんささんさ」と囃したのが始まりとされている。 現在では、華やかな衣装を身につけた多数の参加団体が、盛岡市中心部の目抜き通りをパレードし、その迫力ある太鼓の音と群舞は、訪れる人々を魅了する。最終日には、「和太鼓同時演奏」世界記録奪還を記念した『世界一の太鼓大パレード』と、『大輪踊り(だい わおどり)』を行い、グランドフィナーレとなる。飛び入り参加も可能な「輪踊り」も行われ、観光客も一体となって祭りの賑わいを分かち合う。 |
弘前ねぷたまつり 青森県弘前市のお祭り
「ヤーヤドー」の掛け声とともに哀切に満ちた扇ねぷたが街を練り歩く。
| 弘前ねぷたまつり | |
 | |
| 【場所】 青森県弘前市中心部 | |
| 【時期】 8月1-7日 | |
| 【種類】 ねぶた・ねぷた | |
| 【概要】 扇ねぷたや組ねぷたと呼ばれる、勇壮華麗な約60台のねぷたが市内を練り歩く。交差点付近ではねぷたを回転させたり集団演技・舞が披露され、祭りをより一層盛り上げる。 ねぷたの表絵には中国の「三国志」や「水滸伝」を題材とした鏡絵と呼ばれる勇壮で色鮮やかな武者絵が描かれ、その裏側には見送り絵と呼ばれる妖艶な美人画や幽霊画が描かれる。 ねぷたの起源は諸説あるが、眠気を払う「ねむり流し」が変化したものと言われている。武者絵が描かれたねぷたは、夜空に浮かび上がる姿が幻想的で、太鼓や笛の囃子に合わせて「ヤーヤドー」の掛け声が響き渡る。 青森ねぶたは凱旋ねぶたと言われ賑やかで豪壮である一方、弘前ねぷたは出陣ねぶたと言われ力強く、哀切に満ちている。 期間中は、ねぷたの運行だけでなく、津軽情っ張り大太鼓の演奏や弘前ねぷた3Dプロジェクションマッピングなど、様々な関連イベントも開催され、多くの観光客で賑わう。 国の重要無形民俗文化財にも指定されている。 |
青森ねぶた祭 青森県青森市のお祭り
跳人(ハネト)のラッセラーのかけ声と囃子(ハヤシ)の音に合わせて大迫力、5mのねぶたが青森市内中心部を運行する。
| 青森ねぶた祭 | |
 | |
| 【場所】 青森県青森市中心部 | |
| 【時期】 8月2-7日 | |
| 【種類】 ねぶた・ねぷた | |
| 【概要】 日本が誇る夏の祭の一つ。5mほどの巨大な武者人形などが描かれた灯籠「ねぶた」が街を練り歩くのが最大の特徴。ねぶたは、竹や木枠に和紙を貼り、鮮やかな色彩で絵付けされたもので、中には電球が仕込まれており、夜には幻想的に輝く。 祭りの起源は諸説あるが、七夕の灯籠流しや、睡魔を流す「ねむり流し」が変化したものと考えられている。 祭りの期間中、シャンシャンと鳴り響く「囃子(はやし)」と共に花笠に色鮮やかな浴衣姿の「ハネト」と呼ばれる跳人たちが「ラッセラー」の掛け声とともに跳ね踊り、祭りを一層盛り上げる。最終日にはねぶたの海上運行と花火大会が行われ、祭りは最高潮に達する。青森ねぶた祭は、国の重要無形民俗文化財に指定されており、その迫力と美しさから多くの観光客を魅了している。 |
秋田竿燈まつり 秋田県秋田市のお祭り
秋田の夜空を灯す稲穂の数々。最終日は限界まで挑戦する竿燈妙技。
| 秋田竿燈まつり | |
 | |
| 【場所】 秋田県秋田市中心部 | |
| 【時期】 8月3-6日 | |
| 【種類】 行燈・提灯 | |
| 【概要】 この祭りの主役は「竿燈」と呼ばれる、稲穂に見立てた竹竿に提灯を多数吊るしたもの。差し手と呼ばれる演技者たちは、高さ最大12m、重さ50kgにもなる竿燈を、手のひら、額、肩、腰など一点で支え、バランスを取りながら巧みに操る。提灯の明かりが夜空を彩り、「ドッコイショー、ドッコイショ」の掛け声とともに、五穀豊穣や病魔退散を祈願する。 昼には「竿燈妙技大会」が開催され、差し手たちがその技を競い合う。夜の竿燈大通りを280本もの竿燈が埋め尽くす光景は、まさに圧巻で、秋田の夏の風物詩として多くの人々を魅了している。 東北三大祭りの一つで国の重要無形民俗文化財にも指定されている。 |
立佞武多祭り 青森県五所川原市のお祭り
高さが20mを超える巨大な山車が街を運行。立佞武多の圧倒的な存在感。
| 立佞武多祭り | |
 | |
| 【場所】 青森県五所川原市中心部 | |
| 【時期】 8月4-8日 | |
| 【種類】 ねぶた・ねぷた | |
| 【概要】 「青森のねぶた」と「弘前ねぷた」と並ぶ青森三大佞武多の一つ。最大で高さ約23m、重さ19トンにもなる巨大な人形灯籠「立佞武多」が、「ヤッテマレ!ヤッテマレ!」の掛け声と力強いお囃子に乗って市街地を練り歩く。 明治時代から巨大なねぷたが作られていたが、電線の普及や戦争により一度途絶えた。しかし、平成10年に約80年ぶりに復刻し、その圧倒的な迫力と美しさで観客を魅了している。五所川原市民の「もつけ」(熱中する、夢中になる)魂が生んだ、青森を代表する勇壮な祭り。 |
山形花笠まつり 山形県山形市のお祭り
艶やかな衣装と紅花の笠を手にした踊り手が「花笠音頭」にあわせて街を踊り練りあるく。
| 山形花笠まつり | |
 | |
| 【場所】 山形県山形市 中心部 | |
| 【時期】 8月5-7日 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 艶やかな紅花をあしらった笠を手に、「ハー ヤッショ、マカショ」の威勢の良い掛け声とともに、揃いの衣装をまとった踊り手が「花笠音頭」にあわせて市街地を練り歩く。 踊りの種類は大きく分けて2つあり、笠を回して踊る正調花笠踊りの「薫風最上川」と、趣向を凝らした創作花笠踊りがある。企業や学校、地域団体など様々なグループが参加し、それぞれ個性豊かな踊りを披露する。飛び入り参加が可能な「飛び入り花笠」の時間もあり、観光客も一体となって祭りの熱気を体験できる。山形の夏の夜を彩る、活気に満ちた祭り。 |
仙台七夕まつり 宮城県仙台市のお祭り
色鮮やかな七夕飾りが街を埋め尽くす。東北の真夏を感じる豪華な七夕まつり。
| 仙台七夕まつり | |
 | |
| 【場所】 宮城県仙台市中心部 | |
| 【時期】 8月6-8日 | |
| 【種類】 人形・装飾 | |
| 【概要】 仙台市内中心部および周辺に色鮮やかな七夕飾りをほどこす東北三大祭りの一つ。伊達政宗公の時代から続く伝統的なお祭りでもともと、旧暦7月7日の行事であったが、東北の季節感に合わせるため8月6日から8日に開催されている。 一番の見どころは、仙台市中心部の商店街を埋め尽くす豪華絢爛な七夕飾り。和紙などで作られた吹き流しや、短冊、折り鶴など、趣向を凝らした飾りが通りを彩り、訪れる人々を魅了する。各飾りには、商売繁盛や無病息災などの願いが込められており、その美しさと華やかさから、日本全国はもとより海外からも多くの観光客が訪れる。夜にはライトアップもされ、昼間とはまた違った幻想的な雰囲気を楽しめる。 |
桐生八木節まつり 群馬県桐生市のお祭り
八木節で街がクラブと化す、メイドインジャパンのダンスホール。
| 桐生八木節まつり | |
 | |
| 【場所】 群馬県桐生市本町・末広町・錦町 | |
| 【時期】 8月の第1金曜日から三日間 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 最大の特徴は、桐生が発祥とされる「八木節」の軽快なリズムに合わせて、多くの市民が「ヤグラ」と呼ばれる舞台を囲んで踊り明かす光景。 まつり期間中は、市街地の広範囲で交通規制が敷かれ、総延長約2.5㎞が歩行者天国となる。色とりどりの浴衣を身にまとった人々が通りを埋め尽くし、各所に設置されたヤグラから流れる八木節の音頭に合わせて踊る。八木節の他にも、子どもみこしやジャンク市、パフォーマンスイベントなども開催され、老若男女が一体となって桐生の夏の夜を盛り上げる。 本町三丁目の衆生院の境内にあった牛頭天王社の祭りを源流としているが昭和39年から、春の商工祭・文化祭、夏の七夕祭・花火大会、秋の桐生祭・体育祭など、多くの行事・祭礼と統合され、「桐生八木節まつり」として開催されるようになった。 伝統と活気が融合した桐生八木節まつりは、桐生の夏の風物詩として親しまれている。 2023年桐生八木節まつり パンフレット表 2023年桐生八木節まつり パンフレット裏 |
やっさいもっさい踊り大会 千葉県木更津市のお祭り
「おっさ」を掛け声に港町木更津が心を一つにする踊り大会。
| やっさいもっさい踊り大会 | |
 | |
| 【場所】 〒292-0831 千葉県 木更津市 富士見 | |
| 【時期】 8月14日 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 市民が一体となって「おっさ」という掛け声とともに踊り歩く、自由な踊りが特徴の市民参加型のお祭り。 「やっさいもっさい」とは、木更津に伝わる民謡「木更津甚句」(きさらづじんく)の中にある囃子言葉。高度成長期に、木更津に新日本製鐵君津製鐵所がオープンし、それまでの住民と、新しくやって来た人々の和を考え、「みんながおとなりどうし」を合言葉に始まった。 老若男女問わず、誰もが気軽に参加できるのが魅力で、各チームが趣向を凝らした衣装やパフォーマンスを披露する。お囃子に合わせて踊り、木更津の夏の夜を熱く盛り上げる。見物客も飛び入り参加できるなど、一体感を味わえるのがこの踊り大会の醍醐味。 ※掛け声の「おっさ」は、「おお、そうだよ!」と同調するときの相づちで「みんなお互いに理解しあおうよ」という意味。 |
阿波おどり 徳島県徳島市のお祭り
徳島中の老若男女が踊り狂う、熱狂の夏祭り。「ヤットサー」の掛け声が町中に響き渡る。
| 阿波おどり | |
 | |
| 【場所】 徳島県徳島市中心地 | |
| 【時期】 8月11-15日 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 徳島県で400年以上の歴史を持つ伝統的な盆踊りで「前夜祭」「選抜阿波おどり」「阿波おどり」の3つで構成され国内外から多くの観光客が訪れる。日本三大盆踊りの一つ。 踊り手たちは1,000以上ある「連(れん)」と呼ばれるグループを組み、色鮮やかな衣装をまとい、三味線、太鼓、鉦、笛などの鳴り物に合わせて街を練り歩く。特徴的なのは、その自由で熱狂的な踊り方。「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損々」という掛け声の通り、観客も一体となって盛り上がる。 「ヤットサー」の掛け声と共に女性は優雅でしなやかな「女踊り」、男性は力強く躍動感あふれる「男踊り」を披露する。また、それぞれの連が独自の工夫を凝らした踊りを披露するため、見どころが尽きない。 |
東山盆踊り 福島県会津若松市のお祭り
温泉街が本気で取り組む盆踊り。湯川の清流を囲んでの踊りは圧巻。
| 東山盆踊り | |
 | |
| 【場所】 福島県会津若松市東山町湯本 | |
| 【時期】 8月13-16日 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 東山温泉旅館協同組合が主催し、温泉街の中心部が会場となる。東山温泉を流れる湯川の上に組まれたやぐらを囲んで、民謡「会津磐梯山」の唄とお囃子に合わせて、盆踊りを行う。市民や温泉客、東山温泉の女将や芸者衆が一緒に踊るさまは見事。 盆踊りだけでなく、屋台の出店や福引きなども行われ、お祭りムードを盛り上げる。地域の文化と歴史に触れることができる、夏の思い出作りにぴったりのイベント。 昭和19年から学童疎開に来ていた子ども達を元気づけるために始まった。 |
尾島ねぷたまつり 群馬県太田市のお祭り
「ヤーヤドー」の掛け声とともにねぷたが太田市尾島の通りを練り歩く。北関東で見つけたもう一つのねぷたまつり。
| 尾島ねぷたまつり | |
 | |
| 【場所】 群馬県太田市尾島商店街大通り(県道142号) | |
| 【時期】 8月14・15日 | |
| 【種類】 ねぶた・ねぷた | |
| 【概要】 青森県弘前市との歴史的なつながりから昭和61年に始まり、本場弘前ねぷたの様式を継承している。 「ヤーヤドー」の掛け声とともに、高さ7メートルにも及ぶ勇壮な扇ねぷたとねぷた太鼓の隊列が尾島商店街大通りを練り歩く。夜空に浮かび上がる色鮮やかな武者絵は幻想的で、祭り終盤に行われるねぷた太鼓と祭り囃子の大合奏は圧巻。太田の夏の夜を彩る一大イベントとして、多くの人々を魅了している。 |
おびひろ平原まつり 北海道帯広市のお祭り
北の大地の恵みに感謝する、短い夏を感じるお祭。
| おびひろ平原まつり | |
 | |
| 【場所】 北海道帯広市西2条南7丁目-11丁目及び広小路 夢の北広場 | |
| 【時期】 8月14-16日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 戦後の混乱期、市民の士気を高める「帯広平和まつり」として始まり、半世紀以上の歴史を持つ。 祭りの目玉は、先人への感謝と五穀豊穣を願う「夢降夜(ゆめふるや)」の神輿渡御、全道各地から太鼓チームが集結し迫力ある演奏を繰り広げる「平原・太鼓まつり」、そして趣向を凝らした衣装と踊りが見所の「おびひろ盆踊り」。 その他、大道芸フェスティバルや各種街区イベント、地元グルメが楽しめる「キッチン平原」など、見て参加して楽しめる催しが盛りだくさんで、帯広の短い夏を熱く華やかに彩る。 |
横手の送り盆まつり 秋田県横手市のお祭り
餓死者の霊を供養するために始まった盆まつり。威勢のよい囃子と屋形舟が御霊を送る。
| 横手の送り盆まつり | |
 | |
| 【場所】 蛇の崎橋周辺 〒013-0017 秋田県横手市蛇の崎町2 | |
| 【時期】 8月15・16日 | |
| 【種類】 舟 | |
| 【概要】 約400年もの歴史を持ちお盆に迎えた先祖の霊を送り出すための行事として、市民に大切に受け継がれている。 祭りの見どころは、横手川で行われる灯籠流し。夕闇が迫る中、願い事を書いた色とりどりの灯籠が次々と川面に放たれ、幻想的な光景が広がる。 日中には、市内を勇壮に練り歩く屋形舟の巡行が行われ、祭り全体が活気に満ち溢れる。これは江戸中期の大飢餓で亡くなった人々の供養のために、ワラで作った屋形舟を川原に繰り出し霊を供養したのが始まりと言われている。 15日には、約1000人の踊り手が屋形舟を囲んで踊る市民盆おどり、16日には屋形舟の繰り出しが行われ、華やかな花火をバックに屋形舟の勇壮なぶつかり合いが繰り広げられる。 夏の終わりの風物詩として、多くの観光客も訪れる賑やかなお祭りで県の指定無形民俗文化財。 |
山鹿灯籠まつり 8月熊本県山鹿市のお祭り
頭に金灯籠を掲げた浴衣姿の女性たちが、山鹿市内を優雅に舞い踊る。
| 山鹿灯籠まつり | |
 | |
| 【場所】 熊本県 山鹿市内 山鹿小学校グラウンド(千人灯籠踊り) 熊本県山鹿市山鹿351 | |
| 【時期】 8月15-17日 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 頭に和紙だけで作られた金灯籠を掲げた浴衣姿の女性たちが、ゆったりとした情緒漂う「よへほ節」の調べにのせて市内を優雅に舞い踊る。 その起源は、深い霧に行く手を阻まれた第12代景行天皇のご巡幸を、山鹿の里人たちが松明を掲げ無事にお迎えしたことに由来する。以来、里人たちは行在所跡(現在の大宮神社)に天皇を祀り、毎年灯火を献上するようになったのが始まりとされている。 室町時代になると紙製の金灯籠に姿を変え、その後、金灯籠を頭に掲げた女性が舞い踊る「山鹿灯籠踊り」が誕生し、祭りの代名詞ともいえる千人灯籠踊りが生まれた。 8月16日は山鹿小学校グラウンドにて千人灯籠踊りが行われる。 期間中は、奉納灯籠踊りや大宮神社への奉納、花火大会なども行われ、街全体がお祭りムードに包まれる。特に夜空の下で揺らめく数千もの金灯籠の光景は、訪れる人々を魅了する。 2023年 山鹿灯籠まつりリーフレット 2023年 山鹿灯籠まつり会場図 |
鬼来迎 千葉県山武郡のお祭り
地獄の再現と菩薩の救いを仮面狂言にした日本の民俗芸能。
| 鬼来迎 | |
 | |
| 【場所】 広済寺 〒289-1717 千葉県山武郡横芝光町虫生483 | |
| 【時期】 8月16日 | |
| 【種類】 歌舞伎・舞台 | |
| 【概要】 全国唯一の仮面による地獄劇。8月16日、お盆の「地獄の釜が開く日」に上演される。 この行事は、鎌倉時代初期に始まったとされ、地獄の様相と菩薩の救いを描くことで、因果応報や衆生救済を説く。閻魔大王や鬼婆、黒鬼、赤鬼などの仮面をつけた役者たちが、亡者が苦しむ地獄絵図を演じ、最後に地蔵菩薩が現れて鬼を説き伏せ、亡者を救済するという物語。 その歴史と独自性から、国の重要無形民俗文化財に指定されており、地域の重要な伝統芸能として保存・継承されている。 |
西馬音内盆踊り 秋田県雄勝郡のお祭り
別世界を体感できる秋田の奇祭。華やかな「端縫い衣装」と頭巾が印象的な「彦三頭巾」で共に踊るのは「亡者踊り」。
| 西馬音内盆踊り | |
 | |
| 【場所】 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内本町108-1 | |
| 【時期】 8月16-18日 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 秋田県羽後町に伝わる約700年の歴史を持つ伝統的な盆踊りで郡上踊り(岐阜県)、阿波踊り(徳島県)とともに「日本三大盆踊り」に数えられる。国の重要無形民俗文化財に指定されており、京都の「念仏踊り」や「風流(ふりゅう)」の流れを汲むとされている。 最大の特徴は、編み笠や彦三頭巾(ひこさずきん)で顔を隠し、藍染めの浴衣や端縫い(はぬい)衣装をまとって踊る点。特に「亡者」と呼ばれる、彦三頭巾で顔全体を覆い隠した姿は、幻想的で幽玄な雰囲気を醸し出し、見る者に強い印象を与える。 踊りは優雅で流れるような動きが特徴で、笛や太鼓、鉦(かね)などの生演奏に合わせて、老若男女が一体となって踊る。お盆の時期、毎年8月16日から18日の夜にかけて行われ、かがり火が焚かれた中で繰り広げられるその光景は、「亡者と生者が一体となる盆踊り」とも称され、見る人を魅了する。死者への供養と五穀豊穣を願う心が込められた、地域に根付いた文化として大切に受け継がれている。 |
深川神明宮例大祭 東京都江東区のお祭り
「ワッショイ」の掛け声で巡幸する深川神明宮の本社神輿。氏子各町の12基の大神輿が行列を組んで連合渡御を行う。
| 深川神明宮例大祭 | |
 | |
| 【場所】 深川神明宮 〒135-0004 東京都江東区森下1丁目3−17 | |
| 【時期】 8月17日に近い日曜日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 深川神明宮の例大祭には、三年に一度の「本祭り」と、その間の年の「蔭祭り」がある。「本祭り」は特に盛大に行われ、宮神輿の巡幸や町神輿の連合渡御が最大の見どころとなる。深川の総鎮守として崇敬される深川神明宮の宮神輿が氏子十二ヶ町を巡幸し、また各町の町神輿も勢揃いして練り歩く。 特徴的なのは「水かけ祭り」とも呼ばれる勇壮な水かけで、沿道から担ぎ手に清めの水が勢いよくかけられる。掛け声は伝統的な「ワッショイ!」。 蔭祭りの年は、8月17日に近い日曜日に本殿祭のみを行い、神社としての祭礼行事はないが、町神輿の町内巡幸、子ども神輿や山車の巡幸などの祭礼行事を行う町もある。 下町らしい飾りっ気のなさの中にも、熱気と活気が溢れる祭りで、地元住民を中心に多くの人で賑わう。 2024深川神明宮例大祭MAP |
富岡八幡宮例大祭(深川八幡祭り) 東京都江東区のお祭り
「わっしょい、わっしょい』の掛け声と共に神輿の御渡しが行われ、沿道からは清めの水が浴びせられる、江戸の夏を象徴する「水かけ祭」。
| 富岡八幡宮例大祭(深川八幡祭り) | |
 | |
| 【場所】 東京都江東区 富岡八幡宮周辺 | |
| 【時期】 8月中旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 「深川八幡祭り」とも呼ばれ、赤坂の日枝神社の山王祭、神田明神の神田祭とともに「江戸三大祭」の一つに数えられている。 3年に一度の八幡宮の御鳳輦が渡御を行う本祭りでは、約50基の町神輿が勢揃いする連合渡御が圧巻で、「ワッショイ、ワッショイ」という威勢のいい掛け声と共に街を練り歩く。 この祭りの最大の特徴は、「水かけ祭り」とも呼ばれる豪快な「水かけ」。沿道の観衆が担ぎ手に清めの水を浴びせかけ、担ぎ手と観衆が一体となって盛り上がる光景は、まさに江戸の粋を感じさせる。 起源は1642年、徳川家光の長男家綱の世継ぎ祝賀に由来するとされ、380年以上の歴史を誇る伝統的な祭りとして、地域の人々に大切に受け継がれている。 |
輪島大祭(輪島前神社大祭) 石川県輪島市のお祭り
総漆塗りの豪華なキリコが巡行する。日本海の荒々しさを感じる漆器の街の祭。
| 輪島大祭(輪島前神社大祭) | |
 | |
| 【場所】 石川県輪島市輪島前神社 〒928-0071 石川県輪島市輪島崎町1−200 | |
| 【時期】 8月22-25日 | |
| 【種類】 山車・だんじり | |
| 【概要】 輪島大祭は、石川県輪島市で毎年8月22日から25日にかけて行われる、旧輪島町4地区(海士町・奥津比咩神社、河井町・重蔵神社、鳳至町・住吉神社、輪島崎町・輪島前神社)の産土神の例大祭の総称。300年以上の歴史があり、能登を代表するキリコ祭りの一つとして知られてる。 4つの地区の中でフィナーレを飾るのは輪島前神社の祭礼。大漁と海上安全を願う鯛の形をした神輿が、キリコをともなって、町内の細い通りを勢いよく駆け抜ける。 クライマックスは松明神事。輪島崎町では松明の倒れる方向で吉凶を占い、海側に倒れれば大漁、山側に倒れれば豊作といわれている。 |
小張松下流綱火 茨城県つくばみらい市のお祭り
あやつり人形と仕掛け花火が合体したつくばみらい市の伝統芸能。火難除け・五穀豊穣を祈願する国の重要無形民俗文化財。
| 小張松下流綱火 | |
 | |
| 【場所】 小張愛宕神社 〒300-2353 茨城県つくばみらい市小張3235 | |
| 【時期】 8月23・24日 | |
| 【種類】 人形・装飾 | |
| 【概要】 あやつり人形と仕掛け花火を組み合わせたユニークな演目で、「三本綱」や「からくり人形仕掛け花火」とも呼ばれる。小張松下流と高岡流の二流派が伝わっている 。空中に張り巡らされた綱を巧みに操作し、お囃子に合わせて人形を動かし、物語を展開させる。劇的な場面では花火が盛大に打ち上げられ、観客を魅了する。 中世から近世にかけて小張城主であった松下石見守重綱が考案したものといわれ、戦勝祝いや犠牲者の供養のために陣中で行ったと伝えられており、重綱は鉄砲を扱う火薬師であったとも言われる。家臣として仕えた大橋吉左衛門が助手をしていた関係から、火薬の調合などを伝授され松下流と名付け、受け継がれている。 現在は火難除け・五穀豊穰を祈願して奉納し、小張松下流綱火保存会が保存・伝承している。 昭和51年(1976)に国の重要無形民俗文化財の指定を受けた。 |
吉田の火祭り 山梨県富士吉田市のお祭り
山じまいを告げる大松明が富士吉田の街を照らす。不思議な高揚感が沸く日本の三奇祭。
| 北口本宮富士山浅間神社鎮火祭(吉田の火祭り) | |
 | |
| 【場所】 山梨県富士吉田市 北口本宮富士山浅間神社~参道 | |
| 【時期】 8月26・27日 | |
| 【種類】 火 | |
| 【概要】 「日本三大奇祭」の一つで、富士山の夏山登山の終わりを告げる「お山仕舞い」の祭りとして知られ、北口本宮冨士浅間神社と諏訪神社の例大祭として行われる。 8月26日の「鎮火祭」では大神輿、富士御影が御旅所に到着すると、直径90㎝、高さ約3mにもなる大松明が約70本以上、市内の目抜き通りに立てられ、夕闇とともに一斉に点火される。街全体が炎に包まれるその光景は圧巻で、富士山の噴火を鎮めるという意味合いも込められている。 翌27日の「すすき祭り」では、神輿が氏子中を練り歩き、すすきの玉串を持って安産や無病息災を祈願する。 400年以上の歴史を持ち、富士山信仰とも深く結びついた、勇壮で神秘的な祭り。 |
三河一色大提灯まつり 愛知県西尾市のお祭り
全長約10mの巨大な提灯が創る幻想的な空間。450年以上続く愛知県の有形民俗文化財。
| 三河一色大提灯まつり | |
 | |
| 【場所】 三河一色諏訪神社 〒444-0423 愛知県西尾市一色町一色宮添129 | |
| 【時期】 8月26・27日 | |
| 【種類】 行燈・提灯 | |
| 【概要】 最大の特徴は、高さ10メートル、直径5.6メートル、重さ480キログラムにもなる巨大な提灯。6組12張りの大提灯が立ち並び、それぞれに源平合戦や伝説の物語が描かれている。巨大ろうそくでこれらの提灯に火が灯されると、夜空に幻想的な光景が浮かび上がる。 海魔退散を祈願したのが始まったとされ、450年以上続く県の有形民俗文化財。古くから伝わる伝統と壮大な提灯の美しさを堪能できる、見どころ満載の祭り。 |
大曲の花火 全国花火競技大会 秋田県大仙市のお祭り
日本最高峰の芸術花火、全国の花火師が集う日本三大競技花火大会の一つ。
| 大曲の花火 全国花火競技大会 | |
 | |
| 【場所】 秋田県大仙市大曲 雄物川河川敷運動公園 | |
| 【時期】 8月最終土曜日 | |
| 【種類】 花火 | |
| 【概要】 日本最高峰の花火が楽しめる花火競技大会。最大の特徴は、日本一の花火師たちが技と美を競い合う点にある。昼花火、夜花火(10号玉、創造花火)の3部門で審査が行われ、最高位の内閣総理大臣賞を目指す。 特に、大会提供の「大会提供花火」は、音楽に合わせて1時間にわたって繰り広げられる壮大な花火ショーで、観客を圧倒する。また、大会のフィナーレを飾る「創造花火」は、花火師の独創性が光る傑作揃い。 大曲市は「花火のまち大曲」として季節ごとに異なるテーマ「四季の花火」を展開している。 |
古利根川流灯まつり 埼玉県葛飾郡杉戸町のお祭り
畳一畳分の大型灯ろうが川面を埋め尽くす。約250基の灯ろうが作る天の川。
| 古利根川流灯まつり | |
 | |
| 【場所】 古利根川河畔 (古川橋~清地橋) 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | |
| 【時期】 8月下旬 | |
| 【種類】 行燈・提灯 | |
| 【概要】 最大の見どころは、古利根川に流される灯籠で、1つ1つの大型灯ろうは畳一畳分。日本最大級の大型灯ろう約250基の光の帯が川面を埋め尽くし、そのさまはまさに地上に降りた天の川。夜空には花火も打ち上げられ、灯籠の光と花火が織りなす競演は、訪れる人々を魅了する。ちなみに灯ろうは、組み立て細工の要領で釘を使わずに全て町の人の手作り。 会場には露店も立ち並び、地元グルメなどを楽しむこともできる。夏の夕涼みを兼ねて、幻想的な光景を体験しに多くの人が訪れる。家族連れやカップル、友人同士など、誰と訪れても楽しめる夏の風物詩として、地域に親しまれている。 |
亀戸天神社例大祭 8月東京都江東区のお祭り
学問の神様、下町の天神さまとして親しまれている神社で執り行われる大祭。残暑厳しい夏空の下、御神輿が威勢良く担がれる。
| 亀戸天神社例大祭 | |
 | |
| 【場所】 亀戸天神社 〒136-0071 東京都江東区亀戸3丁目6−1 | |
| 【時期】 8月下旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 学問の神様として親しまれる菅原道真公を祀る亀戸天神社で開催されるお祭り。特に4年に一度の大祭では、鳳輦(ほうれん)と呼ばれる御神輿が牛に曳かれ氏子地域を巡行し、各町の神輿も盛大に宮入りする連合渡御が行われ、江戸下町の勇壮な祭礼絵巻が繰り広げられる。 普段は静かな境内も、この期間中は紅白の提灯が揺らぎ、多くの参拝者で賑わう。また、夜には1000個以上の灯明が灯される「献灯明」が行われ、心字池に映る幻想的な光景は見る者を魅了する。地域の人々にとって、夏の終わりを告げる風物詩として親しまれている。 |
中央区大江戸まつり盆踊り大会 東京都中央区のお祭り
中央区が運動場で行う本気の盆踊り。オリジナル曲目『これがお江戸の盆ダンス』が響き渡る。
| 中央区大江戸まつり盆おどり大会 | |
 | |
| 【場所】 浜町運動場 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2丁目59 | |
| 【時期】 8月下旬 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 浜町運動場に大きなやぐら を建て、中央区民踊連盟、各町会、中央区にある企業などが中心になって盆踊りが行われる。 中央区オリジナルの『これがお江戸の盆ダンス』や『ダンシングヒーロー』、『バハマ・ママ』などが曲目として使われ、伝統と斬新が交錯する“粋”を感じる盆踊り。10層もの踊りの輪が取り囲む姿は圧巻。盆踊りの事前練習会も開催され、初心者でも気軽に楽しめるよう配慮されている。 さらに区内名物市や伝統芸能の披露、子ども向けの縁日コーナーなど、多彩な催しも行われる。毎年数万人が来場し、区民のふるさと意識を高め、地域活性化に貢献している。 2023中央区大江戸まつり盆踊りパンフレット 2023中央区大江戸まつり盆踊り プログラム |
東京高円寺阿波おどり 東京都杉並区のお祭り
商店街の賑わい作りから始まった高円寺の夏の風物詩。110の連、9000人の踊り手が練り踊る。
| 東京高円寺阿波おどり | |
 | |
| 【場所】 JR「高円寺」駅、東京メトロ・丸ノ内線「新高円寺」駅周辺商店街及び高南通りの8演舞場 東京都杉並区 | |
| 【時期】 8月下旬 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 東京都杉並区高円寺で開催される東京最大級の阿波おどり。約1万人の踊り手が参加し、期間中には100万人もの観客が訪れる東京の夏の風物詩として知られている。 1957年に高円寺の商店街が町おこしとして始めた「高円寺ばか踊り」が起源で、その後徳島県出身者からの指導を受け、本格的な阿波おどりへと発展した。 高円寺駅周辺の商店街や高南通りに8つの演舞場が設けられ、「流し踊り」と呼ばれる街中での踊りと、ホールで行われる「舞台踊り」の両方が楽しめる。各連(チーム)ごとに趣向を凝らした衣装や踊りが特徴で、見る阿呆も踊る阿呆も一体となって盛り上がる。地域住民、商店街、ボランティアが一体となって運営を支える、歴史と人情味あふれる祭り。 2023東京高円寺阿波おどりpamphlet |
佃島の盆踊&入船三丁目町会盆踊り 東京都中央区のお祭り
江戸の名残をとどめる指定無形民俗文化財。櫓を囲って地元住民がキレよく踊る盆踊り。
| 佃島の盆踊 | |
 | |
| 【場所】 佃公園・佃小橋たもと 東京都中央区佃 | |
| 【時期】 9月 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 江戸時代から300年続く祖先の霊を祀る念仏踊りで、都の無形文化財に指定されている。 櫓太鼓に合わせ仮設のやぐらの周りを踊る。唄も「秋の七草」「糸屋の娘」と情趣深い。 地域住民にとって夏の風物詩であり、先祖供養の意味合いとともに、地域コミュニティの絆を深める重要な行事となっている。地元の方々はもちろん、遠方からも多くの見物客が訪れ、その賑わいは夏の風物詩として親しまれている。 |
| 入船三丁目町会盆踊り | |
 | |
| 【場所】 東京都中央区入船3丁目 NTT裏×Rico’s(旧ピアゴ)前 | |
| 【時期】 8月 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 東京都中央区入船三丁目の交差点で行われる、地域に根差した盆踊り大会。例年8月に開催され、交通規制をかけて交差点の真ん中にやぐらを建て、その周りを多くの人が囲んで踊る。 中央区の入船3丁目交差点で行われる盆踊り大会。入船3丁目町会が主催する会場で、中央区らしい曲目が楽しめる。地元の人々にとって夏の風物詩であり、アットホームな雰囲気で楽しめるのが魅力とされている。地域住民の交流の場として、また夏の思い出を作るイベントとして親しまれている。 |
| 八丁堀納涼大会 | |
 | |
| 【場所】 京華スクエア 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目17−9 京華スクエア | |
| 【時期】 9月 | |
| 【種類】 踊り | |
| 【概要】 京橋七の部連合町会が主催して行われる盆踊り大会。 会場となる京華スクエア前のスズラン通りは交通規制が行われ、多くの屋台が出店して賑わう。焼き鳥やフランクフルト、生ビールなどが楽しめ、地域住民だけでなく近隣で働く人々も大勢訪れる。 この大会の特徴は、東京音頭や炭坑節といった定番の盆踊り曲に加え、「大江戸八丁堀音頭」や「ホームラン音頭」といった地域にちなんだ個性的な曲も踊られる点。また、雨天時には敷地内の体育館で踊れるため、天候に左右されずに楽しめるのも魅力。最終日には提灯の電気が消され、花火が打ち上げられる恒例のフィナーレも人気を集める。 |
以上、「8月のお祭り」でした。他の月のお祭りもまとめています。どうぞ以下からご覧ください。
1月のお祭り 2月のお祭り 3月のお祭り 4月のお祭り 5月のお祭り 6月のお祭り 7月のお祭り 8月のお祭り 9月のお祭り 10月のお祭り 11月のお祭り 12月のお祭り