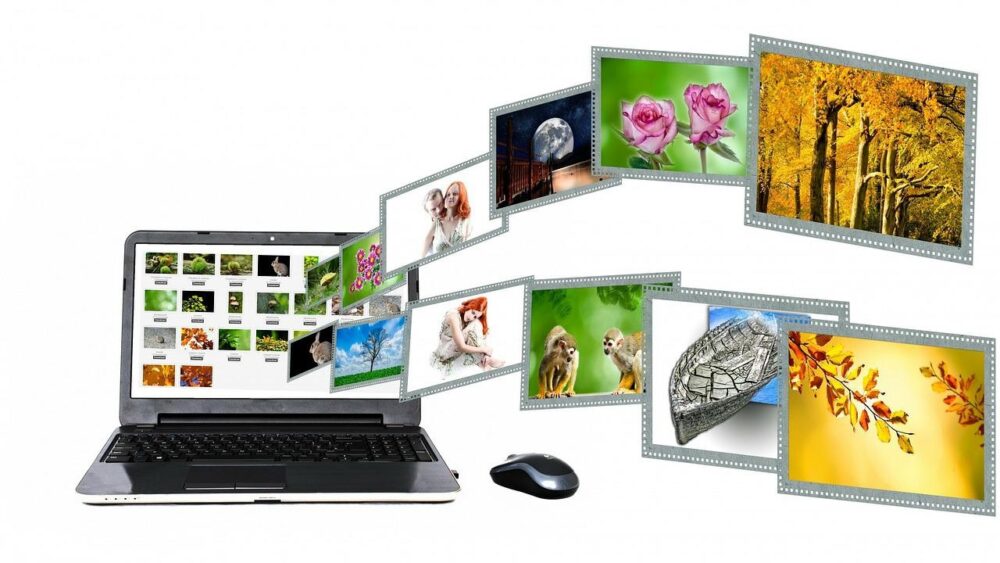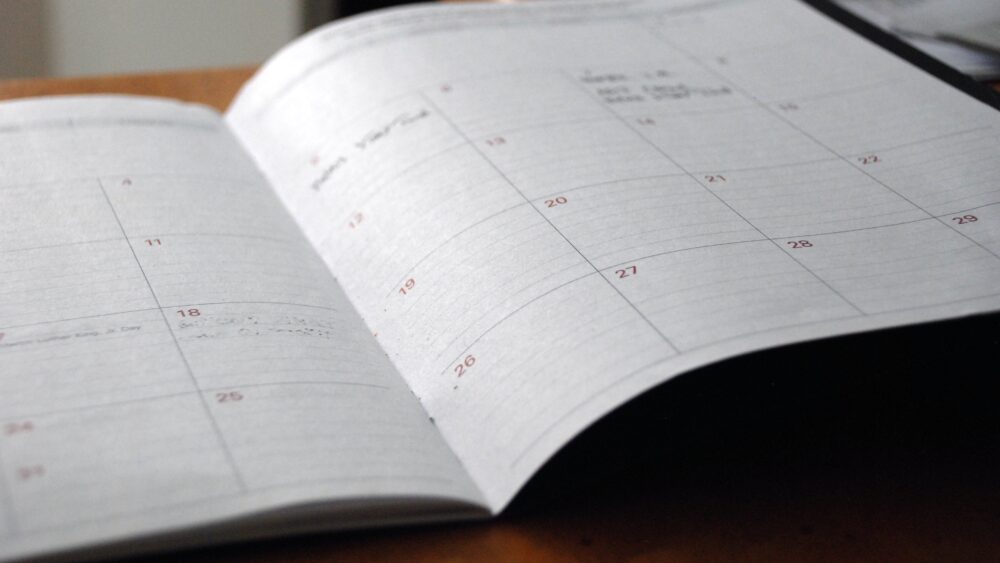月ごとに祭を検索してその祭りと旅を実際に楽しんで頂くために、本ブログでご紹介しているお祭りを月ごとにまとめました。具体的な旅のプランはリンクを貼りましたので参考にしてください。
目次
こいのぼりの里まつり 群馬県館林市のお祭り
春のお花と一緒に見たい空を優雅に泳ぐこいのぼり群。その数はギネス級。

| 名称 | こいのぼりの里まつり |
| 概要 | こいのぼりの掲揚イベントで市制施行50周年を契機にこいのぼりの掲揚数5283匹でギネス認定を受けた。掲揚場所は鶴生田川・近藤沼公園・旧つつじが岡パークイン・茂林寺川・多々良沼の市内5か所。 とくに桜の木が多い鶴生田川では、夜間のライトアップが行われる。 さくらとつつじの見頃時期に合わせて3月下旬~5月中旬に開催される。 鶴生田川浄化啓発を目的として、こいのぼりの掲揚を始めたことから始まり、現在に至っている。 |
| 開催場所 | 群馬県 館林市内の鶴生田川、近藤沼、茂林寺川、旧つつじが岡パークイン、多々良沼 |
| 時期 | 3月下旬~5月上旬 |
| 問合せ | 館林市観光協会 TEL:0276-74-5233 |
| 参考 | 館林市観光協会 |
こいのぼりの里まつりのくわしい記事
小江戸川越春まつり 埼玉県川越市のお祭り
桜と共に春の到来を知らせる小江戸川越の春祭り。

| 名称 | 小江戸川越春まつり |
| 概要 | 小江戸川越に春を告げるイベント。川越市内では、こいのぼりが飾られ、獅子舞や山車の展示、民踏大会、春の舟遊、縁日大会などが開催される。 |
| 開催場所 | 埼玉県川越市 中心市街地 |
| 時期 | 3月下旬~5月上旬 |
| 問合せ | 公益社団法人 小江戸川越観光協会 TEL:049-227-8233 川越市 産業観光部 観光課 観光企画担当 〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1 TEL:049-224-5940(直通) FAX:049-224-8712 |
| 参考 | 小江戸川越観光協会 |
小江戸川越春まつりのくわしい記事
春のぼたん祭 東京都台東区のお祭り
徳川家康公を神様としてお祀りする神社でぼたんを愛でるお祭り。500株以上のぼたんがあでやかに咲き誇る。

| 名称 | 春のぼたん祭 |
| 概要 | 上野東照宮ぼたん苑で開かれるぼたんを愛でるお祭り。中国牡丹、アメリカ品種、フランス品種を含め500株以上のぼたんがあでやかに咲き誇る。 連なる番傘に燈篭、五重塔の眺望が見せる江戸情緒とあわせて楽しむ事ができる。 |
| 開催場所 | 上野東照宮ぼたん苑 |
| 時期 | 4月上旬ー 5月上旬 |
| 問合せ | 上野東照宮ぼたん苑 |
| 参考 | 春のぼたん祭 – 上野東照宮ぼたん苑 |
春のぼたん祭のくわしい記事
御柱祭 上社 山出し祭 長野県諏訪市のお祭り
約10トンの巨木を山から里へ勇敢な男たちが曳き落とす7年に1度の大祭。コロナ禍の影響を受け今回はトレーラーで運搬。

御柱祭 上社 山出し祭のくわしい記事
御柱祭 下社 山出し祭 長野県諏訪市のお祭り
約10トンの巨木を山から里へ勇敢な男たちが曳き落とす7年に1度の大祭。

御柱祭 下社 山出し祭のくわしい記事
| 名称 | 式年造営御柱大祭(御柱祭) |
| 概要 | 7年に1度寅と申の年に、八ヶ岳山麓・霧ケ峰から16本のモミの木を切り出し諏訪大社の上社本宮、上社前宮、下社秋宮、下社春宮の4宮の四隅に1本づつ建てる。 上社と下社それぞれに山出し祭と里引き祭がありそれらをまとめて御柱祭と言う。 見どころは木落とし坂での「木落とし」。モミの巨木にまたがり急斜面を100mほど滑り落ちる。 |
| 開催場所 | 〒392-0015 長野県諏訪市中洲宮山1 諏訪大社 上社本宮 〒391-0013 長野県茅野市宮川2030 諏訪大社 上社前宮 〒393-0092 長野県諏訪郡下諏訪町大門193 諏訪大社 下社春宮 〒393-0052 長野県諏訪郡下諏訪町 5828 諏訪大社 下社秋宮 |
| 時期 | 上社 山出し祭は4月上旬 里引き祭は5月上旬 下社 山出し祭は4月中旬 里引き祭は5月中旬 |
| 問合せ | 諏訪地方観光連盟 御柱祭観光情報センター 〒392-8511 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 諏訪市役所経済部観光課内 TEL:0266-58-1123 FAX:0266-58-1844 営業日:平日 9:00-17:00(土・日・祝祭日を除く) ※御柱祭山出し・里曳き期間は営業 |
| 参考 | 祭りを旅する①関東甲信越編 日ノ出出版株式会社 西山哲太郎 ONBASHIRA SUWA IN SHINSHYU |
善光寺御開帳 長野県長野市のお祭り
七年に一度の最大の盛儀。絶対秘仏の「前立本尊」を本堂にお迎えする行事。

| 名称 | 善光寺御開帳 |
| 概要 | 絶対秘仏である御本尊の御身代わり「前立本尊」を善光寺の本堂にお迎えする行事。 「前立本尊」は普段は御宝庫に安置されていますが、七年に一度の御開帳の時だけ、特別にお姿を拝むことができる。 前立本尊中央の阿弥陀如来の右手に結ばれた金糸は五色の糸に変わり、白い「善の綱」として、本堂前の回向柱に結ばれる。その回向柱に触れることによって、前立本尊に触れるのと同じこととなる。 |
| 開催場所 | 〒380-0851 長野県長野市長野元善町491 |
| 時期 | 4月上旬~5月下旬 ※数えで7年に1度 ※2022年(令和4年)は4月3日(日)~6月29日(水) |
| 問合せ | 善光寺御開帳奉賛会 〒380-0904 長野県長野市七瀬中町276 長野商工会議所内 TEL:026-227-2428 FAX:026-227-2758 |
| 参考 | 善光寺御開帳 |
善光寺御開帳のくわしい記事
明治神宮 春の大祭(崇敬者の大祭) 東京都渋谷区のお祭り
新緑の美しい明治神宮で、日本伝統芸能の最高峰の人々が熟練の技を奉納する。

| 名称 | 明治神宮 春の大祭(崇敬者の大祭) |
| 概要 | 明治神宮崇敬会の会員多数参列のもとに行われる崇敬者の大祭。日本伝統芸能の最高峰とされる人々が「舞楽」、「能・狂言」、「三曲」、「邦楽邦舞」、「薩摩琵琶」など、熟練の技を奉納する。 |
| 開催場所 | 〒151-8557 東京都渋谷区代々木神園町1−1 明治神宮 |
| 時期 | 4月下旬~5月3日 |
| 問合せ | 明治神宮 〒151-8557 東京都渋谷区代々木神園町1-1 TEL:03-3379-5511(代表) |
| 参考 | 明治神宮 |
明治神宮 春の大祭(崇敬者の大祭)のくわしい記事
くらやみ祭り 東京都府中市のお祭り
くらやみの中で大太鼓の音が鳴り響く。格式と伝統を今に引き継ぐ神聖な祭。

| 名称 | くらやみ祭り |
| 概要 | 都指定無形民俗文化財「武蔵府中のくらやみ祭」として指定され、みこしや大太鼓、山車の巡行などたくさんの見所がある。 貴いものを見る事は許されないという古来から存在する儀礼に起因し、街の明かりを消した深夜の暗闇の中で行われていたため「くらやみ祭」と呼ばれるようになった。 |
| 開催場所 | 〒183-0023 東京都府中市宮町3-1 |
| 時期 | 4月30日〜5月6日 |
| 問合せ | 大國魂神社(おおくにたまじんじゃ) 〒183-0023 東京都府中市宮町3-1 TEL:042-362-2130 FAX:042-335-2621 |
| 参考 | 厄除け・厄払いは東京府中の大國魂神社 |
くらやみ祭りのくわしい記事
高岡御車山祭 富山県高岡市のお祭り
優れた工芸技術の装飾が施された高岡の御車山車。

| 名称 | 高岡御車山祭 |
| 概要 | 前田利長公を祀る高岡關野神社の春季例大祭。 一般には「山」に車をつけた「山車」が多いが、「車」に山をつけた「車山」となるのが特徴。旧市街中心部を絢爛豪華な山車(やま)7台が奉曳(ぶえい)巡行する。 山車は金工、漆工、染織等の優れた工芸技術の装飾がほどこされており、華やかな山車が特長。4月30日の宵祭りでは山車(やま)のライトアップ展示が行われる。 国の重要有形民俗文化財・無形民俗文化財の両方に指定されている。 |
| 開催場所 | 富山県 高岡市 高岡市山町筋・片原町周辺 |
| 時期 | 5月1日 |
| 問合せ | 高岡御車山会館 〒933-0928 富山県高岡市守山町47-1 TEL:0766-30-2497 |
| 参考 | 高岡御車山保存会 祭りを旅する③東海・北陸編 日ノ出出版株式会社 西山哲太郎 |
高岡御車山祭のくわしい記事
福野夜高祭 富山県南砺市のお祭り
若衆の勇ましい掛け声が響き渡る極彩色の美しい行燈山車。

| 名称 | 福野夜高祭 |
| 概要 | 「ヨイヤサ、ヨイヤサ」の掛け声の掛け声と夜高節の唄声と共に、高さ7mにも及ぶ7つの町内の夜高行燈が町内を練り回します。 見どころは、行燈山車同士がすれ違う時の引き合い。勇ましい掛け声とともに若衆が相手方の行燈を蹴ったり、自らの台棒を相手の台棒にくぐらせてひっくり返そうとしたりと激しい壊し合いをします。 |
| 開催場所 | 富山県南砺市福野地域 |
| 時期 | 5月1日~3日 |
| 問合せ | (一社)南砺市観光協会 〒939-1852 富山県南砺市是安206-22(JR城端駅内) TEL:0763-62-1201 FAX: 0763-62-1202 |
| 参考 | 旅々なんと 祭りを旅する③東海・北陸編 日ノ出出版株式会社 西山哲太郎 |
福野夜高祭のくわしい記事
常陸大津の御船祭 茨城県北茨城市のお祭り
5年に1度行われる大津の春の大祭。300人の曳き手が御輿を乗せた神船を曳きまわす。

| 名称 | 常陸大津の御船祭 |
| 概要 | 大津町の佐波波地祇(サワワチギ)神社で、5年に1度、5月2-3日に行われる春の大祭。 神船の両側に海の幸を描き、御輿を乗せた神船を、水主(歌子)の歌う御船歌や囃しにあわせ300人ほどの曳き手に曳かれ町中を練り歩く。 船底に車輪はなく、ソロバンとよばれる井桁状に組んだ木枠100丁を敷き、20、30人の若者が船縁にとりつき左右に揺らしながら木枠の上を滑らすように曳いていくという、見ごたえのある勇壮な祭り。国の指定重要無形民俗文化財。 常陸大津の御船祭ポスター 常陸大津の御船祭チラシ 北茨城春のお祭りwith花火 マルシェ出店者一覧 |
| 開催場所 | 茨城県北茨城市大津町 |
| 時期 | 5月2・3日 5年に1度 |
| 問合せ | 北茨城市観光協会 〒319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630番地 TEL:0293-43-1111 |
| 参考 |
常陸大津の御船祭のくわしい記事
鉄砲洲稲荷神社例大祭 東京都中央区のお祭り
江戸時代の新富座の賑わいを垣間見る。本格的な舞台と衣装で奉納される子ども歌舞伎。

| 名称 | 鉄砲洲稲荷神社例大祭 |
| 概要 | 3年に1度、本社神輿の渡御が行われ、毎年「新富座こども歌舞伎例大祭奉納公演」として小中学生らによる歌舞伎が奉納される。 |
| 開催場所 | 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目6−7鉄砲洲稲荷神社 |
| 時期 | 5月2~5日 |
| 問合せ | 鐵砲洲稲荷神社 〒104-0043 東京都中央区湊1-6-7 TEL:03-3551-2647 FAX:03-3551-2645 |
| 参考 | 鐵砲洲稲荷神社 |
鉄砲洲稲荷神社例大祭のくわしい記事
越中八尾曳山祭 富山県富山市のお祭り
町人文化を象徴する、美術工芸の粋を集めた豪華な6基の曳山。

| 名称 | 越中八尾曳山祭 |
| 概要 | 家の軒下には松飾りが挿され、朝方より獅子舞、神輿、そして6基の曳山が曳山囃子を演奏しながら若者達が各町揃いの法被を羽織って厳かに渡御する。夜には1,000余の灯がともる堤灯山車となり、坂の町を練り歩きます。 6町が曳山、1町が獅子(獅子舞)をそれぞれ保有し祭礼を執り行っている。 曳山は江戸時代富山藩の御納戸所として栄華を極めた町人文化の象徴であり、裕福な豪商の旦那衆によって造りあげられたもの。 |
| 開催場所 | 富山県富山市八尾地域 |
| 時期 | 5月3日 |
| 問合せ | 越中八尾観光協会 富山市八尾町上新町2898-1 TEL:076-454-5138 FAX:076-454-6321 Email: kankou02@cty8.com |
| 参考 | 越中八尾観光協会 |
越中八尾曳山祭のくわしい記事
加須市民平和祭 埼玉県加須市のお祭り
「こいのぼりのまち」加須で、全長100mの巨大こいのぼりをクレーンを使ってあげる。壮大なこいのぼり。

| 名称 | 加須市民平和祭 |
| 概要 | 全長100メートル、重さ330キログラム、目玉の直径10メートルの巨大こいのぼりが利根川河川敷緑地公園の大空にあげられる。 加須市の鯉のぼり産業は明治時代から続いており、全長100メートルのジャンボこいのぼりは、昭和63年に開催された「さいたま博」に合わせ、加須青年会議所により加須市のPR作品として制作された。その後、平成元年第1回加須市民平和祭で公式に初遊泳された。現在は4世が活躍している。 |
| 開催場所 | 〒347-0001 埼玉県加須市大越 |
| 時期 | 5月3日 |
| 問合せ | 加須市 経済部 観光振興課 〒347-8501 埼玉県加須市三俣二丁目1番地1 TEL:0480-62-1111(代表) FAX:0480-62-1934 |
| 参考 |
加須市民平和祭のくわしい記事
鳥見神社の獅子舞 千葉県印西市のお祭り
いにしえより受け継がれてきた悪魔払いと豊作を祈念した獅子舞。ジジ(親獅子)、セナ(子獅子)、カカ(雌獅子)の3匹の獅子が舞う。

| 名称 | 鳥見神社の獅子舞 |
| 概要 | 保存会によって獅子舞が、毎年5月3日の例大祭で奉納される。獅子舞は、悪魔払いと豊作を祈念して行われ、この日を「おこと」という。 舞人は、氏子の青年男子が選ばれ、ジジ(親獅子)・セナ(若獅子)・カカ(雌獅子)の3匹によって舞わる。舞は「初の切」・「二の切」・「弓越えの舞」・「寝起きの舞」・「三角の舞」・「みみず拾いの舞」・「けんかの舞」・「仲直り三角の舞」「くじびきの舞」等で構成される。 着物や帯を獅子舞人につけて舞ってもらうと幸福になると言われている。千葉県無形民俗文化財。 |
| 開催場所 | 千葉県 印西市 平岡1476 平岡鳥見神社 |
| 時期 | 5月3日 |
| 問合せ | 印西市役所教育委員会 教育部生涯学習課文化係 TEL: 0476-33-4714 FAX: 0476-42-0033 |
| 参考 | 鳥見神社の獅子舞[県指定無形民俗文化財] |
鳥見神社の獅子舞のくわしい記事
小田原北條五代祭り 神奈川県小田原市のお祭り
北条五代歴代城主を模した武者たちが小田原市内を練り歩く。総勢1,600名の大行列。

| 名称 | 小田原北條五代祭り |
| 概要 | 北条五代歴代城主を模した武者行列と、吹奏楽部や陸上自衛隊の音楽隊、神輿など総勢1600名が勇壮に市中を練り歩く。小田原市最大のイベント。 |
| 開催場所 | 小田原市内 |
| 時期 | 5月3日 |
| 問合せ | 一般社団法人 小田原市観光協会 |
| 参考 |
小田原北條五代祭のくわしい記事
春日部大凧あげ祭り 埼玉県春日部市のお祭り
江戸川河川敷で、子どもたちの健康と成長を願いながら百数十人が協力して大空に大凧を揚げる。

| 名称 | 春日部大凧あげ祭り |
| 概要 | 江戸川河川敷で、大凧(縦15メートル、横11メートル、重さ800キログラム)、小凧(縦6メートル、横4メートル、重さ150キログラム)が揚げられる。 凧は、和紙と竹で3カ月もかけて春日部市「庄和大凧文化保存会」の会員によって作られ、大凧の凧文字はその年の世相を反映した文字を公募により選定、子凧文字は市内の小学5年生から募集し選定している。 大凧を揚げる前に、その年に初節句を迎える子どもたちの健康と幸福な成長を願う儀式が行われ、その後、上若(かみわか)組と下若(しもわか)組それぞれの大凧を揚げる。大凧を揚げるのは百数十人。見物客は10万人以上。江戸川河川敷を埋めた人々が見守る中、大凧が空へ舞い揚がる。 |
| 開催場所 | 〒344-0102 埼玉県春日部市西宝珠花83 西宝珠花地先江戸川河川敷 |
| 時期 | 5月3日・5日 |
| 問合せ | 春日部市大凧あげ祭り実行委員会事務局 TEL:048-736-1111 |
| 参考 | 春日部大凧あげ祭り 春日部市 春日部大凧あげ祭り |
春日部大凧あげ祭りのくわしい記事
清正公大祭 東京都港区のお祭り
加藤清正公にあやかった白金台の祭り。葉菖蒲の入った勝守(かちまもり)で勝負に勝つ。

| 名称 | 清正公大祭 |
| 概要 | 加藤清正公が祀られている覚林寺で行われる。武運の強かった清正公にあやかリ、「苦悩に打ち勝つ」という願いを込め「葉菖蒲入リのお勝守」が授与される。 祭りの時期は天神坂の上まで露店が並ぶ。 |
| 開催場所 | 〒108-0071 東京都港区白金台1丁目1−47 |
| 時期 | 5月4・5日 |
| 問合せ | |
| 参考 |
清正公大祭のくわしい記事
相模の大凧まつり 神奈川県相模原市のお祭り
約950kgの凧が相模の大空を舞う。保存会を立ち上げ、日本一を自負する大人達の本気の凧あげ。

| 名称 | 相模の大凧まつり |
| 概要 | 天保年間から受け継がれてきた相模原市の伝統行事の一つ。新磯(新戸、上磯部、下磯部、勝坂)地区で、「相模の大凧文化保存会」によって活動が続いている。 なかでも、新戸会場の八間凧は、14.5メートル四方、約950kgものサイズであり、毎年揚げているものとしては日本一の大きさを誇っている。毎年、公募により選ばれた題字が書かれる。 |
| 開催場所 | 神奈川県相模原市相模川新磯地区河川敷会場 (1)新戸会場(新戸スポーツ広場) (2)勝坂会場(新戸スポーツ広場) (3)下磯部会場(磯部頭首工下流) (4)上磯部会場(三段の滝下広場) |
| 時期 | 5月4日・5日 |
| 問合せ | (~4/14)新磯まちづくりセンター TEL:046-251-0014 (4/15~)相模原市コールセンター TEL:042-770-7777 |
| 参考 |
相模の大凧まつりのくわしい記事
間々田のじゃがまいた 栃木県小山市のお祭り
「ジャーガマイタ、ジャガマイタ」の掛け声と共に蛇を池に入れ、邪気を払い、雨乞いを行う。

| 名称 | 間々田のじゃがまいた |
| 概要 | 長さ15mを越える龍頭蛇体の巨大な蛇(ジャ)を担ぎ「ジャーガマイタ、ジャガマイタ」のかけ声とともに町中を練り歩く。 主役となるのは子供たちで、田植えの時期を前に五穀豊穣や疫病退散を祈願する。蛇体を使って邪気を祓ったり、蛇体に災厄を託して送ったりする形態の蛇祭りで、この種の行事の典型例として重要である一方、祭りにたくさんの蛇体が登場するという、他の類似の祭りには見られない特徴がある。 また蛇体を池に入れ、農作物のための降雨を祈る雨乞いの要素も見られ、国の重要無形民俗文化財に指定された。 |
| 開催場所 | 〒329-0205 栃木県小山市間々田2330-1 間々田八幡宮 |
| 時期 | 5月5日 |
| 問合せ | 間々田八幡宮 〒329-0205 栃木県小山市間々田2330-1 TEL/FAX:0285-45-1280 Mail:info@mamada-hachiman.jp |
| 参考 | 間々田八幡宮 |
間々田のじゃがまいたのくわしい記事
白髭神社ぼんでん祭り 東京都墨田区のお祭り
隅田川に大きなぼんでんを立て、五穀豊穣と水の害が起こらないことを祈願する。町内の世話人が引き継ぐ伝統行事。

| 名称 | 白髭神社ぼんでん祭り |
| 概要 | 「ぼんでん」とは御幣のことで、世話人が早朝から神社に集まって、ぼんでん(御幣)を調製。完成した ぼんでん(御幣)を神前に供え、祭典の後、隅田川川岸にて神事が斎行される。 稲の花(穂)が風の害に遭わぬようにと祈念したことから、鎮花祭ともよばれている。 |
| 開催場所 | 〒131-0032 東京都墨田区東向島3丁目18−3 |
| 時期 | 5月5日 |
| 問合せ | 白鬚神社 |
| 参考 |
白髭神社ぼんでん祭りのくわしい記事
宝の舞 東京都台東区のお祭り
宝童子が宝船を曳いて浅草寺を練り歩く。わかりやすく、微笑ましい端午の節句。

| 名称 | 宝の舞 |
| 概要 | 端午の節句に奉演される寺舞で、観音さまの福徳に感謝するとともに子供の成長を願う行事。 ご本尊の示現に関わった檜前浜成・竹成兄弟が漁師であったことにちなみ、漁師の衣装をまとった宝童子が宝船を曳いて練り歩く。 |
| 開催場所 | 〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−1 浅草寺 |
| 時期 | 5月5日 |
| 問合せ | 浅草寺 〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−1 TEL:03-3842-0181 |
| 参考 | 聖観音宗 あさくさかんのん 浅草寺 公式サイト |
宝の舞のくわしい記事
相模国府祭 神奈川県中郡大磯町のお祭り
「暴れ神輿」「鷺の舞」「チマキ撒き」と特長豊かな神事が目白押し。平安時代から続く神奈川県の無形民俗文化財。

| 名称 | 相模国府祭 |
| 概要 | 相模の六社が集う祭りで、 1000年以上の歴史を持つ神奈川 県の無形民俗文化財。 相模国の行政なる長、国司が相模国の天下泰平と五穀豊穣を神々に祈願したものがはじまりといわれている。 神揃山では、相模国の成立にあたり論争の模様を儀式化した神事である座問答やチマキ撒きが行われ、大矢場(現馬場公園)では、三種類の舞(鷺の舞・龍の舞・獅子の舞)が奉納される。 |
| 開催場所 | 〒259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷 六所神社、神揃山、馬場公園 |
| 時期 | 5月5日 |
| 問合せ | 大磯町 産業環境部 産業観光課 観光推進係 〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1398-18 TEL:0463-61-4100(内線:334) |
| 参考 | オマツリジャパン |
相模国府祭のくわしい記事
長崎獅子祭 東京都豊島区のお祭り
豪華な羽と袴のいで立ちで、長崎神社周辺を獅子が舞い踊る。

| 名称 | 長崎獅子祭 |
| 概要 | 獅子頭を被った三頭の獅子が、腹につけた太鼓を打ち鳴らしながら長崎神社周辺を舞い踊る。元禄年間から伝承される豊島区の民俗芸能。区の無形民俗文化財にも指定されている。 獅子は華やかな盛装とボリュームのある獅子頭が特徴的で「病気平癒」や「五穀豊穣」を願い舞う。 |
| 開催場所 | 〒171-0051 東京都豊島区長崎1丁目9-4長崎神社周辺 |
| 時期 | 5月の第2日曜日 |
| 問合せ | 長崎神社 〒171-0051 東京都豊島区長崎1丁目9-4 |
| 参考 | 長崎獅子舞 – オフィシャルホームページ! |
長崎獅子祭のくわしい記事
曽我の傘焼きまつり 神奈川県小田原市のお祭り
傘を燃やして松明にしたという「曽我兄弟」の故事にちなんだお祭り。願いを込めて傘を燃やす。

| 名称 | 曽我の傘焼きまつり |
| 概要 | 日本三大仇討ちのひとつとして数えられる「曽我物語」の曽我十郎・五郎兄弟が父の仇を討つ際に、傘を燃やして松明にしたという故事にちなんだお祭り。 人形芝居、松明行列が行われた後、 梅の里センター 駐車場にて傘焼きが行われる。 曽我の里において愛され大切に守り伝えられてきた伝統ある祭り。 |
| 開催場所 | 〒250-0205 神奈川県小田原市曽我別所807番地17 小田原市梅の里センター |
| 時期 | 5月中旬 |
| 問合せ | 曽我兄弟遺跡保存会 |
| 参考 | 小田原・曽我の傘焼きまつり 曽我兄弟遺跡保存会 |
曽我の傘焼きまつりのくわしい記事
神田祭り 東京都千代田区のお祭り
日本三大祭り、江戸三大祭りのダブルタイトルを持つキングオブまつり。その規模の大きさはまさに「天下祭」。

| 名称 | 神田祭り |
| 概要 | 江戸三大祭(他は山王祭、三社祭or深川祭)の一つであり、日本の三大祭(他は京都の祇園祭、大阪の天神祭の一つでもある日本を代表するお祭り。 隔年で行われ神幸祭、御輿宮入、太鼓フェスティバル、例大祭が主な行事。「神田明神祭」とも呼ばれている。 |
| 開催場所 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目16−2 |
| 時期 | 5月中旬 |
| 問合せ | 神田明神 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 TEL:03-3254-0753 FAX:03-3255-8875 |
| 参考 | 神田祭特設サイト |
神田祭りのくわしい記事
三社祭(浅草神社例大祭) 東京都台東区のお祭り
江戸下町の風情を残した勇壮で華やかな江戸を代表する大祭り。東京スカイツリーとの夢の共演。

| 名称 | 三社祭(浅草神社例大祭) |
| 概要 | 江戸風情を残しつつ勇壮で華やかな神輿渡御を主に行われる東京の初夏を代表する風物詩の一つ。 初日は、お囃子屋台をはじめ鳶頭木遣りや浅草の各舞、また芸妓連の手古舞や組踊り等で編成された「大行列」、「神事びんざさら舞」が奉納される。 二日目は、「例大祭式典」が斎行され、その後に「町内神輿連合渡御」によって浅草氏子四十四ヶ町の町内神輿約百基が神社境内に参集し、一基ずつお祓いを受けて各町会を渡御する。 最終日は、宮神輿三基「一之宮」「二之宮」「三之宮」の各町渡御として、早朝には神社境内から担ぎ出される「宮出し」が行われ、日中は氏子各町を三方面に分かれ渡御し、日没後に神社境内へ戻る「宮入り」を迎えて祭礼行事が終わる。 期間中は浅草の街がお祭り一色に彩られ、神社では各神事が斎行されると共に、境内や神楽殿においても様々な舞踊が披露される。 |
| 開催場所 | 〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−1 |
| 時期 | 5月第3週の金・土・日曜日 |
| 問合せ | 浅草神社 |
| 参考 | 浅草神社 |
三社祭(浅草神社例大祭)のくわしい記事
浅草寺 白鷺の舞 東京都台東区のお祭り
優雅な笛、太鼓に合わせて白鷺達が浅草寺の境内を美しく舞う。浅草寺絵巻から生まれた貴重な舞い。

| 名称 | 浅草寺 白鷺の舞 |
| 概要 | 昭和43年(1968)に明治100年記念(東京100年)行事として始められ、『浅草寺縁起』(寛文縁起)に描かれる「白鷺の舞」を再興した寺舞。 鷺舞の神事は京都八坂神社が起源とされ、浅草寺の舞はその鷺舞を参考に、寺舞保存会によって演じられている。 白鷺の装束をまとった踊子が舞い、武人、棒ふり、餌まき、楽人、守護童子などが、「白鷺の唱」を演奏しながら練り歩く。 |
| 開催場所 | 〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−1 |
| 時期 | 4月第2日曜日、5月三社祭、11月3日 |
| 問合せ | 浅草寺 〒111-0032 東京都台東区浅草2-3-1 TEL:03-3842-0181 |
| 参考 | 聖観音宗 あさくさかんのん 浅草寺 公式サイト |
浅草寺 白鷺の舞のくわしい記事
花園神社例大祭 東京都新宿区のお祭り
繁華街新宿が一変する、新宿の大通りでの神輿の御渡り。

| 名称 | 花園神社例大祭 |
| 概要 | 繁華街新宿の靖国通り、新宿通り、明治通りで花園神社の本社神輿と雷電神輿の二基が練り歩く。陰の年には八ヶ町の神輿が集合し、連合渡行が行われる。境内には露店が多数出る。 |
| 開催場所 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目17−3 |
| 時期 | 5月の28日に一番近い土・日・月曜日 |
| 問合せ | 花園神社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目17−3 03-3209-5265 |
| 参考 | 東京都新宿鎮座 花園神社 |
花園神社例大祭のくわしい記事
湯河原 湯かけまつり 神奈川県足柄下郡のお祭り
風呂桶を持って参加する温泉地ならではのお祭り。びしょ濡れは必至。

| 名称 | 湯河原 湯かけまつり |
| 概要 | 神奈川県と熱海市の境に流れる千歳川の上流「藤木川」の不動滝から泉公園までの約2kmの道を桶の神輿が「湯」を浴びながら練り歩く。 沿道には温泉の「湯」が入った1,000個の樽と湯桶約5,000個が用意され、約60tものお湯を観客が神輿めがけて勢いよく浴びせかける。 湯の効能が高いことから温泉の湯を樽に詰め、大名家や御用邸に献上した古事が始まりとされており、献湯神輿の出発に際し、道中の安全を祈願してお湯をかけ御祓(おはらい)をする儀式があり、これを再現したもの。 |
| 開催場所 | 〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上566 |
| 時期 | 5月の第4土曜日 |
| 問合せ | (一社)湯河原温泉観光協会 TEL:0465-64-1234 |
| 参考 | 湯河原温泉 公式観光サイト |
湯河原 湯かけまつりのくわしい記事
御神火祭 栃木県那須郡のお祭り
白面金毛九尾狐太鼓と大松明(御神火)が創る狐空間。山の怒りを鎮めるために始まった火祭り。

| 名称 | 御神火祭 |
| 概要 | 松明を持った100名の白装束の行列が那須温泉神社から殺生石まで行列し、大松明(御神火)へ火をつける。暗闇の中、大松明(御神火)の炎が大きく燃え盛り、那須高原に古くから伝わる白面金毛九尾の狐太鼓が演奏される。 |
| 開催場所 | 〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本 殺生石 |
| 時期 | 5月下旬 |
| 問合せ | 一般社団法人 那須町観光協会 〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本182 TEL:0287-76-2619 |
| 参考 | 一般社団法人 那須町観光協会 |
御神火祭のくわしい記事
蓬莱橋ぼんぼり祭り 静岡県島田市のお祭り
世界一長い木造橋がぼんぼりの灯りで幻想的に。江戸から人と人を繋いできた橋。

| 名称 | 蓬莱橋ぼんぼり祭り |
| 概要 | 世界一長い木造橋、蓬莱橋にぼんぼりで装飾。昼間は詩吟や舞踊、太鼓の演奏などで賑やか、夜はぼんぼりの灯りで幻想的なお祭り。 蓬莱橋は江戸から明治への時代の移り替わりの中、牧之原大茶園の開墾を支えてきた。大井川との文化と共にそこに住む人との交流を深め、そして蓬莱橋を後世に残すことを目的に開催されている。 |
| 開催場所 | 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目22−14 |
| 時期 | 5月下旬 |
| 問合せ | 蓬莱橋ぼんぼり祭り実行委員会 |
| 参考 | 島田市観光協会 |
蓬莱橋ぼんぼり祭りのくわしい記事
湯島天満宮例大祭&五條天神社例大祭 東京都文京区のお祭り
学問の神様が祀られる神社で執り行われる天神祭。湯島周辺で威勢の良い神輿が練り歩く。隣町では五條天神社例大祭が同時開催。

| 名称 | 湯島天満宮例大祭 |
| 概要 | 学問の神様、菅原 道真が祀られる神社で執り行われる例大祭で天神祭とも呼ばれる。 通常、祭典自体は5月25日に固定されているが、鳳輦・神輿の渡御や神楽などの催し物は25日に近い週末に行なう。 |
| 開催場所 | 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目30−1 |
| 時期 | 5月下旬 |
| 問合せ | 湯島天神(湯島天満宮) 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目30−1 TEL:03-3836-0753 |
| 参考 | 湯島天神公式サイト |

| 名称 | 五條天神社例大祭 |
| 概要 | 3年に一度の本祭では土曜日の夕刻に町神輿が連合渡御し、日曜日には終日、本社神輿(千貫神輿)と鳳輦の華やかなお神輿が町内を巡る。 それ以外の年は、里神楽奉納・町神輿の巡行・奉納弓道大会が行われる。 |
| 開催場所 | 〒110-0007 東京都台東区上野公園4−17 |
| 時期 | 5月下旬 |
| 問合せ | 五條天神社 03-3821-4306 |
| 参考 |
湯島天満宮例大祭&五條天神社例大祭のくわしい記事
素盞雄神社天王祭&葛飾菖蒲まつり 東京都荒川区と葛飾区のお祭り
神輿を激しく振り、夏の疫病をはらい落とす。宿場町千住の初夏のお祭り。
江戸時代から続く花菖蒲の名所。200種類の花菖蒲が咲き誇る。

| 名称 | 素盞雄神社天王祭 |
| 概要 | 人や物の行き来が盛んな街道の夏に流行する疫病を、激しい神輿振りによって、御祭神の神威をより一層振り起こして祓う悪疫退散・除災招福・郷土繁栄を願う祭禮。 宵宮祭・例大祭は、61ヶ町総代をはじめ氏子崇敬者の参列のもと、厳粛な祭儀が斎行される。このおごそかな祭典を境として、氏子61ヶ町が勇壮華麗な祭一色へと染まっていく。 令和5年 素盞雄神社天王祭 巡行図 |
| 開催場所 | 〒116-0003 東京都荒川区南千住6丁目60−1 |
| 時期 | 5月下旬-6月上旬 |
| 問合せ | 素盞雄神社 |
| 参考 | 素盞雄神社(すさのお神社)素盞雄大神と飛鳥大神が御祭神|天王祭 |

| 名称 | 葛飾菖蒲まつり |
| 概要 | 「堀切菖蒲園」と「都立水元公園」で行われる菖蒲を愛でるお祭り。 「堀切菖蒲園」に咲き誇る花菖蒲は、浮世絵師・歌川広重をはじめとした多くの画家に描かれ、江戸の名所のひとつとして古くから知られている。約200種6,000株の花菖蒲が美しく咲き誇る。 期間中の日曜には、太鼓演奏などのステージショーやパレードが開催される。期間限定で夜間にはライトアップがされることがある。 「都立水元公園」は、東京都で唯一の水郷景観をもった公園といわれ、都内では最大級の花菖蒲園を有している。約100種14,000株の花菖蒲が咲き乱れる。 期間中の土・日曜には、公園内にある野外ステージで民謡踊りやカラオケ大会が行われる。また、露店なども出店し、まつりムードを盛り上げる。 葛飾菖蒲まつり リーフレット 2023 |
| 開催場所 | 〒124-0006 東京都葛飾区堀切2丁目19−1 |
| 時期 | 5月下旬-6月中旬 |
| 問合せ | 葛飾区観光課 |
| 参考 | 2023葛飾菖蒲まつり|葛飾区公式サイト |
素盞雄神社天王祭&葛飾菖蒲まつりのくわしい記事
以上、「5月のお祭り」でした。他の月のお祭りもまとめています。どうぞ以下からご覧ください。
1月のお祭り 2月のお祭り 3月のお祭り 4月のお祭り 5月のお祭り 6月のお祭り 7月のお祭り 8月のお祭り 9月のお祭り 10月のお祭り 11月のお祭り 12月のお祭り