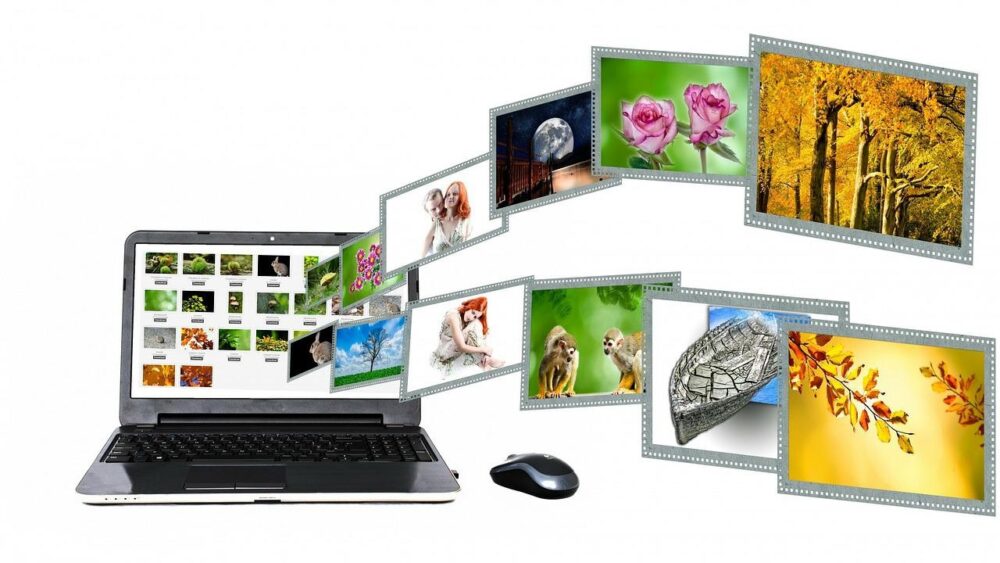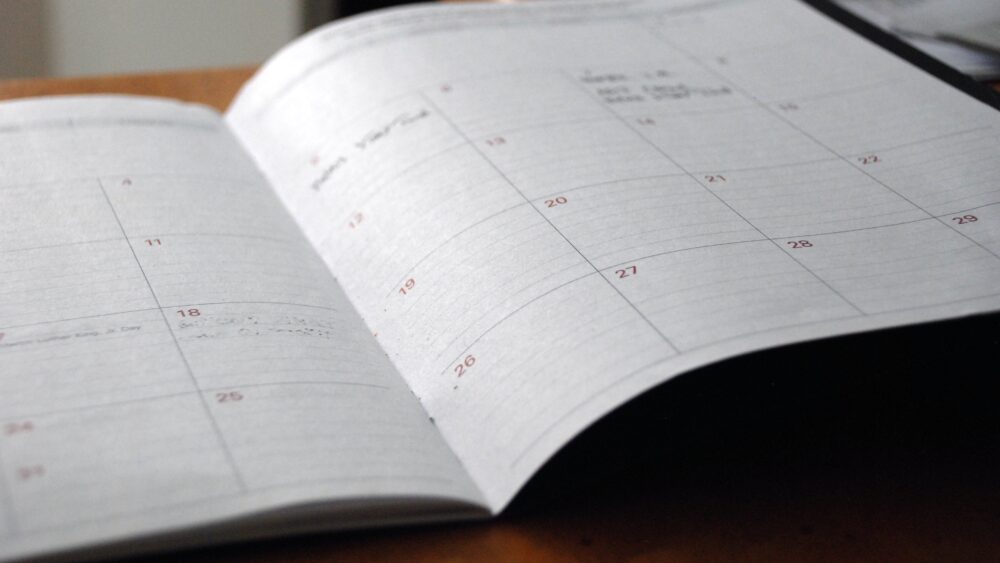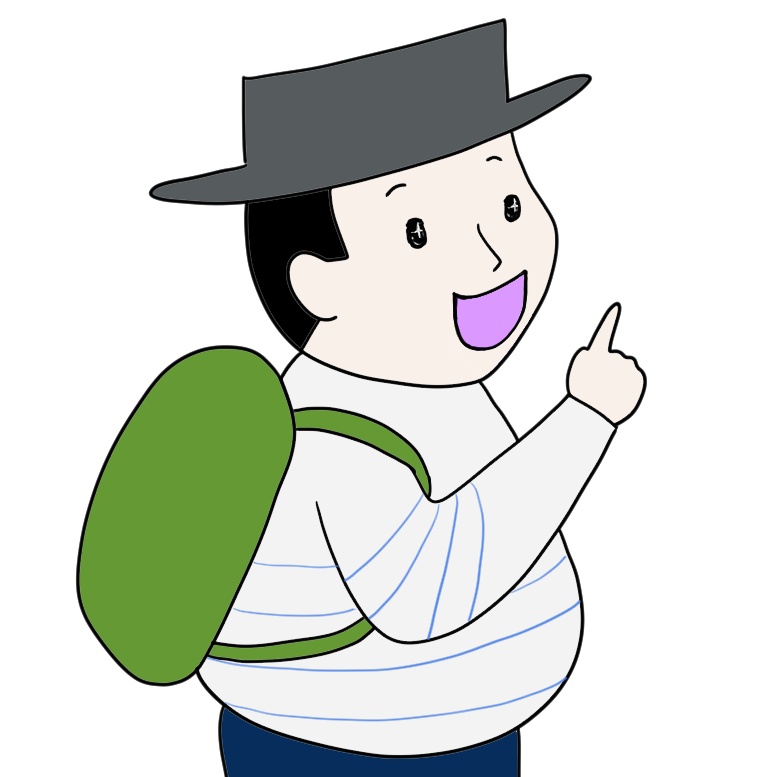お祭りと言えばやっぱり威勢の良い掛け声で街を練り歩くお神輿を想像する人が多いのではないでしょうか。そんな神輿ですが担ぎ方が変わっていたり、形が変わっていたり、大量の水をかけたりと面白いお神輿がいっぱいあります。そんな神輿のお祭りをご紹介します。
詳細記事はリンクをクリックしてご覧ください。
目次
はむら花と水のまつり 4月東京都羽村市のお祭り
色鮮やかな桜と色とりどりのチューリップに囲まれて春を感じる神輿の川入れ。
| はむら花と水のまつり | |
 | 【場所】 東京都羽村市羽東 稲荷神社、多摩川周辺 |
| 【時期】4月初旬-中旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 前期が「さくらまつり」、後期が「チューリップまつり」として開催される。 「さくらまつり」期間中は玉川上水沿い・羽村堰周辺に咲く約200本の桜がライトアップされ、4月の第2日曜日は市内各所の神社から山車や神輿が練り歩き、神輿が川を渡る。 「チューリップまつり」は、約35万球のチューリップが周囲一帯を彩る。 | |
かなまら祭 4月神奈川県川崎市のお祭り
街がピンク一色に染まる。堂々とち◯こを担いで子孫繁栄・安産・縁結びを願う奇祭。
| かなまら祭 | |
 | 【場所】 若宮八幡宮 〒210-0802 神奈川県川崎市川崎区大師駅前2丁目13−16 |
| 【時期】4月の第1日曜日 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 男根をかたどった3基の神輿がかつぎ出される。子授けや縁結び、現在ではエイズ除けの祭りとしても有名で、外国人観光客も大勢訪れる。 元々金山神社は鍛冶の神様を祀る神社であったが、江戸時代に川崎宿の飯盛女(遊女)たちの病除け に端を発し、かなまら祭りが行われるようになった。春になると草木が芽を出して再生することから、自分たちの体の再生を願って飯盛女たちが地面にゴザを敷いて下半身の病除けを祈願した。 海外の様々なメディアで取り上げられたこともあり、「かなまら祭」のおおらかでひらかれた雰囲気から、外国人にも人気があり「うたまろフェスティバル」として大師の風物詩となっている。名物の男性器をかたどった飴やグッズも人気。 かなまら祭 チラシ | |
大井蔵王権現神社例大祭 4月東京都品川区のお祭り
火事や疫病から人々を救った天狗への感謝を表すお祭り。江戸時代から続く蔵王権現太鼓の奉納と宮神輿の巡行。
| 大井蔵王権現神社例大祭 | |
 | 【場所】 大井1丁目会館 〒140-0014 東京都品川区大井1丁目14−8 |
| 【時期】4月中旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 通称「天狗祭り」と呼ばれ、江戸時代に火事や疫病から大井村を救ったとされる権現神社の天狗の伝説に由来する。 最大の見どころは、巨大な天狗の面を載せた御神輿が町内を巡行すること。おしろいを塗って赤やピンクの長襦袢姿の男性たちが担ぎ手となり、独特の姿で練り歩く。また、「大井権現太鼓」の奉納演奏も行われ、迫力ある太鼓の音が祭りを盛り上げる。伝統と歴史を感じられる、地域に根差したお祭りとして親しまれている。 2023年は蔵王権現太鼓の奉納、宮神輿が巡行した。 | |
神田祭り 5月東京都千代田区のお祭り
日本三大祭り、江戸三大祭りのダブルタイトルを持つキングオブまつり。その規模の大きさはまさに「天下祭」。
| 神田祭り | |
 | 【場所】 神田明神 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 |
| 【時期】5月中旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 江戸三大祭(他は山王祭、三社祭or深川祭)の一つであり、日本の三大祭(他は京都の祇園祭、大阪の天神祭の一つでもある日本を代表するお祭り。 奇数年に行われる「本祭」と、偶数年に行われる「陰祭」があり、特に本祭は大規模で、大小約200基もの神輿が神田・日本橋・大手町・丸の内・秋葉原といった広範囲を練り歩き、街全体が活気に満ちあふれる。 鳳輦(ほうれん)や神輿、時代装束の行列が繰り広げられる「神幸祭」や、各町会の神輿が威勢よく神社を目指す「神輿宮入」は圧巻で、江戸の粋と伝統を感じさせる一大イベント。「神田明神祭」とも呼ばれている。 | |
三社祭(浅草神社例大祭) 5月東京都台東区のお祭り
江戸下町の風情を残した勇壮で華やかな江戸を代表する大祭り。東京スカイツリーとの夢の共演。
| 三社祭(浅草神社例大祭) | |
 | 【場所】 浅草寺 〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−1 |
| 【時期】5月第3週の金・土・日曜日 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 江戸風情を残しつつ勇壮で華やかな神輿渡御を主に行われる東京の初夏を代表する風物詩の一つ。 初日は、お囃子屋台をはじめ鳶頭木遣りや浅草の各舞、また芸妓連の手古舞や組踊り等で編成された「大行列」、「神事びんざさら舞」が奉納される。 二日目は、「例大祭式典」が斎行され、その後に「町内神輿連合渡御」によって浅草氏子四十四ヶ町の町内神輿約百基が神社境内に参集し、一基ずつお祓いを受けて各町会を渡御する。 最終日は、宮神輿三基「一之宮」「二之宮」「三之宮」の各町渡御として、早朝には神社境内から担ぎ出される「宮出し」が行われ、日中は氏子各町を三方面に分かれ渡御し、日没後に神社境内へ戻る「宮入り」を迎えて祭礼行事が終わる。 期間中は浅草の街がお祭り一色に彩られ、神社では各神事が斎行されると共に、境内や神楽殿においても様々な舞踊が披露される。 【2024年】 ●5月16日 19:00 本社神輿神霊入れの儀 ●5月17日 13:00 大行列 14:20 びんざさら舞奉納(社殿) 15:00 びんざさら舞奉納(神楽殿) 15:30 各町神輿神霊入れの儀 ●5月18日 10:00 例大祭式典 11:30 子之宮渡御 12:00 町内神輿連合渡御 16:00 巫女舞奉奏(神楽殿) ●5月19日 6:30 宮出し 宮出し終了後 本社神輿各町渡御 14:00 巫女舞奉奏(神楽殿) 15:00 奉納舞踊(神楽殿) 16:00 太鼓奉演(境内) 20:00 宮入り 宮入り後 本社神輿御霊返しの儀 令和6年 大行列順路 一之宮本社神輿渡御順路 二之宮本社神輿渡御順路 三之宮本社神輿渡御順路 | |
花園神社例大祭 5月東京都新宿区のお祭り
繁華街新宿が一変する、新宿の大通りでの神輿の御渡り。
| 花園神社例大祭 | |
 | 【場所】 花園神社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目17−3 |
| 【時期】5月の28日に一番近い土・日・月曜日 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 新宿の街全体がお祭りムードに包まれる活気あふれる祭り。偶数年の「本祭」と奇数年の「陰祭」があり、本祭では花園神社の本社神輿と雷電神輿の二基が、陰祭では八ヶ町の神輿が集合し、連合渡行が行われる。境内には約100の露店が並び、多くの人々で賑わう。迫力ある神輿渡御や伝統的な神事、多様な屋台グルメが楽しめる。 | |
湯河原 湯かけまつり 5月神奈川県足柄下郡のお祭り
風呂桶を持って参加する温泉地ならではのお祭り。びしょ濡れは必至。
| 湯河原 湯かけまつり | |
 | 【場所】 〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上566 |
| 【時期】5月の第4土曜日 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 温泉の恵みに感謝し、無病息災を願うお祭り。 神奈川県と熱海市の境に流れる千歳川の上流「藤木川」の不動滝から泉公園までの約2kmの道を桶の神輿が「湯」を浴びながら練り歩く。 沿道には温泉の「湯」が入った1,000個の樽と湯桶約5,000個が用意され、約60tものお湯を観客が神輿めがけて勢いよく浴びせかける。参加者はびしょ濡れになるが、それもまた祭りの醍醐味。 湯の効能が高いことから温泉の湯を樽に詰め、大名家や御用邸に献上した古事が始まりとされており、献湯神輿の出発に際し、道中の安全を祈願してお湯をかけ御祓(おはらい)をする儀式があり、これを再現したもの。 | |
湯島天満宮例大祭&五條天神社例大祭 5月東京都文京区のお祭り
学問の神様が祀られる神社で執り行われる天神祭。湯島周辺で威勢の良い神輿が練り歩く。隣町では五條天神社例大祭が同時開催。
| 湯島天満宮例大祭 | |
 | 【場所】 湯島天満宮 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目30−1 |
| 【時期】5月下旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 学問の神様・菅原道真公を祀る湯島天満宮の一年で最も重要な神事。別名「天神祭」とも呼ばれる。 例大祭の中心は、神社の神輿が氏子地域を練り歩く「神輿渡御」で、担ぎ手たちの威勢の良い掛け声が響き渡る。特に、2年に一度の本祭(偶数年)では、華やかな「鳳輦(ほうれん)」と「宮神輿」が巡行し、さらに4年ごとに宮神輿が担がれて渡御する年と、町会神輿が連合で宮入りする年が交互にある。 境内では江戸里神楽や和太鼓の奉納、生花・盆栽の展示などが行われ、多くの露店も立ち並び、下町らしい賑わいを見せる。 通常、祭典自体は5月25日に固定されているが、鳳輦・神輿の渡御や神楽などの催し物は25日に近い週末に行なう。 | |
| 五條天神社例大祭 | |
 | 【場所】 五條天神社 〒110-0007 東京都台東区上野公園4−17 |
| 【時期】5月下旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 最大の見どころは、3年に一度の本祭で巡行する千貫神輿や鳳輦(ほうれん)の大行列。上野公園から上野広小路一帯を練り歩く壮麗な光景は圧巻で、威勢の良い担ぎ手の掛け声とともに地域全体が活気に包まれる(土曜日の夕刻に町神輿が連合渡御し、日曜日には終日、本社神輿(千貫神輿)と鳳輦の華やかなお神輿が町内を巡る)。 例年行われる里神楽奉納、巫女舞、奉納弓道大会、奉納太鼓など、多彩な神賑行事も魅力。日本の伝統文化と活気を肌で感じられるお祭りとして、地元の人々だけでなく、多くの観光客で賑わう。 ちなみに五條天神社は医薬祖神である大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)、そして学問の神様である菅原道真公を祀っている。 | |
素盞雄神社天王祭 5-6月東京都荒川区のお祭り
神輿を激しく振り、夏の疫病をはらい落とす。宿場町千住の初夏のお祭り。
| 素盞雄神社天王祭 | |
 | 【場所】 素盞雄神社 〒116-0003 東京都荒川区南千住6丁目60−1 |
| 【時期】5月下旬-6月上旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 人や物の行き来が盛んな街道の夏に流行する疫病を、激しい神輿振りによって、御祭神の神威をより一層振り起こして祓う悪疫退散・除災招福・郷土繁栄を願う伝統的なお祭り。 最大の見どころは、特徴的な「二天棒神輿振り」。通常の神輿が4本や6本の担ぎ棒を使うのに対し、素盞雄神社の神輿はわずか2本の担ぎ棒で担がれ、屋根の鳳凰が地面につくほど左右に激しく振られる。この勇壮な神輿振りは都内でも珍しく、多くの見物客を魅了する。 3年に一度の「本まつり」では、千貫神輿と呼ばれる御本社大神輿が氏子61ヶ町を渡御し、それ以外の年は「氏子まつり」として100基を超える町神輿が巡行する。荒川区の無形民俗文化財にも登録されており、地域に深く根付いた夏の風物詩として親しまれている。 令和5年 素盞雄神社天王祭 巡行図 | |
六郷神社祭礼 6月東京都大田区のお祭り
平安時代から続く神社で行われる祭礼。鳩をいただく神輿が氏子町内を練り歩く。
| 六郷神社祭礼 | |
 | |
| 【場所】 六郷神社とその周辺 〒144-0046 東京都大田区東六郷3丁目10−18 | |
| 【時期】 6月3日、6月第1土曜日、日曜日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 5年に一度の本祭の年には「一之宮神輿」が、その他の年には「二之宮神輿」が氏子地域を巡行する「神幸祭」が最大の見どころ。また、数百年の伝統を持つ「神獅子」と呼ばれる子供獅子舞が奉納され、各御神酒所で披露される。 期間中は、六郷の14町から約40基もの町神輿がそれぞれの地域を渡御し、金曜日には神社で「御霊入れ」、日曜日には「御霊返し」が行われる。かつては「曳船祭」として、関東三大船祭りの一つにも数えられていた伝統ある祭り。境内には多数の露店も出店し、多くの人で賑わう。 【2024年】 ●6月3日(月) 11:00例大祭式典(式典執行) ●8日(土) 神楽奉奏13:30・14:00・16:00 子供神獅子舞奉納 13:30(道行き)・14:00(神楽殿)・16:00(神楽殿) ●9日(日) 子供神獅子舞奉納 8:30(道行き)・13:00(神楽殿)・14:30(神楽殿)・16:00(神楽殿) 御神輿渡御 宮出し 8:30・宮入り 16:45 |
鳥越祭り 6月東京都台東区のお祭り
猿田彦、手古舞連に続くのは、千貫御輿といわれるほどの東京一の重さを誇る神輿。百数十個の高張提灯も美しい下町のお祭り。
| 鳥越祭り | |
   | |
| 【場所】 鳥越神社 〒111-0054 東京都台東区鳥越2丁目4−1 | |
| 【時期】 6月9日に近い金・土・日曜日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 千貫神輿(せんがんみこし)と呼ばれる都内最大級の神輿が特徴で、その重厚さと迫力から「関東三大祭」の一つに数えられることもある。 祭りの見どころは、氏子衆が担ぐ千貫神輿が深夜まで町内を巡行する「神輿渡御」。神輿を氏子各町が引き継ぎながら担ぎ、御神輿の列の先頭には、猿田彦(天狗)や、手古舞連、子供たちの持つ五色の旗が歩く。 夕刻、神輿の弓張提灯と町会の高張提灯に火が入ると、祭りは最高潮を迎える。宮入道中は、「鳥越の夜祭り」と言われ、荘厳かつ幻想的。沿道には多くの見物客が詰めかける。 また、祭りの前日には「奉納相撲」や「子供神輿」、露店なども並び、地域全体が活気に満ち溢れる。夏の訪れを告げる下町の風物詩として、地元の人々に深く愛されている。 【2024年】 ●6月8日(土)10:00 大祭式 ●6月8日(土)町内神輿の渡御 連合参拝宮入り ●6月9日(日)千貫神輿の渡御 宮出し6:30 鳥越の夜祭り19:00時頃 宮入り21:00 |
須賀神社例大祭 6月東京都新宿区のお祭り
坂の多い街の中、本社の神輿が威勢よく練り歩く。四谷の夏を告げる例大祭。
| 須賀神社例大祭 | |
   | |
| 【場所】 〒160-0018 東京都新宿区須賀町5 | |
| 【時期】 6月上旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 隔年で「本祭」と「陰祭」があり、本祭の年には本社神輿が四谷の街を威勢よく練り歩く「神輿渡御」が行われる。陰祭の年には、氏子18ケ町の町会神輿による連合渡御が行われる。 祭りの期間中は、境内に露店が立ち並び、神楽殿では神楽が奉納されるなど、賑やかな雰囲気に包まれる。特に本社神輿の宮出しや渡御は圧巻で、多くの見物客で賑わう。 江戸時代から続く歴史を持ち、かつては「四谷の天王祭り」として江戸の五大祭りにも数えられた伝統あるお祭り。 【2023年】 ●6月2日(金) 宵宮 (前夜祭) ●6月3日(土) 例大祭々典 午後5時より和太鼓集団 荒魂 奉納太鼓 午後6時より東龍倶楽部 龍踊り奉納 ●6月4日(日) 本社神輿渡御 宮出し11:30 宮入り17:00 ●6月5日(月) 修祭 |
品川神社 例大祭&荏原神社 天王祭 6月東京都品川区のお祭り
北の天王祭と南の天王祭が同時に開催する品川っ子の特別な期間。太鼓付きの神輿が品川を練り歩く。
| 品川神社例大祭 | |
   | |
| 【場所】 品川神社 〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目7−15 | |
| 【時期】 6月上旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 「北の天王祭」として知られ、疫病除けの神である牛頭天王を祀る。 見どころは、徳川家康ゆかりの「天下一嘗の御神面」を屋根に付けた宮神輿の渡御。締め太鼓と篠笛で奏でる「品川拍子」に合わせて、担ぎ手が神輿の横棒に肩を入れ、前後左右に不規則に動かす「城南担ぎ」と呼ばれる独特の担ぎ方が特徴。特に、53段ある急な石段を宮神輿が上り下りする「宮入り・宮出し」は迫力満点。期間中は旧東海道沿いに多くの屋台が並び、街全体が祭り一色に染まる。 |
| 荏原神社 天王祭 | |
   | |
| 【場所】 荏原神社 〒140-0001 東京都品川区北品川2丁目30−28 | |
| 【時期】 6月上旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 品川の夏の風物詩として知られる例大祭。宝治元年(1247年)に京都八坂神社から牛頭天王(ごずてんのう)が勧請されたことに始まり、約780年の歴史を持つ伝統的なお祭り。 俗称「かっぱ祭り」とも呼ばれ、かつては神輿が東京湾の海中を練り歩く「海中渡御」が行われていた。これは、海から見つかったとされる牛頭天王(須佐之男尊)の御神面を神輿に付け、豊漁・豊作を祈願する神事だったため。埋め立てが進んだ現在では、海中渡御は一部異なる形で行われることもあるが、氏子各町の神輿が品川の町を勇壮に渡御し、大勢の観客で賑わう。 品川神社(北の天王祭)と対をなす「南の天王祭」としても親しまれる。 【2023年】 ●6月2日(金)14:00 大祭式 ●6月3日(土) 9:00 町内神輿宮入り ●6月4日(日)16:00 町内神輿櫻河岸渡御 |
日枝神社大祭 山王祭 6月東京都千代田区のお祭り
歴代の将軍が上覧拝礼する「天下祭」。神幸祭、連合宮入、下町連合 渡御と「天下祭」と呼ばれるのにふさわしいお江戸の大祭り。
| 日枝神社大祭 山王祭 | |
   | |
| 【場所】 日枝神社 〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目10−5 | |
| 【時期】 6月中旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 徳川将軍家の産土神(うぶすながみ)として信仰されてきた日枝(ひえ)神社の祭礼で、日本三大祭・江戸三大祭の一つに数えられる壮大な祭り。特に偶数年には「本祭」として、約300メートルにも及ぶ「神幸祭」の行列が東京都心を練り歩く。 この行列では、御鳳輦(ごほうれん)や宮神輿、山車が、王朝装束をまとった約500名の奉仕者と共に巡行し、まるで江戸時代の絵巻物が現代に蘇ったかのような荘厳な光景が広がる。徳川将軍家から「天下祭」として崇敬され、江戸城内への神輿渡御も許されるなど、幕府の手厚い庇護のもと発展してきた。 神輿が国道の起点である「日本国道路元標」に差しかかると、担ぎ手たちが一斉に神輿を高々と上げる。また、日本橋髙島屋の正面入口で行われる”差し”がみどころ。木頭(きがしら)の合図で、いくつかの神輿が威勢よく差し上げられる。 稚児行列や和菓子を奉納する「山王嘉祥祭」、そして納涼大会盆踊りなど、期間中には様々な行事が行われ、多くの人々で賑わう。 【2024年】 ●6月7日(金)6:00末社八坂神社例祭 7:45-17:45頃神幸祭 13:45日本橋御旅所祭 ●6月8日(土)16:00-17:00頃連合宮入 ●6月9日(日)9:00-14:00下町連合渡御 ●6月13日(木)-15日(土)18:30盆踊り ●6月15日(土)例祭 -皇城鎮護・都民平安祈願- ●6月16日(日)11:00煎茶礼道日 13:00山王嘉祥祭 ●6月7日(金)-16日(日)嘉祥菓子接待席(無料) 2024山王祭楽しみ方ガイド |
岩内神社 例大祭 7月北海道岩内郡岩内町のお祭り
北海道の港町で行われる神輿の渡御。市内を神輿が練り歩いた後に、供奉船で海上渡御を行う。
| 岩内神社 例大祭 | |
  | |
| 【場所】 岩内神社 〒045-0012 北海道岩内郡岩内町宮園41 | |
| 【時期】 7月7-9日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 200年以上の歴史を持つ伝統的なお祭りで古くより町民から「いわない祭り」として親しまれている。7日の宵宮祭を皮切りに、8日の本祭、そして8日と9日には神輿渡御が行われる。特に9日の夜には、国道を全面通行止めにして篝火が焚かれる中、2基の神輿が「神社坂」を一気に駆け上がる様子は圧巻。2日間、約23㎞ 練り歩いた渡御の集大成として、境内での各団体奉仕者の姿、社殿へ一気に還る神輿、担ぎ手の姿は大勢を魅了する。 期間中は、町道に100店以上の露店が立ち並び、町内外から多くの人々が訪れ賑わう。神輿渡御には約450名が奉仕し、海上渡御供奉船は十艘を超えるなど、岩内町を挙げての盛大なお祭り。 岩内神社例大祭 R6 例大祭 渡御時間表 及び 時間表 |
住吉神社例大祭 7月北海道小樽市のお祭り
ニシン漁が最盛期の頃から始まった別名「小樽まつり」。道内最大級の神輿「百貫神輿」が小樽市内を練り歩く。
| 住吉神社例大祭 | |
  | |
| 【場所】 小樽住吉神社 〒047-0014 北海道小樽市住ノ江2丁目5 | |
| 【時期】 7月中旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 小樽の総鎮守としての歴史と伝統を持つ住吉神社で執り行われる例大祭で小樽三大祭りの一つ。ニシン漁が最盛期の頃から行われ市民からは「小樽まつり」の名で親しまれている。五穀豊穣や産業繁栄、市内平安を祈願する祭りで、3日間にわたって盛大に行われる。 祭りの最大の見どころは、道内最大級の重さを誇る「百貫神輿御幸渡御(ひゃっかんみこしぎょこうとぎょ)」です。重さ約100キロの神輿が、大勢の担ぎ手に担がれて小樽の町を練り歩く様は圧巻で、沿道には多くの見物客が詰めかける。 また、歴史ある「太々神楽(だいだいかぐら)」の奉納も行われ、祭りを厳かに彩る。境内には多くの露店が立ち並び、花手水や副参道鳥居のライトアップなど、普段とは異なる幻想的な雰囲気も楽しめる。 【2023年】 ●7月14日 15:00 第二分隊発御祭 16:00 第二分隊渡御 19:00 太々神楽 ●7月15日 9:00 本隊渡御 第二分隊渡御 17:00 本隊手宮到着 18:45 百貫神輿渡御 19:00太々神楽 ●7月16日 8:00 本隊渡御 第二分隊渡御 17:00 還御祭 還御祭終了後、神社福役による餅まき 17:30 能楽奉納 演目「高砂」 |
平方のどろいんきょ 7月埼玉県上尾市のお祭り
大人達が神輿を転がして真面目に泥だらけになる、奇祭中の奇祭。
| 平方のどろいんきょ | |
  | |
| 【場所】 埼玉県上尾市大字平方 上宿地区 | |
| 【時期】 7月の中旬の日曜日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 夏祭りや天王様とも言われ、疫病退散・五穀豊穣を祈念して水を大量に民家の庭にまき、ぬかるんだ状態にして、白木の頑丈な隠居神輿を泥の中で転がしたりする全国でも大変珍しいお祭り。 『土』と『人』と『神様』が一体となったお祭りで、その泥を浴びれば、家内安全・無病息災・悪病退散の御利益があると伝えられている。 「どろいんきょ」という名称や由来については、隠居した御神輿を担ぎだして泥だらけにしたとか、隠居した人たちが余興で担いだのが始まりと等と言われている。埼玉県指定の無形民俗文化財。 |
茅ヶ崎海岸浜降祭 7月神奈川県茅ヶ崎市のお祭り
サザンビーチに並ぶ約40基の神輿。「どっこい、どっこい」の掛け声勇ましく、茅ヶ崎の神輿が「禊(みそぎ)」をする。
| 茅ヶ崎海岸浜降祭 | |
  | |
| 【場所】 茅ヶ崎西浜海岸(サザンビーチちがさき西側) | |
| 【時期】 7月第3月曜日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 早朝、茅ヶ崎市と寒川町の各神社から、白い磯着をまとった男衆がそれぞれの神輿を担ぎ、茅ヶ崎海岸を目指して練り歩く。 海岸に到着すると、神輿は波打ち際まで進み、冷たい潮水を浴びる。これは「禊(みそぎ)」と呼ばれ、神輿を清め、豊漁と安全を祈願する神事。約40基の神輿が一堂に会し、「どっこい、どっこい」という勇壮な掛け声とともに海岸を埋め尽くす様は圧巻で、「暁の祭典」とも称される。神奈川県の無形民俗文化財、かながわのまつり50選にも指定されており、多くの見物客で賑わう。 【2023年】 4:30 一番神輿が祭典会場に入場(7時までに全部の神輿が順次入場) 7:00 浜降祭合同祭開式 8:00 一斉にお発ち(各神輿が帰路へ) 9:00 終了 |
下館祇園まつり 7月茨城県筑西市のお祭り
羽黒神社を中心に開催される下館のお祭り。筑西市民に愛されながら神輿と山車が練り歩く。
| 下館祇園まつり | |
  | |
| 【場所】 茨城県筑西市 羽黒神社-駅前通り | |
| 【時期】 7月の最終木曜日から4日間 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 茨城県内屈指の夏祭りとして知られ、迫力ある神輿の渡御が最大の見どころ。 特に注目されるのは、明治時代に造られた重さ1トンの「明治神輿」、女性が担ぐ「姫神輿」、そして日本最大級とされる重さ2トンの「平成神輿」。これらの大神輿と、30基以上の子ども神輿が市街地を練り歩き、街は熱気に包まれる。 祭りの3日目には市内外の神輿・山車が一堂に会する「わっしょいカーニバル」、最終日早朝には勤行川で「川渡御」が行われる。この川渡御が祭りのフィナーレを飾り、夏の風物詩として多くの人々を魅了している。 |
羽田まつり 7月東京都大田区のお祭り
空と海のコラボ。国際空港近くで行われる昔ながらの漁師町のお祭。
| 羽田まつり | |
  | |
| 【場所】 羽田神社 〒144-0044 東京都大田区本羽田3丁目9−12 | |
| 【時期】 7月下旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 かつて漁師町として栄えた名残から通りでは大漁旗が掲げられる。最大の見どころは羽田独特の「ヨコタ」と呼ばれる神輿の担ぎ方。神輿を左右90度に大きく傾け、波に揺れる船を表現する勇壮でダイナミックな担ぎ方で、担ぎ手たちが一体となって神輿をローリングさせながら進む。 神輿の担ぎ手だけで約3,000人、見物客は3万人を超えるほど賑わい、羽田空港の氏神様であることから、航空会社の客室乗務員などがボランティアとして参加することでも知られている。町内神輿連合渡御では、多数の神輿が街を練り歩き、熱気に包まれる。 |
上溝夏まつり 7月神奈川県相模原市のお祭り
江戸時代から続く上溝の夏祭り。提灯が灯った山車と神輿が商店街を練り歩く。
| 上溝夏まつり | |
  | |
| 神奈川県相模原市中央区上溝 上溝商店街通りほか | |
| 【時期】 7月下旬の土・日曜日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 上溝に江戸末期から伝わる伝統と歴史を誇る祭りで、上溝商店街通りを歩行者天国にして開催される。日曜日の夕方頃より、郷土に古くから伝わる御輿と山車が各町内から商店街通り本町交差点の祭典本部前に集まり、御輿の渡御と山車の運行が始まる。 夜のとばりがおりる頃には、それぞれの御輿に提灯の灯がともり、更にお祭りの賑わいや華やかさを演出する。左右に振らされる神輿は圧巻の光景。 会場周辺には露店が多数立ち並び、焼きそばやかき氷などの定番グルメから地域ならではの味まで楽しめる。 |
おびひろ平原まつり 8月北海道帯広市のお祭り
北の大地の恵みに感謝する、短い夏を感じるお祭。
| おびひろ平原まつり | |
  | |
| 【場所】 北海道帯広市西2条南7丁目-11丁目及び広小路 夢の北広場 | |
| 【時期】 8月14-16日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 戦後の混乱期、市民の士気を高める「帯広平和まつり」として始まり、半世紀以上の歴史を持つ。 祭りの目玉は、先人への感謝と五穀豊穣を願う「夢降夜(ゆめふるや)」の神輿渡御、全道各地から太鼓チームが集結し迫力ある演奏を繰り広げる「平原・太鼓まつり」、そして趣向を凝らした衣装と踊りが見所の「おびひろ盆踊り」。 その他、大道芸フェスティバルや各種街区イベント、地元グルメが楽しめる「キッチン平原」など、見て参加して楽しめる催しが盛りだくさんで、帯広の短い夏を熱く華やかに彩る。 |
深川神明宮例大祭 8月東京都江東区のお祭り
「ワッショイ」の掛け声で巡幸する深川神明宮の本社神輿。氏子各町の12基の大神輿が行列を組んで連合渡御を行う。
| 深川神明宮例大祭 | |
  | |
| 【場所】 深川神明宮 〒135-0004 東京都江東区森下1丁目3−17 | |
| 【時期】 8月17日に近い日曜日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 深川神明宮の例大祭には、三年に一度の「本祭り」と、その間の年の「蔭祭り」がある。「本祭り」は特に盛大に行われ、宮神輿の巡幸や町神輿の連合渡御が最大の見どころとなる。深川の総鎮守として崇敬される深川神明宮の宮神輿が氏子十二ヶ町を巡幸し、また各町の町神輿も勢揃いして練り歩く。 特徴的なのは「水かけ祭り」とも呼ばれる勇壮な水かけで、沿道から担ぎ手に清めの水が勢いよくかけられる。掛け声は伝統的な「ワッショイ!」。 蔭祭りの年は、8月17日に近い日曜日に本殿祭のみを行い、神社としての祭礼行事はないが、町神輿の町内巡幸、子ども神輿や山車の巡幸などの祭礼行事を行う町もある。 下町らしい飾りっ気のなさの中にも、熱気と活気が溢れる祭りで、地元住民を中心に多くの人で賑わう。 2024深川神明宮例大祭MAP |
富岡八幡宮例大祭(深川八幡祭り) 8月東京都江東区のお祭り
「わっしょい、わっしょい』の掛け声と共に神輿の御渡しが行われ、沿道からは清めの水が浴びせられる、江戸の夏を象徴する「水かけ祭」。
| 富岡八幡宮例大祭(深川八幡祭り) | |
  | |
| 【場所】 東京都江東区 富岡八幡宮周辺 | |
| 【時期】 8月中旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 「深川八幡祭り」とも呼ばれ、赤坂の日枝神社の山王祭、神田明神の神田祭とともに「江戸三大祭」の一つに数えられている。 3年に一度の八幡宮の御鳳輦が渡御を行う本祭りでは、約50基の町神輿が勢揃いする連合渡御が圧巻で、「ワッショイ、ワッショイ」という威勢のいい掛け声と共に街を練り歩く。 この祭りの最大の特徴は、「水かけ祭り」とも呼ばれる豪快な「水かけ」。沿道の観衆が担ぎ手に清めの水を浴びせかけ、担ぎ手と観衆が一体となって盛り上がる光景は、まさに江戸の粋を感じさせる。 起源は1642年、徳川家光の長男家綱の世継ぎ祝賀に由来するとされ、380年以上の歴史を誇る伝統的な祭りとして、地域の人々に大切に受け継がれている。 |
亀戸天神社例大祭 8月東京都江東区のお祭り
学問の神様、下町の天神さまとして親しまれている神社で執り行われる大祭。残暑厳しい夏空の下、御神輿が威勢良く担がれる。
| 亀戸天神社例大祭 | |
  | |
| 【場所】 亀戸天神社 〒136-0071 東京都江東区亀戸3丁目6−1 | |
| 【時期】 8月下旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 学問の神様として親しまれる菅原道真公を祀る亀戸天神社で開催されるお祭り。特に4年に一度の大祭では、鳳輦(ほうれん)と呼ばれる御神輿が牛に曳かれ氏子地域を巡行し、各町の神輿も盛大に宮入りする連合渡御が行われ、江戸下町の勇壮な祭礼絵巻が繰り広げられる。 普段は静かな境内も、この期間中は紅白の提灯が揺らぎ、多くの参拝者で賑わう。また、夜には1000個以上の灯明が灯される「献灯明」が行われ、心字池に映る幻想的な光景は見る者を魅了する。地域の人々にとって、夏の終わりを告げる風物詩として親しまれている。 |
北澤八幡神社例大祭 9月東京都世田谷区のお祭り
古着とレコードの街で行う神輿の渡御。八睦会の神輿が北澤八幡神社に勢ぞろい。
| 北澤八幡神社例大祭 | |
  | |
| 【場所】 北澤八幡神社 〒155-0032 東京都世田谷区代沢3丁目25−3 下北沢駅周辺 | |
| 【時期】 9月第1土曜日、日曜日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 通称「北澤八幡秋まつり」で下北沢地区では最大級のお祭り。毎年氏子地域にある八つの睦会が順番に「年番」を担当しており、本宮では、各睦会の大小23基の神輿や太鼓が揃って宮入りするという壮大な景色が繰り広げられる。特に3年に一度行われる本社神輿(宮神輿)の渡御では、その勇壮な姿に多くの観客が沸き立つ。 境内でも、江戸神楽から雅楽、巫女舞、和太鼓など様々な催しが予定されており、下北沢一帯が祭りの熱気に包まれる例大祭。 13時からは代沢三差路に集った御神輿が北澤八幡神社に向かって宮入りへ、14時半から祭典式が齊行された後、各々の御神輿はそれぞれの地域に戻り、17時からは奉納演芸が行われる。 【2023年】 ●9月2日(土)宵宮 12:00 – 21:00 縁日 13:00 和太鼓・お囃子 14:00 – 20:00 奉納演芸 ●9月3日(日)例大祭 10:00 – 21:00 縁日 13:00 神輿宮入り 14:30 祭典式齊行 17:00 – 20:00 奉納演芸 2023年 北澤八幡神社例大祭 奉納演芸プログラム |
二宮神社秋季例大祭(生姜祭り) 9月東京都あきる野市のお祭り
無病息災を願って生姜が販売される。二宮神社へ神輿が駆け上がる、圧巻の宮入。
| 二宮神社秋季例大祭(生姜祭り) | |
  | |
| 【場所】 二宮神社 〒197-0814 東京都あきる野市二宮2252 | |
| 【時期】 9月8・9日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 あきるの三大祭りのひとつ。別名「生姜祭り」の愛称で親しまれているお祭りで、 古くから祭りに神饌の中に「牛の舌の形の餅」「子持ちの里いも」「葉根付き生姜」を備えることになっている。 二宮周辺で採れた生姜をお祭りにお供えしたことからから、二宮神社の無病息災の生姜として知られるようになり、境内には生姜売りの店が多く立ち並びたくさんの人が訪れるようになった。現在の厄除生姜の販売は毎年行列ができる。 当日は神輿の宮出し・宮入りが行われ、特に神輿が石段を駆け上がる宮入は圧巻。境内には多くの露店が立ち並び、吹奏楽や和太鼓の演奏、さらには東京都無形民俗文化財である「秋川歌舞伎」の奉納も行われ、多くの来場者で賑わう。地元に根付いた歴史あるお祭りで、「あきる野三大まつり」の一つにも数えられている。 【2023年】 ●9月8日(日)宵宮 16:00- 囃子と山車の町内巡行、府中二之宮大太鼓町内巡行、東中学校吹奏楽 16:00- 境内特設舞台 秋留台高校和太鼓、演芸大会 ●9月9日(月)例大祭 10:00- 例大祭式典 11:30- 神社神輿宮出し 14:30- 子ども神輿 16:00- 中学生神輿 15:00- 秋留台高校和太鼓 17:00- 奉納芸能大会 19:00- 神輿宮入 東京都指定無形民俗文化財「秋川歌舞伎」奉納 宮入後 |
芝大神宮 だらだら祭り 9月東京都港区のお祭り
長くつづく事から名づけられた関東のお伊勢さまのお祭り。大東京のオフィスで行われる渡御。
| 芝大神宮 だらだら祭り | |
  | |
| 【場所】 東京都港区芝大門1丁目12-7芝大神宮 | |
| 【時期】 9月11日-21日の11日間 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 毎年9月11日から21日までの11日間にもわたって行われる、期間の長さが特徴の例大祭。その長さから、江戸っ子たちが「だらだら祭り」と揶揄したことが名称の由来とされている。 江戸時代には「関東のお伊勢さま」として全国からの参拝客で賑わったため、多くの人が訪れられるよう祭礼期間が長くなったと言われている。 祭りの名物としては、邪気を払うとされる「生姜」が頒布される「生姜市」や、衣類が増え、良縁に恵まれる縁起物として知られる「千木筥(ちぎばこ)」の授与がある。期間中には、宮神輿や各町会神輿の渡御(隔年開催)も行われ、多くの人々で賑わう。 2023年だらだら祭りチラシ |
吾妻神社馬だしまつり 9月千葉県富津市のお祭り
馬が砂浜を駆け抜ける勇壮な神事と、幻想的な雰囲気の中で神輿が担がれる神事。千葉県の無形民俗文化財。
| 吾妻神社馬だしまつり | |
  | |
| 【場所】 千葉県 富津市 岩瀬海岸/吾妻神社 ※馬だしの神事は岩瀬海岸 | |
| 【時期】 9月中旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 馬だし、オブリ、神輿を中心とした神事が行われ、五穀豊穣や、海上の安全、大漁を祈願する。「馬だし」はオメシと呼ばれる神馬の鞍に神霊を移した幣束(へいそく)をつけ、2人の青年が馬の手綱を持ち両脇にしがみついて海岸を疾走する神事。 オメシが神輿に先立って神社から下山し、海岸を疾走した後、幣束を遺品の漂着地に埋める。その後、オメシは神社へ戻り、神輿が海へ入る「お浜出」が行われる。 ちなみに神霊を馬上に移し渡御する神事は飾り神輿のできる以前の祭りとして重要なもの。提灯が幻想的な雰囲気を出す19時半頃、神輿は吾妻神社に戻ってきて、祭礼が終了となる。千葉県無形民俗文化財に指定されている。 |
新宿十二社 熊野神社 例大祭 9月東京都新宿区のお祭り
大都会新宿で行われる神輿の渡御。都庁を背景に新宿の御神輿が威勢よく練り歩く。
| 新宿十二社 熊野神社 例大祭 | |
  | |
| 【場所】 新宿十二社 熊野神社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目11−2 | |
| 【時期】 9月第3土・日曜日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 江戸時代から続く伝統的なお祭りで、例年多くの参拝客で賑わう。 例大祭では、神事や雅楽の奉納、氏子による神輿の渡御などが行われる。特に、本社神輿の渡御は、十二社周辺や西新宿のオフィス街を練り歩き、多くの見物客を魅了する。 露店も多数出店し、お祭りムードを盛り上げる。伝統と現代が融合した、新宿ならではのお祭り。 |
金王八幡宮例大祭 9月東京都渋谷区のお祭り
渋谷の街に14基の神輿が繰り出す。若者の街で執り行う伝統行事。
| 金王八幡宮例大祭 | |
  | |
| 【場所】 東京都渋谷区渋 谷駅周辺 | |
| 【時期】 9月中旬 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 寛治6年(1092年)に創建された金王八幡宮の例祭として、五穀豊穣、街の繁栄、氏子崇敬者の無病息災を祈願して数百年間続けられてきた。 見どころは、渋谷の各町会から参加する14基の神輿がSHIBUYA109前に集結し、一斉に担ぎ上げられる連合渡御。迫力満点の光景は祭りの最高潮を迎え、多くの見物客で賑わう。また、境内では里神楽などの奉納行事や露店も多数出店し、国際都市渋谷ならではの多様な人々が祭りを盛り上げる。 |
勝浦大漁まつり 9月千葉県勝浦市のお祭り
漁師町らしい威勢の良い掛け声が響く、力強く、活気あふれる千葉の海のおまつり。
| 勝浦市秋季合同祭(勝浦大漁まつり) | |
  | |
| 【場所】 千葉県勝浦市中心部 | |
| 【時期】 9月敬老の日(9月第3月曜日)を最終日とする4日間 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 江戸時代後期に起源を持ち、千葉県の「ちば文化資産」にも選定されている。 この祭りの見どころは、各地区の神輿や江戸後期築造の屋台、山車の巡行です。特に2日目には墨名(とな)市営駐車場で「合同祭典」が行われ、各地区から集結した19基もの神輿が勇壮な「一斉担ぎ」を披露する。漁師町らしく威勢の良い、掛け声や「唄」、神輿を担いだまま跳ねる「揉み」が特徴。 最終日には勝浦漁港で神輿が船から船へと渡される「神輿の船渡し」が行われ、祭りのフィナーレを飾る。地元住民と観光客が一体となって盛り上がる、伝統と活気に満ちた祭り。 |
大原はだか祭り 9月千葉県大原市のお祭り
「汐ふみ」の勇壮豪快、太平洋の大海原に神輿が入る。海の男たちの五穀豊穣・大漁祈願。
| 大原はだか祭り | |
  | |
| 【場所】 千葉県いすみ市中心部 | |
| 【時期】 9月20日・21日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 五穀豊穣と大漁を祈願する勇壮な祭り。大原地区の神輿十社は親神(おやがみ)である鹿島神社に参集し、法楽を施行し、午後大原漁港に向う。 東海・浪花両地区の神輿もそれぞれ地区の行事後大原漁港へ集結。十八社がそろって五穀豊穣・大漁祈願ののち怒濤の中で神輿が数社もみあう「汐ふみ」の行事にうつる。 夕闇のせまる頃、花火を合図に大原小学校校庭に集まり、神輿を高く上げて別れを惜しむ「大別れ式」が行われる。 地域の人々にとって、一年で最も重要な行事の一つであり、その歴史と伝統が今に受け継がれている。 |
阿伎留神社例大祭 9月東京都あきる野市のお祭り
百貫を超える六角神輿が檜原街道沿いを練り歩く。あきる野市に秋を告げる3日間。
| 阿伎留神社例大祭 | |
  | |
| 【場所】 阿伎留神社 〒190-0164 東京都あきる野市五日市1081 檜原街道沿い | |
| 【時期】 9月28-30日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 あきる野三大まつりの一つで全国でも珍しい百貫(約375kg)を超える六角神輿が五日市の町を練り歩くのが見どころ。 神輿の渡御のほか、露払いとして獅子舞が舞いを奉納する風習があり、近隣の囃子連による奉祝囃子や山車の巡行も行われ、祭りを盛り上げる。特に最終日の宮入は、多くの観客で賑わい、迫力満点。地域の人々が一体となり、活気あふれる秋の伝統行事として親しまれている。 阿伎留神社例大祭チラシ1 阿伎留神社例大祭チラシ2 |
以上神輿のお祭りでした。日本にはまだまだ面白いお祭りがいっぱい。種類の違うお祭りもご紹介していますのでぜひご覧ください。
「種類」からお祭りを探すはこちら