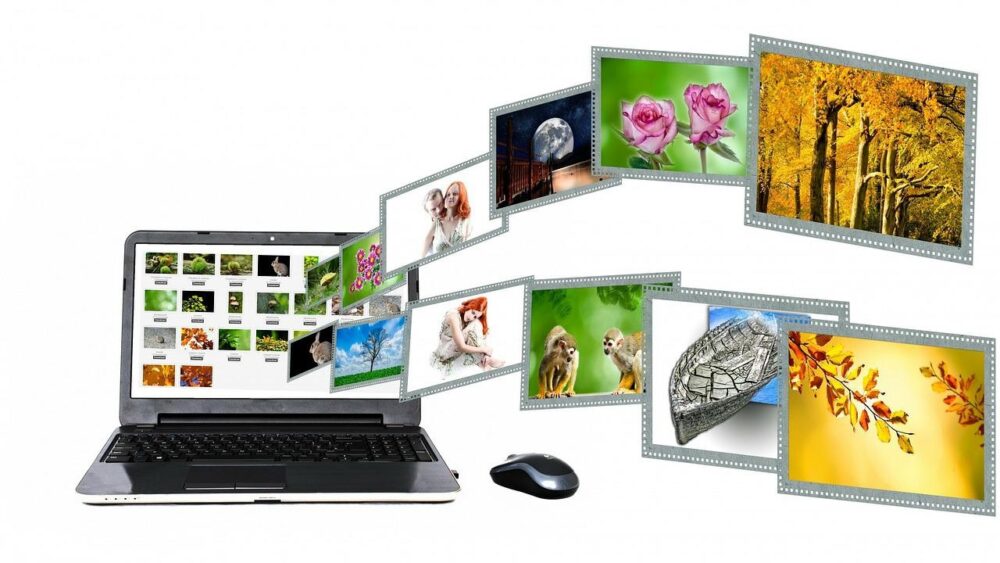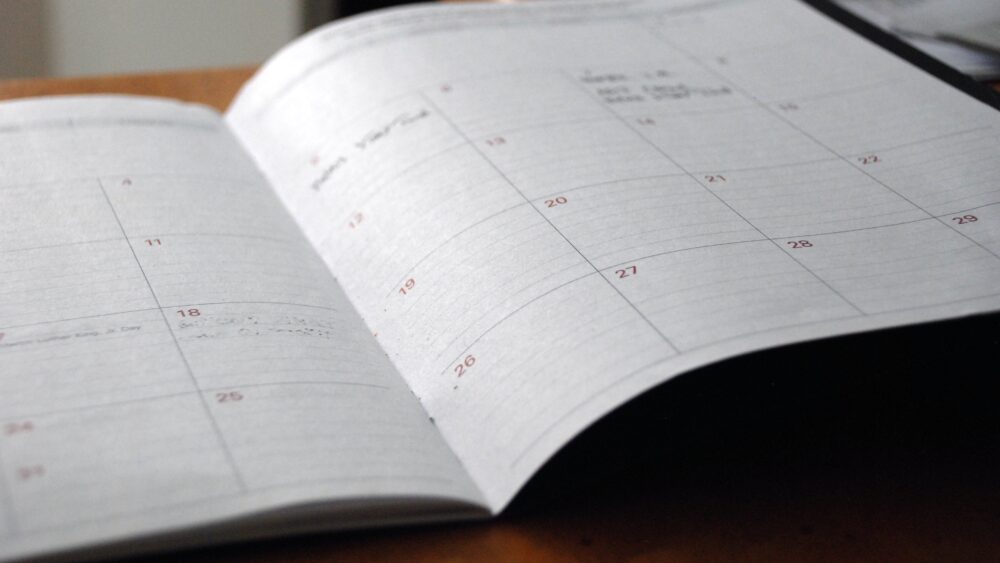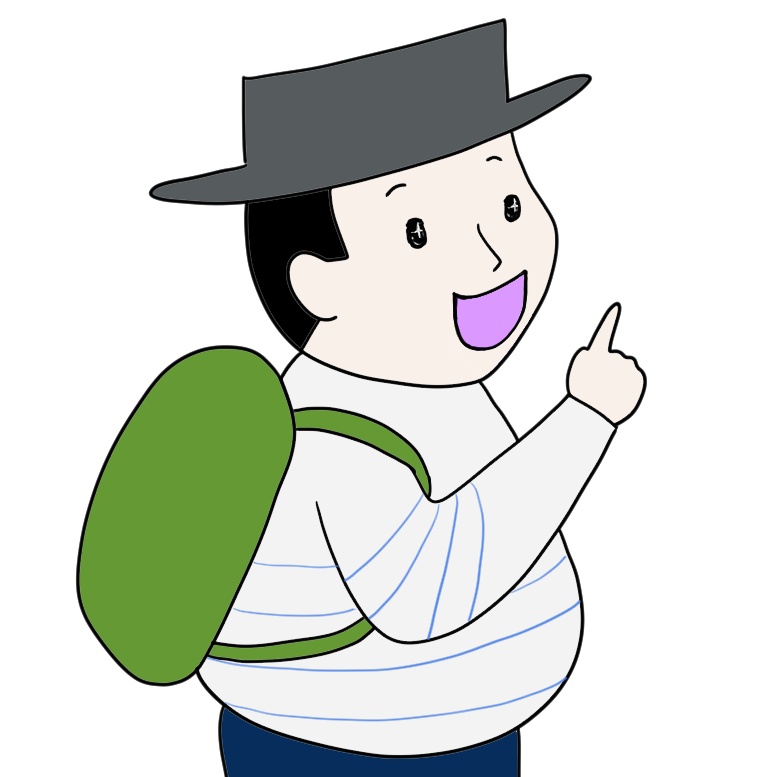6月のお祭りをまとめました。
詳細記事はリンクをクリックしてご覧ください。
目次
善光寺御開帳 長野県長野市のお祭り
七年に一度の最大の盛儀。絶対秘仏の「前立本尊」を本堂にお迎えする行事。
| 善光寺御開帳 | |
 | 【場所】 善光寺 〒380-0851 長野県長野市長野元善町491 |
| 【時期】4月上旬-5月下旬 ※数えで7年に1度 ※2022年(令和4年)は4月3日(日)-6月29日(水) | |
| 【種類】御開帳 | |
| 【概要】 絶対秘仏である御本尊の御身代わり「前立本尊」を善光寺の本堂にお迎えする行事。「前立本尊」は普段は御宝庫に安置されていますが、七年に一度の御開帳の時だけ、特別にお姿を拝むことができる。 前立本尊中央の阿弥陀如来の右手に結ばれた金糸は五色の糸に変わり、白い「善の綱」として、本堂前の高さ約10メートルの回向柱に結ばれる。その回向柱に触れることによって、前立本尊に触れるのと同じこととなる。 御開帳期間中は、多くの参拝者が全国から訪れ、賑わいを見せる。 | |
素盞雄神社天王祭&葛飾菖蒲まつり 中旬東京都荒川区と葛飾区のお祭り
神輿を激しく振り、夏の疫病をはらい落とす。宿場町千住の初夏のお祭り。
江戸時代から続く花菖蒲の名所。200種類の花菖蒲が咲き誇る。
| 素盞雄神社天王祭 | |
 | 【場所】 素盞雄神社 〒116-0003 東京都荒川区南千住6丁目60−1 |
| 【時期】5月下旬-6月上旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 人や物の行き来が盛んな街道の夏に流行する疫病を、激しい神輿振りによって、御祭神の神威をより一層振り起こして祓う悪疫退散・除災招福・郷土繁栄を願う伝統的なお祭り。 最大の見どころは、特徴的な「二天棒神輿振り」。通常の神輿が4本や6本の担ぎ棒を使うのに対し、素盞雄神社の神輿はわずか2本の担ぎ棒で担がれ、屋根の鳳凰が地面につくほど左右に激しく振られる。この勇壮な神輿振りは都内でも珍しく、多くの見物客を魅了する。 3年に一度の「本まつり」では、千貫神輿と呼ばれる御本社大神輿が氏子61ヶ町を渡御し、それ以外の年は「氏子まつり」として100基を超える町神輿が巡行する。荒川区の無形民俗文化財にも登録されており、地域に深く根付いた夏の風物詩として親しまれている。 令和5年 素盞雄神社天王祭 巡行図 | |
| 葛飾菖蒲まつり | |
 | 【場所】 堀切菖蒲園 〒124-0006 東京都葛飾区堀切2丁目19−1 |
| 【時期】5月下旬-6月上旬 | |
| 【種類】花見 | |
| 【概要】 メイン会場は江戸時代から花菖蒲の名所として知られる「堀切菖蒲園」と、約100種14,000株が咲き誇る広大な「都立水元公園」の2ヶ所。堀切菖蒲園では、歌川広重の浮世絵にも描かれた歴史ある花菖蒲が楽しめ、夜間にはライトアップも行われる。一方、都立水元公園では、都内唯一の水郷景観の中で、のびのびと咲く花菖蒲の壮大な景色が広がる。 期間中は、両会場で様々なイベントが催され、週末にはパレードや舞台イベント、屋台なども登場し、多くの見物客で賑わう。両会場間や周辺の観光スポットを結ぶ「かつしか菖蒲めぐりバス」も運行され、花菖蒲とともに葛飾の魅力を満喫できるイベント。 葛飾菖蒲まつり リーフレット 2023 | |
高瀬裏川花しょうぶまつり 熊本県玉名市のお祭り
江戸時代に水運で栄えた町並みを背景に紫や白の花しょうぶが咲き誇る。熊本県玉名に初夏の訪れを告げる風物詩。
| 高瀬裏川花しょうぶまつり | |
 | 【場所】 高瀬裏川水際緑地 〒865-0026 熊本県玉名市秋丸 |
| 【時期】5月下旬-6月上旬 | |
| 【種類】花見 | |
| 【概要】 江戸時代に水運で栄えた高瀬の歴史ある町並みを背景に、約700メートルにわたって紫や白の花しょうぶが美しく咲き誇る玉名市の初夏の風物詩。 期間中は、夜間のライトアップが行われ幻想的な雰囲気が楽しめる。メインイベント日には、花しょうぶコンサートやゆるキャラステージ、野点、高瀬市など様々な催しが開催され、多くの人で賑わう。 菊池川の堤防には全国から寄贈された矢旗が立ち並び、祭りのシンボルとなっている。 | |
六郷神社祭礼 東京都大田区のお祭り
平安時代から続く神社で行われる祭礼。鳩をいただく神輿が氏子町内を練り歩く。
| 六郷神社祭礼 | |
 | |
| 【場所】 六郷神社とその周辺 〒144-0046 東京都大田区東六郷3丁目10−18 | |
| 【時期】 6月3日、6月第1土曜日、日曜日 | |
| 【種類】 神輿 | |
| 【概要】 5年に一度の本祭の年には「一之宮神輿」が、その他の年には「二之宮神輿」が氏子地域を巡行する「神幸祭」が最大の見どころ。また、数百年の伝統を持つ「神獅子」と呼ばれる子供獅子舞が奉納され、各御神酒所で披露される。 期間中は、六郷の14町から約40基もの町神輿がそれぞれの地域を渡御し、金曜日には神社で「御霊入れ」、日曜日には「御霊返し」が行われる。かつては「曳船祭」として、関東三大船祭りの一つにも数えられていた伝統ある祭り。境内には多数の露店も出店し、多くの人で賑わう。 【2024年】 ●6月3日(月) 11:00例大祭式典(式典執行) ●8日(土) 神楽奉奏13:30・14:00・16:00 子供神獅子舞奉納 13:30(道行き)・14:00(神楽殿)・16:00(神楽殿) ●9日(日) 子供神獅子舞奉納 8:30(道行き)・13:00(神楽殿)・14:30(神楽殿)・16:00(神楽殿) 御神輿渡御 宮出し 8:30・宮入り 16:45 |
須賀神社例大祭 東京都新宿区のお祭り
坂の多い街の中、本社の神輿が威勢よく練り歩く。四谷の夏を告げる例大祭。
| 須賀神社例大祭 | |
  | 【場所】 〒160-0018 東京都新宿区須賀町5 |
| 【時期】6月上旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 隔年で「本祭」と「陰祭」があり、本祭の年には本社神輿が四谷の街を威勢よく練り歩く「神輿渡御」が行われる。陰祭の年には、氏子18ケ町の町会神輿による連合渡御が行われる。 祭りの期間中は、境内に露店が立ち並び、神楽殿では神楽が奉納されるなど、賑やかな雰囲気に包まれる。特に本社神輿の宮出しや渡御は圧巻で、多くの見物客で賑わう。 江戸時代から続く歴史を持ち、かつては「四谷の天王祭り」として江戸の五大祭りにも数えられた伝統あるお祭り。 【2023年】 ●6月2日(金) 宵宮 (前夜祭) ●6月3日(土) 例大祭々典 午後5時より和太鼓集団 荒魂 奉納太鼓 午後6時より東龍倶楽部 龍踊り奉納 ●6月4日(日) 本社神輿渡御 宮出し11:30 宮入り17:00 ●6月5日(月) 修祭 | |
品川神社 例大祭&荏原神社 天王祭 東京都品川区のお祭り
北の天王祭と南の天王祭が同時に開催する品川っ子の特別な期間。太鼓付きの神輿が品川を練り歩く。
| 品川神社例大祭 | |
  | 【場所】 品川神社 〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目7−15 |
| 【時期】6月上旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 「北の天王祭」として知られ、疫病除けの神である牛頭天王を祀る。 見どころは、徳川家康ゆかりの「天下一嘗の御神面」を屋根に付けた宮神輿の渡御。締め太鼓と篠笛で奏でる「品川拍子」に合わせて、担ぎ手が神輿の横棒に肩を入れ、前後左右に不規則に動かす「城南担ぎ」と呼ばれる独特の担ぎ方が特徴。特に、53段ある急な石段を宮神輿が上り下りする「宮入り・宮出し」は迫力満点。期間中は旧東海道沿いに多くの屋台が並び、街全体が祭り一色に染まる。 | |
| 荏原神社 天王祭 | |
  | 【場所】 荏原神社 〒140-0001 東京都品川区北品川2丁目30−28 |
| 【時期】6月上旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 品川の夏の風物詩として知られる例大祭。宝治元年(1247年)に京都八坂神社から牛頭天王(ごずてんのう)が勧請されたことに始まり、約780年の歴史を持つ伝統的なお祭り。 俗称「かっぱ祭り」とも呼ばれ、かつては神輿が東京湾の海中を練り歩く「海中渡御」が行われていた。これは、海から見つかったとされる牛頭天王(須佐之男尊)の御神面を神輿に付け、豊漁・豊作を祈願する神事だったため。埋め立てが進んだ現在では、海中渡御は一部異なる形で行われることもあるが、氏子各町の神輿が品川の町を勇壮に渡御し、大勢の観客で賑わう。 品川神社(北の天王祭)と対をなす「南の天王祭」としても親しまれる。 【2023年】 ●6月2日(金)14:00 大祭式 ●6月3日(土) 9:00 町内神輿宮入り ●6月4日(日)16:00 町内神輿櫻河岸渡御 | |
蛇も蚊も祭り 神奈川県横浜市のお祭り
全長20mの大蛇が街を練り歩く。無病息災・子供の成長を願う市の無形民俗文化財。
| 蛇も蚊も祭り | |
  | 【場所】 神明社・道念稲荷神社 〒230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目13−37 |
| 【時期】6月上旬 | |
| 【種類】龍・蛇 | |
| 【概要】 江戸時代から続く無病息災や子供達の成長を願う伝統行事で本宮地区と原地区で行われる。 祭りの主役は、かやで作った全長20mの大蛇巨大な蛇。この蛇は「蛇も蚊も出たけい、日和の雨けい(じゃもかもでたけい、ひよりのあめけい)」という掛け声とともに地域を練り歩き、道中の家々から餅やお菓子などの供物が投げ入れられる。 蛇は最終的に神明社に奉納され、その藁を持ち帰ると一年を無事に過ごせると信じられている。 「蛇も蚊も」という掛け声は、蛇だけでなく蚊も退散させるという意味が込められており、夏の疫病を追い払う願いが込められている。地域住民が一体となって作り上げる、活気あふれるお祭り。 | |
高幡不動尊あじさいまつり 東京都日野市のお祭り
八十八のお地蔵さんを巡るあじさいのお祭り。200種類以上・7800株余りのあじさいを巡るハイキング。
| 高幡不動尊あじさいまつり | |
  | 【場所】 高幡不動尊 〒191-0031 東京都日野市高幡733 |
| 【時期】6月上旬-7月上旬 | |
| 【種類】花見 | |
| 【概要】 境内や山内には、全国から集められた約250種7,800株もの色とりどりのあじさいが咲き誇り、訪れる人々を魅了する。 見どころは、境内のあじさいはもちろん、山内八十八ヶ所巡拝路沿いに咲く山あじさいや、珍しい品種のあじさいなど多岐にわたる。 最近は散策路が整備され、山あじさい園も拡張された。期間中は、あじさい市や植木市、写真コンクール、俳句短歌大会、山内八十八ヶ所クイズめぐりなどのイベントも開催され、賑わいを見せる。 2024年 高幡不動尊あじさいまつり | |
鳥越祭り 東京都台東区のお祭り
猿田彦、手古舞連に続くのは、千貫御輿といわれるほどの東京一の重さを誇る神輿。百数十個の高張提灯も美しい下町のお祭り。
| 鳥越祭り | |
  | 【場所】 鳥越神社 〒111-0054 東京都台東区鳥越2丁目4−1 |
| 【時期】6月9日に近い金・土・日曜日 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 千貫神輿(せんがんみこし)と呼ばれる都内最大級の神輿が特徴で、その重厚さと迫力から「関東三大祭」の一つに数えられることもある。 祭りの見どころは、氏子衆が担ぐ千貫神輿が深夜まで町内を巡行する「神輿渡御」。神輿を氏子各町が引き継ぎながら担ぎ、御神輿の列の先頭には、猿田彦(天狗)や、手古舞連、子供たちの持つ五色の旗が歩く。 夕刻、神輿の弓張提灯と町会の高張提灯に火が入ると、祭りは最高潮を迎える。宮入道中は、「鳥越の夜祭り」と言われ、荘厳かつ幻想的。沿道には多くの見物客が詰めかける。 また、祭りの前日には「奉納相撲」や「子供神輿」、露店なども並び、地域全体が活気に満ち溢れる。夏の訪れを告げる下町の風物詩として、地元の人々に深く愛されている。 【2024年】 ●6月8日(土)10:00 大祭式 ●6月8日(土)町内神輿の渡御 連合参拝宮入り ●6月9日(日)千貫神輿の渡御 宮出し6:30 鳥越の夜祭り19:00時頃 宮入り21:00 | |
つきじ獅子祭り 東京都中央区のお祭り
威勢の良い築地人が巨大な獅子を担いで街を練り歩く。夏の訪れを告げる築地の風物詩。
| つきじ獅子祭り | |
  | 【場所】 波除神社 〒104-0045 東京都中央区築地6丁目20−37 |
| 【時期】6月10日前後数日 | |
| 【種類】獅子 | |
| 【概要】 三年に一度の「本祭り」は、獅子頭神輿の雄雌どちらかの獅子と神社千貫宮神輿の2基が渡御され、「陰祭り」は、本社大神輿と獅子頭神輿のうち1基が渡御される。 この祭りは、江戸時代に築地が埋め立てられた際、荒波を鎮めるためにご神体を祀ったことに由来するとされ、商売繁盛や厄除けの願いが込められている。期間中は縁日も立ち並び、多くの人で賑わう。 【2024年】 ●6月7日(金)鎮花祭(疫病除け・百合の花神事)、宵宮祭 ●6月8日(土)江戸里神楽奉納(石森社中) ●6月9日(日)渡御祭・千貫宮神輿ご巡行 9:00宮出し(築地全町ご巡行) 15:30宮入り・帰社祭 ●6月10日(月)大祭式 R6つきじ獅子祭 順路図 | |
犬子ひょうたん祭 熊本県山鹿市のお祭り
夏の始まりに疫病を鎮めた子犬の守りを授与する。浴衣を着始める山鹿の風物詩。
| 犬子ひょうたん祭 | |
  | 【場所】 八坂神社 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿196 |
| 【時期】6月15日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 江戸時代に疫病が流行した際、子犬が神様の使いとして疫病を鎮めたという伝説に由来する。この祭では、米粉で作られたひょうたんを抱えた子犬の形をしたお守り「犬子ひょうたん」が授与され、無病息災を願う人々で賑わう。 また、山鹿ではこの日を「初かたびら」と呼び、浴衣を着始める風習がある。山鹿の夏の訪れを告げる風物詩として親しまれている。 犬子ひょうたんのご案内 | |
文京あじさいまつり 東京都文京区のお祭り
3,000株の多様なあじさいが会場一帯に花開く。梅雨の時期に楽しむ文京花の五大まつり。
| 文京あじさいまつり | |
  | 【場所】 白山神社 〒112-0001 東京都文京区白山5丁目31−26 |
| 【時期】6月中旬 | |
| 【種類】花見 | |
| 【概要】 約3,000株もの色とりどりのあじさいが境内や周辺を彩り、多くの観光客や地元の人々で賑わう。 期間中は、普段は公開されていない白山神社の富士塚が午前10時から午後4時まで特別に開放され、あじさいに覆われたミニチュアの富士山を登ることができる。また、露店が出店したり、コンサートなどのイベントが開催されたりすることもある。 あじさいの見頃に合わせて開催されるこのお祭りは、梅雨の時期ならではの美しい風景を楽しむことができる人気のイベント。特に、白山神社から白山公園にかけての「あじさいの小道」は、両側に咲き誇るあじさいが見事。 | |
日枝神社大祭 山王祭 東京都千代田区のお祭り
歴代の将軍が上覧拝礼する「天下祭」。神幸祭、連合宮入、下町連合 渡御と「天下祭」と呼ばれるのにふさわしいお江戸の大祭り。
| 日枝神社大祭 山王祭 | |
  | 【場所】 日枝神社 〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目10−5 |
| 【時期】6月中旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 徳川将軍家の産土神(うぶすながみ)として信仰されてきた日枝(ひえ)神社の祭礼で、日本三大祭・江戸三大祭の一つに数えられる壮大な祭り。特に偶数年には「本祭」として、約300メートルにも及ぶ「神幸祭」の行列が東京都心を練り歩く。 この行列では、御鳳輦(ごほうれん)や宮神輿、山車が、王朝装束をまとった約500名の奉仕者と共に巡行し、まるで江戸時代の絵巻物が現代に蘇ったかのような荘厳な光景が広がる。徳川将軍家から「天下祭」として崇敬され、江戸城内への神輿渡御も許されるなど、幕府の手厚い庇護のもと発展してきた。 神輿が国道の起点である「日本国道路元標」に差しかかると、担ぎ手たちが一斉に神輿を高々と上げる。また、日本橋髙島屋の正面入口で行われる”差し”がみどころ。木頭(きがしら)の合図で、いくつかの神輿が威勢よく差し上げられる。 稚児行列や和菓子を奉納する「山王嘉祥祭」、そして納涼大会盆踊りなど、期間中には様々な行事が行われ、多くの人々で賑わう。 【2024年】 ●6月7日(金)6:00末社八坂神社例祭 7:45-17:45頃神幸祭 13:45日本橋御旅所祭 ●6月8日(土)16:00-17:00頃連合宮入 ●6月9日(日)9:00-14:00下町連合渡御 ●6月13日(木)-15日(土)18:30盆踊り ●6月15日(土)例祭 -皇城鎮護・都民平安祈願- ●6月16日(日)11:00煎茶礼道日 13:00山王嘉祥祭 ●6月7日(金)-16日(日)嘉祥菓子接待席(無料) 2024山王祭楽しみ方ガイド | |
駒込富士神社 山開き大祭 東京都文京区のお祭り
富士山の山開きにあわせて行われる駒込富士神社の大祭。神竜(麦わら蛇)を疫病除けの縁起物として授与する。
| 駒込富士神社 山開き大祭 | |
  | 【場所】 駒込富士神社 〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目7−20 |
| 【時期】6月30日-7月2日 | |
| 【種類】花見 | |
| 【概要】 富士山の登山口が開かれることを祝うお祭り。初日の30日は「万灯まつり」として、朝から「万灯回り」が行われる(万灯を掲げた富士講の講員が地域を練り歩く)。2日目は例大祭の式典。 3日目の最終日は「納め」となる。 駒込富士神社は、文京区本駒込にある富士塚の上に建てられた神社で、江戸時代から庶民の富士信仰の中心地として栄えた。山開き大祭では、神事のほか、地元の人々によるお囃子や太鼓の演奏、露店などが立ち並び、多くの参拝者で賑わう。 富士山に見立てた富士塚の山頂には奥宮があり、参拝者は山頂まで登って安全な登山を祈願する。 期間中は縁起物である麦藁蛇(むぎわらへび)や限定で販売される麦らくがんを購入することができる。 ※麦らくがんは富士山の形をした美味しいお菓子。 ※麦藁蛇は「神竜」と呼ばれ、江戸時代中期の宝永年間の頃、江戸で疫病が蔓延した際に麦わら蛇を持っていた家には疫病を患う人がいなかったことから、疫病除けの縁起物として授与されてきた。蛇が枝に巻き付き舌を出している形をしている。台所の水回り付近に掛けてお祀りをする。 | |
篠崎浅間神社 幟祭り 東京都江戸川区のお祭り
2年に一度に行われる浅間神社の山開き。高さ25メートルの幟(のぼり)10本が境内に立ち並ぶ。
| 篠崎浅間神社 幟祭り | |
  | 【場所】 篠崎浅間神社 〒133-0054 東京都江戸川区上篠崎1丁目22−31 |
| 【時期】6月下旬-7月上旬 | |
| 【種類】人形・装飾 | |
| 【概要】 富士山を信仰対象とする神社としての山開き祭で江戸川区指定無形民俗文化財。江戸時代中期にはすでに行なわれていたとされ、期間中は雨のことが多いため「どろんこ祭り」とも呼ばれる。2年に一度、五穀豊穣を祈り、日本最大級重さ1トン高さ25メートルにもなる幟(のぼり)10本が神社境内に立てられる。 この祭りの最大の見どころは、この大幟(おおのぼり)10本を、約200人の「幟会(のぼりかい)」のメンバーらが人力で立てる「幟上げ」。「もんで、もんで」という掛け声と共に、大きな綱と滑車を使って巨大な杉丸太と幟旗をゆっくりと立ち上げていく様子は壮観で、多くの見物客で賑わう。 6月30日は夏越の祓、7月1日は大祭が行われ、境内には所狭しと露店が並ぶ他、稚児行列などの行事も行われる。幟が立たない年は、境内に茅の輪が設置される。 【2023年】 ●6月24日(土) 枠いけ(準備) ●6月25日(日) 6:00 幟上げ ●6月30日(金) 20:00 夏越大祓(一般者の参列不可) 18:30 素人演芸大会 ●7月1日(土) 11:00 浅間幼稚園園児による稚児行列 14:00 大祭式(一般車の参列不可) 18:30 素人演芸大会 ●7月2日 幟返し ※6月30日と7月1日のみ、屋台の出店 | |
繁根木八幡宮 多祓茅輪神事 熊本県玉名市のお祭り
半年ごとに茅の輪をくぐって犯した罪を祓い清める。玉名住民が支えるお祓い神事。
| 繁根木八幡宮 多祓茅輪神事 | |
  | 【場所】 繁根木八幡宮 〒865-0051 熊本県玉名市繁根木188 |
| 【時期】6月30日、12月31日 | |
| 【種類】祓い | |
| 【概要】 「大祓(おおはらえ)」の一環であり、知らず知らずのうちに犯した罪や穢れを半年ごとに祓い清め、心身を清らかな状態にすることを願って執り行われる。 特に6月に行われるものは「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」と呼ばれ、大きな茅の輪をくぐることで、この半年間の厄災を祓い、残りの半年の無病息災を祈願する。参列者は茅の輪を「左・右・左」と8の字を描くように3回くぐるのが一般的な作法とされている。 | |
以上、「6月のお祭り」でした。他の月のお祭りもまとめています。どうぞ以下からご覧ください。
1月のお祭り 2月のお祭り 3月のお祭り 4月のお祭り 5月のお祭り 6月のお祭り 7月のお祭り 8月のお祭り 9月のお祭り 10月のお祭り 11月のお祭り 12月のお祭り