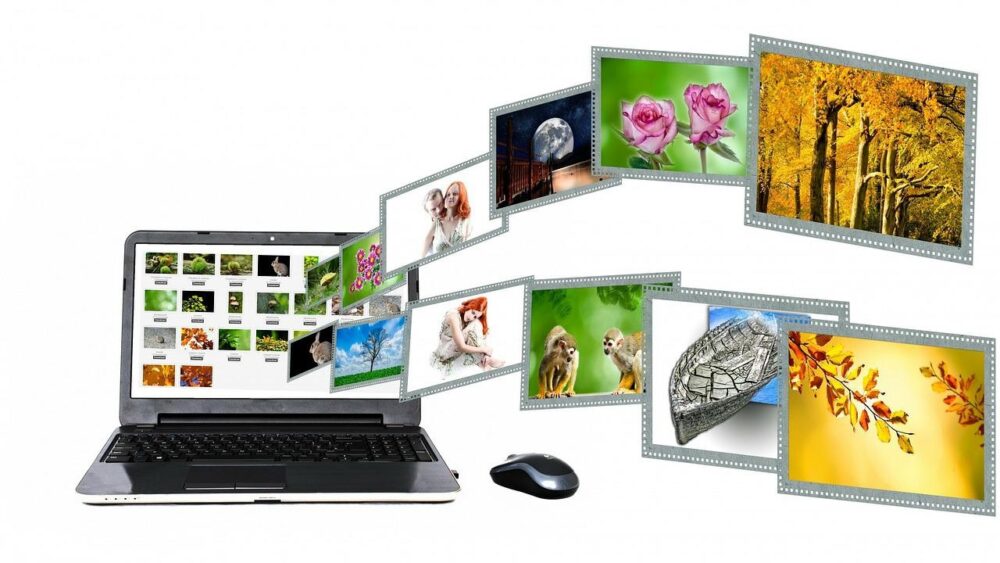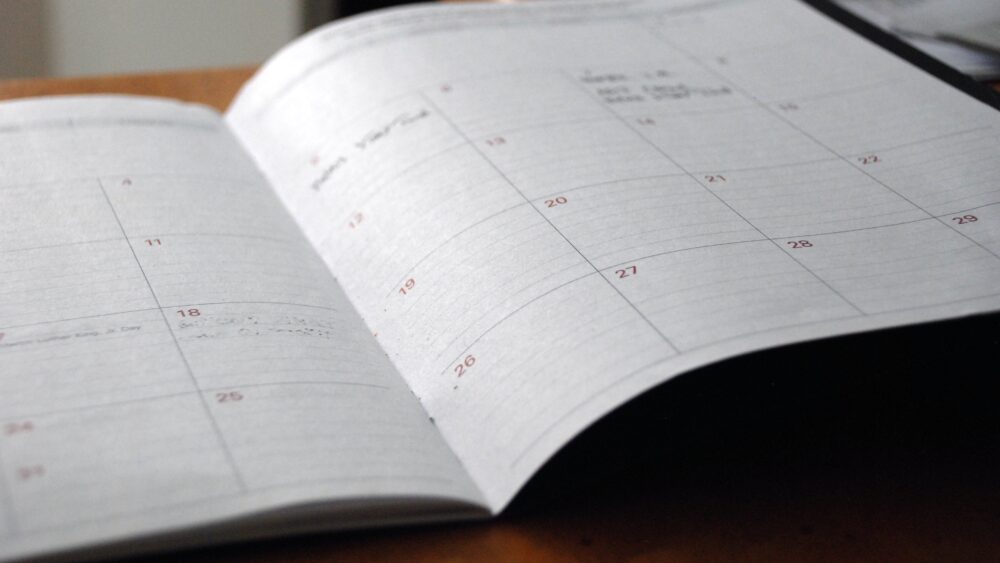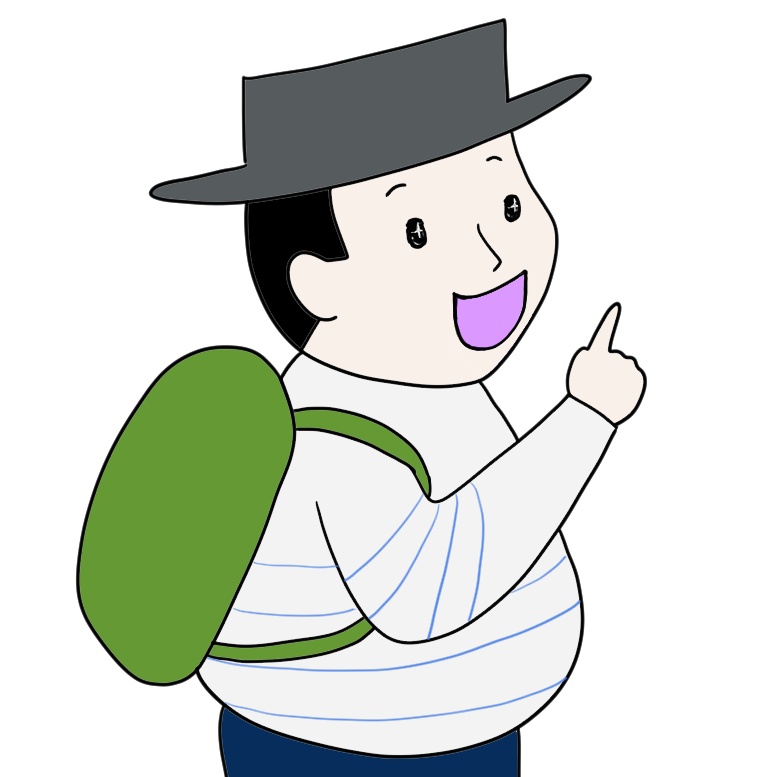11月のお祭りをまとめました。
詳細記事はリンクをクリックしてご覧ください。
目次
天草伊勢えび祭り 熊本県天草市のお祭り
天然新鮮!ぷりっぷりの伊勢えびを頂ける天草市の食のお祭り 。漁の解禁時期に合わせて設定される宿泊プランを利用して大満足の旅。
| 天草伊勢えび祭り | |
 | |
| 【場所】 熊本県天草市内 | |
| 【時期】 8月中旬-12月 | |
| 【種類】 食 | |
| 【概要】 天草の5つのエリアで、天然新鮮なぷりっぷり伊勢えびが楽しめる祭り。 祭りの期間中、天草市内の旅館や飲食店では、刺身、鬼瓦焼き、具足煮、味噌汁など、伊勢えびの旨みを最大限に引き出した様々な料理が提供される。新鮮でぷりぷりの伊勢えびは、その濃厚な甘みと弾力のある食感が特徴で、まさに海の恵みを堪能できる。 また、伊勢えび料理だけでなく、天草の特産品が並ぶ物産展や、郷土芸能の披露など、様々な催しが行われ、訪れる人々を楽しませる。美しい天草の自然と美味しい海の幸を同時に楽しめるため、多くの観光客で賑わう。 地元の人々にとっても、秋の訪れを告げる風物詩として親しまれており、天草の魅力を国内外に発信する重要なイベントとなっている。 |
神田古本祭り 東京都千代田区のお祭り
世界最大の古書の街で行われる本のお祭り。神田神保町が古本と人で埋め尽くされる。
| 神田古本まつり | |
 | 【場所】 神田神保町古書店街(靖国通り沿い・神田神保町交差点他) |
| 【時期】10月下旬-11月上旬 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 130軒の古本屋が軒を連ねる世界最大の神保町古書店街、神田神保町。ここで100万冊もの古書が販売される青空掘り出し市。日本全国さらには海外からも多くの読書人が訪れ、街全体が本と人で埋め尽くされる。 神保町交差点を中心とした靖国通りに沿って「本の回廊」が出現し、数十万冊にも及ぶ様々なジャンルの古書が販売される。専門書から文学、美術書、絵本まで、普段お目にかかれないような希少本に出会える。 期間中は古書販売だけでなく、チャリティ・オークション、トークイベント、神保町を巡るスタンプラリーなど、本にまつわる多彩な催しが行われる。読書家はもちろん、古本初心者や家族連れも楽しめるイベントとして、多くの人で賑わう。本の魅力と古書店街の文化に触れる貴重な機会となっている。 神田古本まつりeventmap1 神田古本まつりeventmap2 | |
唐津くんち 佐賀県唐津市のお祭り
絢爛豪華な漆塗りの曳山14台が唐津市内を練り歩く。「エンヤ!」「ヨイサ!」の掛け声で曳山が進む国の重要無形民俗文化財。
| 唐津くんち | |
 | 【場所】 唐津神社 〒847-0013 佐賀県唐津市南城内3−13 |
| 【時期】11月2・3・4日 | |
| 【種類】山車・だんじり | |
| 【概要】 国指定重要無形民俗文化財、そしてユネスコ無形文化遺産にも登録されている、日本を代表するお祭り。 最大の特徴は、和紙を幾重にも貼り重ねて漆や金箔で仕上げられた、豪華絢爛な14台の「曳山」が街中を練り歩くこと。獅子や兜、鯛など、さまざまな形をした巨大な曳山が、笛や太鼓、鐘の「曳山囃子」と、曳き子たちの「エンヤ、エンヤ」「ヨイサ、ヨイサ」という威勢の良い掛け声に合わせて巡行する。 2日の宵曳山、3日の御旅所神幸、4日の翌日祭と3日間にわたって繰り広げられ、特に2日目の西の浜での「曳き込み」は、重さ2トン以上ある曳山が砂地にめり込みながらも懸命に曳き込まれる圧巻の光景で、多くの観客を魅了する。 祭り期間中の人出は延べ50万人を超える。祭り期間に客人をもてなすくんち料理は絢爛豪華なもてなし料理として有名。 | |
浅草酉の市 東京都台東区のお祭り
運を「かっ込む!」、福を「はき込む!」。年々大きな熊手に換えてゆく江戸っ子恒例の市。
| 浅草酉の市 | |
 | 【場所】 酉の寺 長國寺 〒111-0031 東京都台東区千束3-19-6 |
| 【時期】11月酉の日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 正月を迎える最初の祭りとされていた。始まりは、江戸近郊に位置する花又村(現在の足立区花畑にある大鷲神社)であるといわれ、祭りの形態も、当初は近在の農民が鎮守である「鷲大明神」に感謝した収穫祭であったと伝えられている。 市での代表的な名物は、縁起熊手。金銀財宝を詰め込んだ熊手で、運を「かっ込む」、福を「はき込む」といって開運招福・商売繁盛を願った、江戸っ子らしい洒落の利いた縁起物で翌年の更なる招福を願って、熊手守りは年々大きな熊手に換えてゆくのが良いとされている。 会場では大小様々な熊手が露店に並び、熊手を買うと手締め(家内安全や商売繁盛を願って手をたたくこと)が行われるのが風物詩となっている。 夜遅くまで活気に満ち溢れ、多くの参拝者や観光客で賑わう、東京の晩秋を彩る代表的な行事の一つ。 | |
深川酉の市(大鳥神社例祭) 東京都江東区のお祭り
運を「かっ込む!」、福を「はき込む!」。下町情緒を味わいながらゆったりと楽しめる深川の市。
| 深川酉の市 | |
 | 【場所】 大鳥神社(富岡八幡宮境内) 〒135-0047 東京都江東区富岡1丁目20−3 |
| 【時期】11月酉の日 | |
| 【種類】 | |
| 【概要】 家内安全や商売繁盛を願う下町の風物詩として親しまれている。 特徴は、福を「かきこむ」「取り込む」とされる縁起物「熊手」。大小さまざまな熊手が露店に並び、参拝者は威勢の良い手締めと共に、お守りの「かきこめ守り」や、枡や小判、おかめなどをあしらった縁起熊手を購入する。熊手守りは年々大きな熊手に換えてゆくのが良いとされている。 | |
松嶋神社 酉の市 東京都中央区のお祭り
運を「かっ込む!」、福を「はき込む!」。人形町でひっそりと行われる酉の市。
| 松嶋神社 酉の市 | |
 | 【場所】 松嶋神社 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目15−2 |
| 【時期】11月酉の日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 ご祭神に天日鷲神(あまのひわしのみこと)が祀られていることから、酉の市が開催され、「人形町のおとりさま」として地元の人々に親しまれている。 この酉の市は、かつて人形町が歓楽街として栄えていた江戸時代から続く歴史ある行事で、当時は大変な賑わいを見せたといわれている。現在でも、商売繁盛や開運招福を願う人々で賑わい、縁起物の熊手を買い求める光景が見られる。 日本橋地域で酉の市が行われるのは松嶋神社が唯一であり、長國寺や花園神社のような大規模な酉の市とは異なり、こぢんまりとした温かい雰囲気が特徴。 人形町がかつて芸者や役者が行き交う粋な街だった事にちなんでおかめがついている「かんざし熊手」がある。 | |
築地 酉の市 東京都中央区のお祭り
築地市場近くで行われる酉の市。開運熊手神符「かっこめ」で開運、商売繁盛を願う。
| 築地 酉の市 | |
 | 【場所】 波除稲荷神社 〒104-0045 東京都中央区築地6丁目20−37 |
| 【時期】11月酉の日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 江戸時代から続く行事で、開運招福や商売繁盛を願うものとして知られている。境内には、福をかき集める縁起物とされる熊手を売る露店が立ち並び、多くの参拝客で賑わう。 波除神社では、酉の市限定の特別な御朱印や、開運熊手神符「かっこめ」が授与され、これを受けた人は開運くじを引くこともできる(熊手は「かっこめ」「はっこめ」の囃子声のように、福運や財宝を掻きこむ、掃きこむという縁起から商売繁盛のお守りとなったと言われている)。 築地市場に隣接していることから、魚に因んだ塚が並ぶ珍しい光景も見られる。年末の風物詩として親しまれている。 | |
新宿花園神社 酉の市 東京都新宿区のお祭り
日本を代表する歓楽街で行われる秋の風物詩。新宿の商売繁盛を祈願する。
| 新宿花園神社 酉の市 | |
 | 【場所】 花園神社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目17−3 |
| 【時期】11月酉の日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 日本を代表する歓楽街がある新宿の花園神社で行われる酉の市。威勢の良い掛け声とともに、縁起物の熊手が販売される。熊手は「かっこめ」「はっこめ」の囃子声のように、福運や財宝を掻きこむ、掃きこむという縁起から商売繁盛のお守りとなったと言われている。この熊手は、商売繁盛や開運招福を願うもので、大小さまざまな熊手が境内に並ぶ。多くの露店も出店し、多くの人で賑わう。 特に、深夜まで活気が続くのが特徴で、仕事帰りの会社員や観光客など、幅広い人々が訪れる。 | |
箱根の大名行列 神奈川県足柄下郡箱根町のお祭り
「下に下に」と、総勢約170人の大名行列が旧東海道を練り歩く。紅葉の美しい時期に行われる江戸時代の華やかな参勤交代。
| 箱根の大名行列 | |
 | 【場所】 神奈川県足柄下郡箱根町 |
| 【時期】11月3日 | |
| 【種類】行列 | |
| 【概要】 江戸時代の参勤交代を再現した伝統的なお祭り。 行列は、小田原藩11万3千石の格式にならい、総勢約170名が江戸時代の衣装を身につけて練り歩く。奴(やっこ)が毛槍や挟み箱を持って「下に~、下に~」と声を上げ、大名駕籠や腰元衆が続き、当時の華やかな時代絵巻を彷彿とさせる。また、小田原北條鉄砲衆による火縄銃の空包射撃も披露され、その迫力は見どころの一つ。 この祭りは1935年(昭和10年)の温泉博覧会をきっかけに始まり、太平洋戦争による中断を経て、戦後に復活した。現在では箱根の秋の風物詩として、多くの観光客を魅了している。 | |
浅草寺 白鷺の舞 東京都台東区のお祭り
優雅な笛、太鼓に合わせて白鷺達が浅草寺の境内を美しく舞う。浅草寺絵巻から生まれた貴重な舞い。
| 浅草寺 白鷺の舞 | |
 | 【場所】 浅草寺 〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−1 |
| 【時期】4月第2日曜日、5月三社祭、11月3日 | |
| 【種類】舞い | |
| 【概要】 昭和43年(1968)に明治100年記念(東京100年)行事として始められ、『浅草寺縁起』(寛文縁起)に描かれる「白鷺の舞」を再興した寺舞。 鷺舞の神事は京都八坂神社が起源とされ、浅草寺の舞はその鷺舞を参考に、寺舞保存会によって演じられている。 白鷺の装束をまとった踊子が舞い、武人、棒ふり、餌まき、楽人、守護童子などが、「白鷺の唱」を演奏しながら練り歩く。 舞は静かでゆったりとした動きが特徴で、笛や太鼓の音色に合わせて、優美な姿を見せる。 この舞は、浅草寺本堂裏の庭園や境内で行われ、毎年11月3日の文化の日に行われる例大祭「金龍の舞」とともに、浅草寺を代表する伝統行事となっている。 江戸情緒あふれる浅草の街並みに、白く美しい鷺が舞う姿は、訪れる人々を魅了し、浅草の秋の風物詩として親しまれている。 | |
おかがら火 東京都国立市のお祭り
薪で組まれた2つの山に点火し、その炎の高さを競う。悪い病気にかからないと伝えられるおかがら火。
| おかがら火 | |
 | 【場所】 谷保天満宮 〒186-0011 東京都国立市谷保5209 |
| 【時期】11月3日 | |
| 【種類】火 | |
| 【概要】 本社拝殿前に高さ約3メートルにもなる薪の山を2基積み上げ、18時に一斉に点火されrる。 この神事は、養和元年(1181年)に天神島から現在地へ谷保天満宮が遷座した際、旧社殿や残木を焚き上げたことに由来すると伝えられている。燃え盛る火にあたると風邪をひかない、悪い病気にかからないという言い伝えがあり、多くの参拝者がその火に当たろうと手を伸ばす。炎の高さを競い、御神木の転倒を防ぎ合う関東の奇祭としても知られている。当日には「うそ替え神事」も並行して行われる。 | |
寄居秋祭り(宗像神社秋季例大祭) 埼玉県大里郡のお祭り
歴史ある山車7台が練り歩き、提灯の明かりが寄居の街を優しく照らす。ゆったりと楽しめる寄居の秋祭り。
| 寄居秋祭り(宗像神社秋季例大祭) | |
 | 【場所】 埼玉県大里郡寄居町内 |
| 【時期】11月第1日曜日とその前日の土曜日 | |
| 【種類】山車・だんじり | |
| 【概要】 江戸時代から続く伝統的なお祭り。寄居町の総鎮守である寄居八幡宮の例大祭として行われ、五穀豊穣を感謝し、町の繁栄を願う。 最大の見どころは、絢爛豪華な山車の巡行。寄居市街( 本町から武町の間) が歩行者天国となり、本町、中町、栄町、武町、茅町、宮本、常木の歴史ある山車7台の曳きまわしを行う。彫刻や装飾が施された山車が町内を練り歩き、祭りの雰囲気を盛り上げる。夜には提灯の明かりが山車を照らし出し、幻想的な光景が広がる。 山車の巡行に加え、神輿の渡御、お囃子の演奏、そして町民による露店なども祭りの活気を彩る。地元の方々はもちろん、遠方からも多くの観光客が訪れ、寄居の秋を彩る一大イベントとして親しまれている。 | |
松明あかし 福島県須賀川市のお祭り
長さ10メートル、重さ3トンもの巨大な大松明約30本が須賀川の夜空を焦がす。400年以上の歴史を誇る日本三大火祭りのひとつ。
| 松明あかし | |
 | 【場所】 〒962-0866 福島県須賀川市栗谷沢 須賀川市翠ヶ丘公園内 五老山周辺 |
| 【時期】11月の第2土曜日 | |
| 【種類】火 | |
| 【概要】 今から400年以上前の天正17年、伊達政宗率いる軍が須賀川を攻め落とした合戦で戦死した多くの人々の霊を弔うために始められたとされている。今では戦死者の鎮魂の想いと、先人への感謝の気持ちを込め五老山で行なわれている。 巨大な松明(たいまつ)が特徴で、重さ3トン、長さ10メートルにもなるものが約30本も作られる。これらの松明は、地元の若者たちによって市内を練り歩き、五老山(ごろうさん)に立てられ、火がつけられる。 燃え盛る松明と、勇壮な松明太鼓の音が響き渡る様子は、まさに戦国絵巻さながらの迫力。夜空を焦がす炎は見る人の心を揺さぶる。 | |
牛尾の蛇祭り 千葉県香取郡のお祭り
お米の町、多古町が稲わらで長さ約8mの大蛇を作り「五穀豊穣」を祈念する。前後左右に暴れながら、鳥居に大蛇を巻きつける伝統行事。
| 牛尾の蛇祭り | |
 | 【場所】 白幡神社・潮神社 千葉県香取郡多古町牛尾 |
| 【時期】11月15日が日曜日の年は11月15日の日曜日 11月15日が日曜日以外の年は、11月15日直前の日曜日 | |
| 【種類】龍・蛇 | |
| 【概要】 江戸時代から続く祭礼で、八岐大蛇(やまたのおろち)伝説をなぞった豊作祈願の伝統行事。前日、白幡神社・潮神社の両社の氏子がそれぞれの当番の家に集り、稲藁を用いて長さ約8mの大蛇を作り、尾に「天下泰平」「五穀豊穣」と書した剣を付け、仕上った大蛇はその夜、当番の家の座敷に飾り当日を待つ。 翌朝当番の家に集合した十数名の若者達は酒肴を振まわれ、合図がかかると座敷から大蛇を担ぎ出し、氏子中の童子が扮する素戔鳴尊の荒方、稲田姫に扮する女方を先頭に立て神社に向い、囃子方が後につづく。 神社までの道中、大蛇を担いだ若者達は酒の勢いもあって前後左右にもみながら暴れ廻る。社前に至り、境内でひともみした後、鳥居に大蛇を巻きつけて一段落となる。 しかし、残念ながら人口減少や少子化などの影響で、2024年(令和6年)11月10日の開催をもって、大蛇を担ぐ形式での祭りはその歴史に幕を閉じた。今後は神事のみが行われることになる。 | |
高千穂の夜神楽 宮崎県西臼杵郡高千穂町のお祭り
町内約二十の集落で夜通し奉納される神楽。三十三番を通して日本の神々が総出演する。
| 高千穂の夜神楽 | |
 | 【場所】 宮崎県西臼杵郡高千穂町 町内約二十の集落 |
| 【時期】11月中旬-2月上旬 | |
| 【種類】舞い | |
| 【概要】 里ごとに氏神様を神楽宿と呼ばれる民家や公民館にお招きし、夜を徹して三十三番の神楽を一晩かけて奉納する、昔から受け継がれてきた神事。 例祭日は集落によって異なり、毎年11月中旬から翌年2月上旬にかけて、町内約二十の集落で奉納される。各集落の夜神楽は天照大神をはじめ、日本の神話や伝説の中に登場する神々が総出演する。 夜を徹して三十三番の神楽を奉納する「高千穂の夜神楽」は、昭和53(1978)年に国の重要無形民俗文化財に指定された。 各集落では舞う順番などが前後したり、題目が変わったり、それぞれの集落で舞いものが異なる。同じ夜神楽でも違った趣があり、いくつかの夜神楽を見るのもまた違った面白さがある。 | |
一茶まつり 東京都足立区のお祭り
小林一茶とゆかりの深いお寺で行われる俳句の祭典。想像力クイズ、奉納蛙相撲で一茶をしのぶ。
| 一茶まつり | |
 | 【場所】 炎天寺 〒121-0814 東京都足立区六月3丁目13−20 |
| 【時期】11月23日 | |
| 【種類】歌舞伎・舞台 | |
| 【概要】 小林一茶は竹の塚の作家・竹塚東子などと炎天寺の周辺をよく歩き、「蝉鳴くや六月村の炎天寺」「やせ蛙負けるな一茶是にあり」などの句を残した。 一茶の命日である11月19日に地元の有志が一茶を偲ぶ法要と石田波郷氏を特別選者に句会を開いたのがこの祭りの始まり。 現在は 11 月 23 日に「奉納蛙相撲」や「はいく想像力クイズ」など 毎年趣向をこらして開催している。 | |
新嘗祭 もちつき大会 東京都品川区のお祭り
五穀豊穣を祝って新米のおもちをたべる新嘗祭。コロナウイルス感染防止対策を講じたもちつき大会。
| 新嘗祭 もちつき大会 | |
 | 【場所】 蛇窪神社 〒142-0043 東京都品川区二葉4丁目4−12 |
| 【時期】11月23日 | |
| 【種類】食 | |
| 【概要】 五穀豊穣を祝って無料で新米のおもちを振舞う新嘗祭。その奉祝行事として餅つき大会が開催される。新嘗祭は、その年に収穫された新穀を神様に感謝する大切な祭典。餅つき大会では、地域の方々や参拝者が集まり、つきたてのお餅が振る舞われる。子供たちが餅つきに参加する様子も見られ、大変賑わう。 また、新嘗祭限定の御朱印が授与されることもある。白蛇伝説が残る蛇窪神社ならではの活気あふれる行事として、地域住民に親しまれている。 2021年はコロナウイルス感染防止対策を講じてできるだけ人の手に触れないよう、蒸し器、餅つき機を使用して巫女のみがおもちを扱うこととなった。 | |
新嘗祭 東京都渋谷区のお祭り
収穫された恵みに感謝し日本らしさを強く感じられる祭り。境内には色とりどりの野菜で作られた宝船。
| 新嘗祭 | |
 | 【場所】 明治神宮 〒151-8557 東京都渋谷区代々木神園町1−1 |
| 【時期】11月23日 | |
| 【種類】人形・装飾 | |
| 【概要】 その年に収穫された新穀を神様に捧げ、収穫の恵みに感謝し、国家の安泰と国民の繁栄を祈願するもの。 宮中においても同様に新嘗祭が行われ、天皇陛下が新穀を神々に供え、これらの供え物を神からの賜りものとして自らもお召し上がりになる。 明治神宮では、全国各地から奉納された新穀や野菜、海産物などが神前に供えられ、厳かな雰囲気の中で祭典が執り行われる。野菜で作られた宝船もみられる。多くの参拝者が訪れ、五穀豊穣への感謝と国の平安を共に祈る。 | |
新嘗祭どぶろく祭 東京都中央区のお祭り
秋の収穫を感謝し、濁り酒が振舞われる。築地 波除神社の秋のお祭り。
| 新嘗祭どぶろく祭 | |
 | 【場所】 波除神社 〒104-0045 東京都中央区築地6丁目20−37 |
| 【時期】11月23日 | |
| 【種類】酒 | |
| 【概要】 波除神社における年に3回の「大祭」の1つ(春の初めの祈年祭、例大祭、そして秋の収穫を感謝する「新嘗祭」)。 秋の収穫に感謝するお祭りで、神社の御神饌田で収穫された新米で作られた濁り酒「幸穂(さちほ)」が神前に供えられ、参拝者に無料で振る舞われる。 新嘗祭は、天皇陛下が新穀を神々に供え、自らも召し上がるという古くからの宮中行事であり、全国の神社でも同様に執り行われる。 波除神社では、この日にあわせて「どぶろく祭」として、地域の方々や参拝者が収穫の恵みを分かち合う場を設けている。 当日は、神事のほか、境内では様々な催し物が行われることもあり、多くの人で賑わう。築地の活気とともに、秋の豊かな実りに感謝する温かいお祭り。 | |
東中野の獅子舞 埼玉県春日部市のお祭り
つつましくも、しっかりと歴史を感じる市指定無形民俗文化財の獅子舞。
| 東中野の獅子舞 | |
 | 【場所】 東中野香取神社 〒344-0114 埼玉県春日部市東中野366 |
| 【時期】11月第3日曜日 | |
| 【種類】獅子 | |
| 【概要】 この獅子舞は、雄獅子、雌獅子、子獅子の3頭が笛や太鼓の音に合わせて舞う「三匹獅子舞」。地区内を巡る「辻切り」と東中野香取神社境内で行われる「奉納舞」がある。越谷市の下間久里の獅子舞から伝授されたもの。「天下無双角兵衛獅子舞」と呼ばれる勇壮な舞が見どころ。 力強く勇壮な舞は地域の人々にとって大切な行事であり、多くの見物客で賑わう。県の無形民俗文化財に指定されている。 | |
羽黒山梵天祭り 栃木県宇都宮市のお祭り
五穀豊穣・無病息災を願って、色鮮やかな房を付けた長さ約17mの梵天が上下に振られる。300年以上続く羽黒山神社の例大祭。
| 羽黒山梵天祭り | |
 | 【場所】 栃木県宇都宮市今里町 羽黒山神社及び今里町地内 |
| 【時期】11月下旬 | |
| 【種類】 | |
| 【概要】 収穫を感謝する行事として江戸時代中期から約300年続く伝統行事。最大15メートルにもなる孟宗竹と真竹で作られた長い竿の先端に、色鮮やかな房を付けた神具「梵天」を、揃いの法被姿の若者たちが「ホイサ、ホイサ」と威勢の良いかけ声と共に担ぎ、山頂の神社まで約3キロメートルの参道を上下に振りながら練り歩く。 祭りの当日は、沿道に多くの露店が立ち並び、特に地元名産のゆずや、伝統的なごちそう「鮎のくされ鮨」などが売られ、賑わいを見せる。その勇壮な姿は圧巻。 | |
以上、「11月のお祭り」でした。他の月のお祭りもまとめています。どうぞ以下からご覧ください。
1月のお祭り 2月のお祭り 3月のお祭り 4月のお祭り 5月のお祭り 6月のお祭り 7月のお祭り 8月のお祭り 9月のお祭り 10月のお祭り 11月のお祭り 12月のお祭り