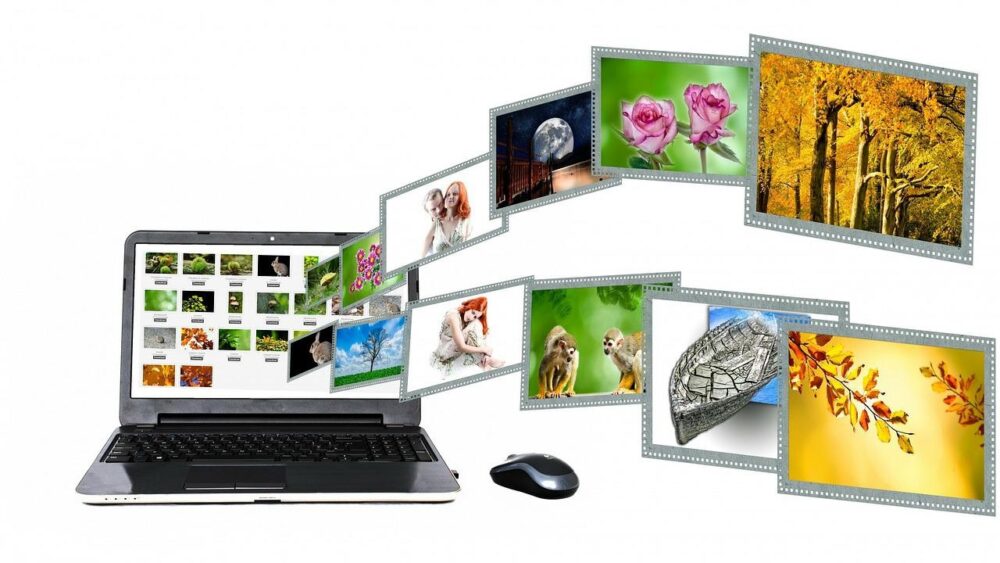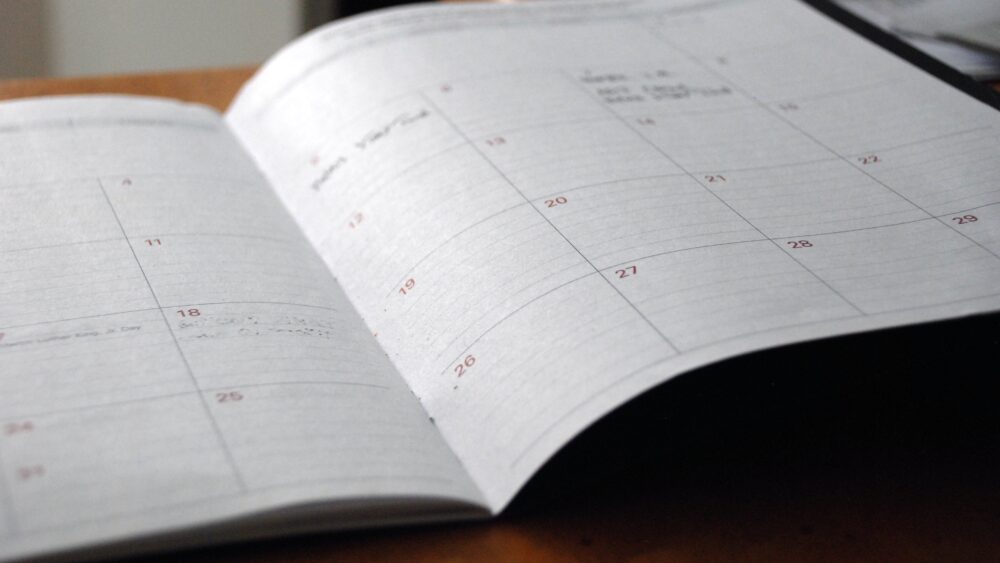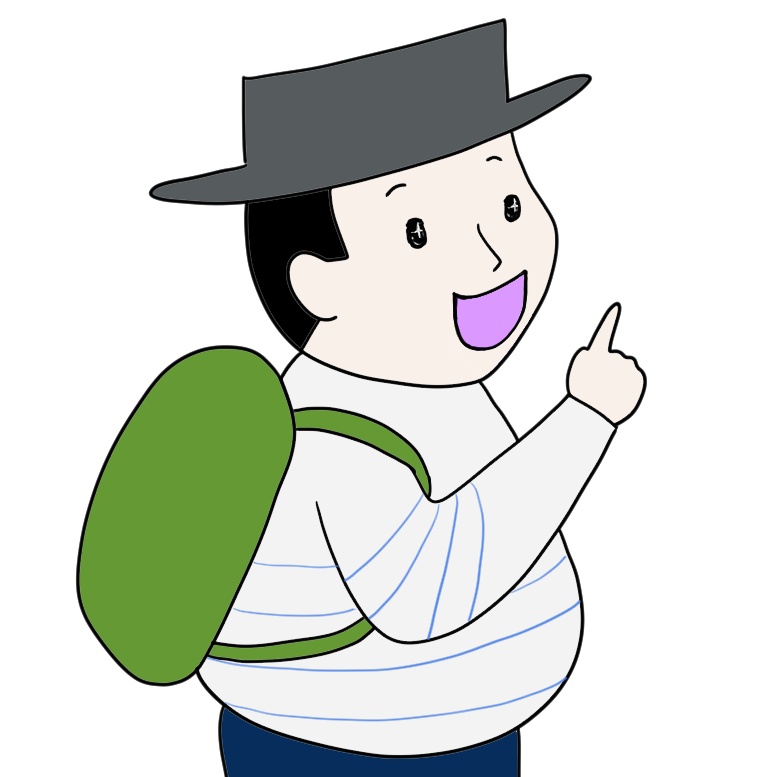ぽちゃま
全国のお祭りでは獅子が神聖なものとして扱われ、舞いに用いられたり担がれることが多くあります。そして獅子の形や素材も実に様々。そんな獅子のお祭りをご紹介します。
詳細記事はリンクをクリックしてご覧ください。
目次
下柴彼岸獅子舞 3月福島県喜多方市のお祭り
喜多方ラーメンの街で出会う重要無形民俗文化財。

| 名称 | 下柴彼岸獅子舞 |
| 概要 | 喜多方駅前通り、喜多方市役所、ふれあい通り、おたづき蔵通りなどの店舗前や沿道、広場などで獅子舞が披露される。 春の彼岸に舞うことから、下柴彼岸獅子といの名となり、福島県の無形民俗文化財。会津彼岸獅子舞の発祥。 |
| 開催場所 | 福島県喜多方市中心部 |
| 時期 | 「春分の日」を中日とした前後3日間 |
| 問合せ | 喜多方市 文化課 TEL:0241-24-5323 |
| 参考 |
下柴彼岸獅子舞のくわしい記事
会津彼岸獅子 3月福島県会津若松市のお祭り
春の彼岸入りに、三体の獅子が豊作と家内安全を祈りながら舞う。

| 名称 | 会津彼岸獅子 |
| 概要 | 春の彼岸入りに、三体の獅子が笛と太鼓の音色に合わせて、舞を披露しながら鶴ヶ城、阿弥陀寺など市内各所を練り歩く。豊作と家内安全を祈り、春の訪れを喜び合う会津の伝統行事。 お盆などにお墓やお寺などで祖先の供養として踊ったと言われており、春の彼岸の時期に舞われることから「彼岸獅子」と呼ぶようになった。 戊辰戦争の際には包囲された鶴ヶ城へ戦わずして入場するため奇策としても活用された。 |
| 開催場所 | 福島県会津若松市 鶴ヶ城、阿弥陀寺、ほか市内各所 |
| 時期 | 3月20日(春分の日) |
| 問合せ | 会津まつり協会 〒965-0042 福島県会津若松市大町1-7-3 TEL:0242-23-4141 |
| 参考 | 会津まつり協会 |
会津彼岸獅子のくわしい記事
横中馬の獅子舞 4月東京都武蔵村山市のお祭り
横田、中村、馬場の3地区の人々が五穀豊穣、無病息災、悪疫退散を祈願する。黒い獅子達が市内を練り歩き舞いを奉納する春のお祭り。
| 横中馬の獅子舞 | |
 | 【場所】 東京都武蔵村山市 |
| 【時期】4月29日 | |
| 【種類】獅子 | |
| 【概要】 横田、中村、馬場の三地区の氏神に五穀豊穣、無病息災を祈願して三匹獅子舞が奉納される。 黒い毛が特徴の三匹の獅子が、笛や太鼓、ささらの音に合わせて勇壮に舞い踊る。露払いとして棒術を披露する少年たちや、花笠をかぶって色とりどりの衣装で舞う「ささらすり」の少女たちも見どころ。 江戸時代中期から続く伝統芸能で、市の無形民俗文化財に指定されている。 | |
鳥見神社の獅子舞 5月千葉県印西市のお祭り
いにしえより受け継がれてきた悪魔払いと豊作を祈念した獅子舞。ジジ(親獅子)、セナ(子獅子)、カカ(雌獅子)の3匹の獅子が舞う。

| 名称 | 鳥見神社の獅子舞 |
| 概要 | 保存会によって獅子舞が、毎年5月3日の例大祭で奉納される。獅子舞は、悪魔払いと豊作を祈念して行われ、この日を「おこと」という。 舞人は、氏子の青年男子が選ばれ、ジジ(親獅子)・セナ(若獅子)・カカ(雌獅子)の3匹によって舞わる。舞は「初の切」・「二の切」・「弓越えの舞」・「寝起きの舞」・「三角の舞」・「みみず拾いの舞」・「けんかの舞」・「仲直り三角の舞」「くじびきの舞」等で構成される。 着物や帯を獅子舞人につけて舞ってもらうと幸福になると言われている。千葉県無形民俗文化財。 |
| 開催場所 | 千葉県 印西市 平岡1476 平岡鳥見神社 |
| 時期 | 5月3日 |
| 問合せ | 印西市役所教育委員会 教育部生涯学習課文化係 TEL: 0476-33-4714 FAX: 0476-42-0033 |
| 参考 | 鳥見神社の獅子舞[県指定無形民俗文化財] |
鳥見神社の獅子舞のくわしい記事
長崎獅子祭 5月東京都豊島区のお祭り
豪華な羽と袴のいで立ちで、長崎神社周辺を獅子が舞い踊る。

| 名称 | 長崎獅子祭 |
| 概要 | 獅子頭を被った三頭の獅子が、腹につけた太鼓を打ち鳴らしながら長崎神社周辺を舞い踊る。元禄年間から伝承される豊島区の民俗芸能。区の無形民俗文化財にも指定されている。 獅子は華やかな盛装とボリュームのある獅子頭が特徴的で「病気平癒」や「五穀豊穣」を願い舞う。 |
| 開催場所 | 〒171-0051 東京都豊島区長崎1丁目9-4長崎神社周辺 |
| 時期 | 5月の第2日曜日 |
| 問合せ | 長崎神社 〒171-0051 東京都豊島区長崎1丁目9-4 |
| 参考 | 長崎獅子舞 – オフィシャルホームページ! |
長崎獅子祭のくわしい記事
つきじ獅子祭り 6月東京都中央区のお祭り
威勢の良い築地人が巨大な獅子を担いで街を練り歩く。夏の訪れを告げる築地の風物詩。
| つきじ獅子祭り | |
 | 【場所】 波除神社 〒104-0045 東京都中央区築地6丁目20−37 |
| 【時期】6月10日前後数日 | |
| 【種類】獅子 | |
| 【概要】 三年に一度の「本祭り」は、獅子頭神輿の雄雌どちらかの獅子と神社千貫宮神輿の2基が渡御され、「陰祭り」は、本社大神輿と獅子頭神輿のうち1基が渡御される。 この祭りは、江戸時代に築地が埋め立てられた際、荒波を鎮めるためにご神体を祀ったことに由来するとされ、商売繁盛や厄除けの願いが込められている。期間中は縁日も立ち並び、多くの人で賑わう。 【2024年】 ●6月7日(金)鎮花祭(疫病除け・百合の花神事)、宵宮祭 ●6月8日(土)江戸里神楽奉納(石森社中) ●6月9日(日)渡御祭・千貫宮神輿ご巡行 9:00宮出し(築地全町ご巡行) 15:30宮入り・帰社祭 ●6月10日(月)大祭式 R6つきじ獅子祭 順路図 | |
水止舞 7月東京都大田区のお祭り
雨を止めるために行われる大田区の奇祭。道行で龍(水神)を喜ばせ、舞台上で龍を鎮めるために獅子舞を行う。
| 水止舞 | |
 | 【場所】 厳正寺 〒143-0012 東京都大田区大森東3丁目7−27 |
| 【時期】7月第2日曜日 | |
| 【種類】獅子 | |
| 【概要】 古くから水害に悩まされてきた地域で、雨乞いと雨止めの両方を祈る珍しい民俗芸能。 前半の「道行」では、藁で作られた龍に若者が入り、法螺貝を吹きながら水を浴びせられ、雨乞いの様子を表現する。。 後半は厳正寺の境内に舞台を移し、3匹の獅子が笛や唄に合わせて舞を奉納する。これは、雨を鎮め、止めることを祈願するもの。 この独特な儀式は、都の無形民俗文化財に指定されている。 | |
住吉神社例大祭 8月東京都中央区のお祭り
佃煮発祥の地の由緒ある祭り。3年に1度の本祭りでは獅子頭の宮出しや八角神輿の渡御が行われる。
| 住吉神社例大祭 | |
 | 【場所】 住吉神社(佃) 〒104-0051 東京都中央区佃1丁目1−14 |
| 【時期】8月上旬 | |
| 【種類】獅子 | |
| 【概要】 毎年8月6日・7日に行われる「蔭祭り」と、3年に一度行われる「本祭り」があります。 本祭りでは、八角神輿や龍虎・黒駒などの勇壮な獅子頭が町内を練り歩き、特に神輿を船に乗せて氏子地域を巡る「船渡御(ふねとぎょ)」は、かつて隅田川に神輿を担いで入る「海中渡御」の名残とも言われ、見どころの一つ。 また、高さ18メートルにも及ぶ大幟が立てられ、江戸の祭礼における「町神輿」「水かけ」「掛け声」という特徴を色濃く残している。 地域の住民が一丸となって盛り上げる活気あふれる祭りで、中央区の無形民俗文化財にも指定されている。 住吉神社例大祭2023_行事日程 | |
石岡のおまつり(常陸國總社宮例大祭) 9月茨城県石岡市のお祭り
各町独自の幌をまとった巨大な獅子が石岡の街を練り歩く。石岡市民が1年で最も熱くなるお祭り。

| 名称 | 石岡のおまつり(常陸國總社宮例大祭) |
| 概要 | 延享年間に奉納相撲が始まり、明治時代前半に豪華な出し物が街なかを練り歩く現在の基礎が固まる。 「正月やお盆には帰省しなくても、おまつりには帰る」と言われるほど、出身者にとっては思い入れのある祭りで関東三大祭の1つである。 「幌獅子」と呼ばれる大きな獅子の頭と布の幌(胴幕)が掛けられた小屋でできた巨大な獅子が石岡の中心地を練り歩く。幌の色は通常2色で、布の色で町内が分かるように各町内独自の色を使用している。 日が落ちると石岡駅前では囃子屋台と幌獅子が集合し、より一層祭りを盛り上げる。 石岡のおまつりポスター |
| 開催場所 | 茨城県 石岡市中心部 常陸國總社宮、石岡駅周辺 |
| 時期 | 9月15日と敬老の日を最終日とする3日間 |
| 問合せ | 石岡市観光協会 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市役所(観光課内) TEL:0299-23-1111 |
| 参考 | 石岡市観光協会公式ホームページ |
石岡のおまつり(常陸國總社宮例大祭)のくわしい記事
東中野の獅子舞 11月埼玉県春日部市のお祭り
つつましくも、しっかりと歴史を感じる市指定無形民俗文化財の獅子舞。

| 名称 | 東中野の獅子舞 |
| 概要 | 地区内を巡る「辻切り」と東中野香取神社境内で行われる「奉納舞」がある。越谷市の下間久里の獅子舞から伝授されたもの。 「天下無双角兵衛獅子舞」と呼ばれる勇壮な舞が見どころ。 |
| 開催場所 | 〒344-0114 埼玉県春日部市東中野366東中野香取神社 |
| 時期 | 11月第3日曜日 |
| 問合せ | 春日部市 文化財保護課 TEL:048-763-2449 |
| 参考 | 東中野の獅子舞 |
東中野の獅子舞のくわしい記事
以上獅子のお祭りでした。日本にはまだまだ面白いお祭りがいっぱい。 種類の違うお祭りもご紹介していますのでぜひご覧ください。
「種類」からお祭りを探すはこちら

「種類」からお祭りを探す
ぽちゃま
日本のお祭りは神輿を担いだり、山車を曳いたり、獅子や龍が出たかと思いきや行燈や提灯で幻想的な装飾を楽しむものなど実に様々な...
ABOUT ME