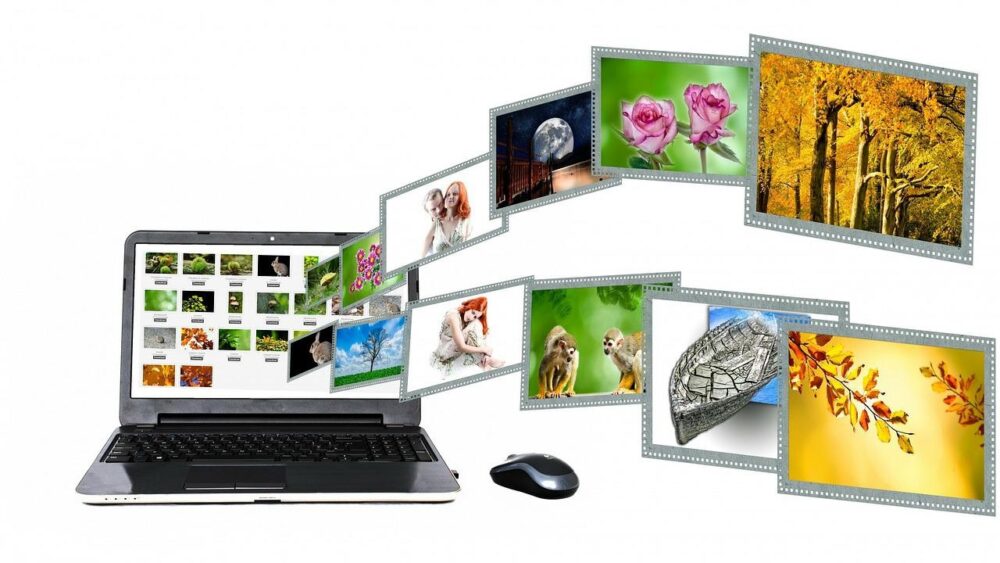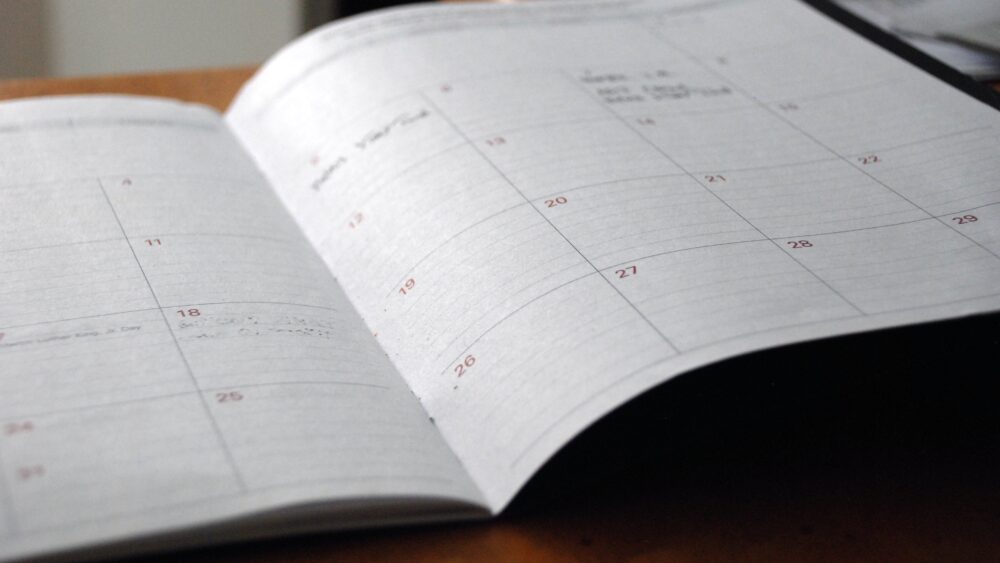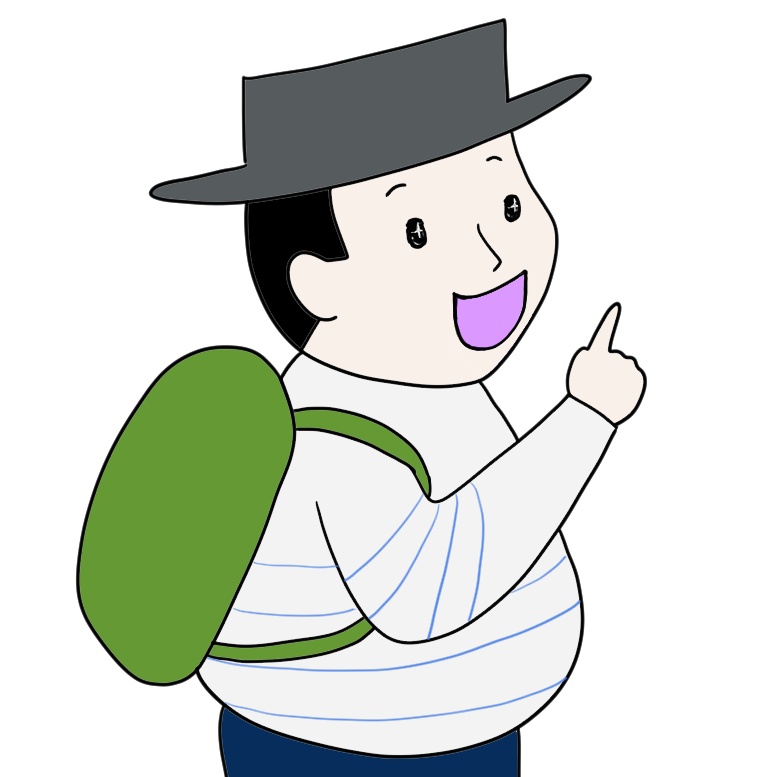9月のお祭りをまとめました。
詳細記事はリンクをクリックしてご覧ください。
目次
天草伊勢えび祭り 熊本県天草市のお祭り
天然新鮮!ぷりっぷりの伊勢えびを頂ける天草市の食のお祭り 。漁の解禁時期に合わせて設定される宿泊プランを利用して大満足の旅。
| 天草伊勢えび祭り | |
 | 【場所】 熊本県天草市内 |
| 【時期】8月中旬-12月 | |
| 【種類】食 | |
| 【概要】 天草の5つのエリアで、天然新鮮なぷりっぷり伊勢えびが楽しめる祭り。 祭りの期間中、天草市内の旅館や飲食店では、刺身、鬼瓦焼き、具足煮、味噌汁など、伊勢えびの旨みを最大限に引き出した様々な料理が提供される。新鮮でぷりぷりの伊勢えびは、その濃厚な甘みと弾力のある食感が特徴で、まさに海の恵みを堪能できる。 また、伊勢えび料理だけでなく、天草の特産品が並ぶ物産展や、郷土芸能の披露など、様々な催しが行われ、訪れる人々を楽しませる。美しい天草の自然と美味しい海の幸を同時に楽しめるため、多くの観光客で賑わう。 地元の人々にとっても、秋の訪れを告げる風物詩として親しまれており、天草の魅力を国内外に発信する重要なイベントとなっている。 | |
おわら風の盆 富山県富山市のお祭り
胡弓が奏でる哀調、編笠姿の踊り手たちが越中八尾の路地を行き過ぎる。大人向けの落ち着いた北陸の盆踊り。
| おわら風の盆 | |
 | 【場所】 富山県富山市八尾地区 |
| 【時期】9月1-3日 | |
| 【種類】踊り | |
| 【概要】 越中おわら節にあわせて踊り手たちが優雅に舞う伝統的な祭り。この祭りの起源は江戸時代に遡り、五穀豊穣を祈り、また台風からの風の被害を鎮める「風祭り」として始まった。 最大の特徴は、哀愁を帯びたおわら節の地方(じかた)の調べと、揃いの浴衣や編笠をかぶった男女が、提灯の灯りの下、洗練された踊りを披露する姿。特に、編笠で顔を隠すことで生まれる幻想的な雰囲気と、しっとりとした踊りは多くの人々を魅了する。 地域ごとの「町流し」では、それぞれの町の特色ある踊りが披露され、八尾の町並みを幽玄な世界に変える。11の町それぞれに支部があり、それぞれのルート、独自の輪踊り・街流しがある。 夜の提灯の明かりの中で踊られる「月見踊り」は、おわら風の盆の真髄とも言える。 | |
二宮神社秋季例大祭(生姜祭り) 東京都あきる野市のお祭り
無病息災を願って生姜が販売される。二宮神社へ神輿が駆け上がる、圧巻の宮入。
| 二宮神社秋季例大祭(生姜祭り) | |
 | 【場所】 二宮神社 〒197-0814 東京都あきる野市二宮2252 |
| 【時期】9月8・9日 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 あきるの三大祭りのひとつ。別名「生姜祭り」の愛称で親しまれているお祭りで、 古くから祭りに神饌の中に「牛の舌の形の餅」「子持ちの里いも」「葉根付き生姜」を備えることになっている。 二宮周辺で採れた生姜をお祭りにお供えしたことからから、二宮神社の無病息災の生姜として知られるようになり、境内には生姜売りの店が多く立ち並びたくさんの人が訪れるようになった。現在の厄除生姜の販売は毎年行列ができる。 当日は神輿の宮出し・宮入りが行われ、特に神輿が石段を駆け上がる宮入は圧巻。境内には多くの露店が立ち並び、吹奏楽や和太鼓の演奏、さらには東京都無形民俗文化財である「秋川歌舞伎」の奉納も行われ、多くの来場者で賑わう。地元に根付いた歴史あるお祭りで、「あきる野三大まつり」の一つにも数えられている。 【2023年】 ●9月8日(日)宵宮 16:00- 囃子と山車の町内巡行、府中二之宮大太鼓町内巡行、東中学校吹奏楽 16:00- 境内特設舞台 秋留台高校和太鼓、演芸大会 ●9月9日(月)例大祭 10:00- 例大祭式典 11:30- 神社神輿宮出し 14:30- 子ども神輿 16:00- 中学生神輿 15:00- 秋留台高校和太鼓 17:00- 奉納芸能大会 19:00- 神輿宮入 東京都指定無形民俗文化財「秋川歌舞伎」奉納 宮入後 | |
北澤八幡神社例大祭 東京都世田谷区のお祭り
古着とレコードの街で行う神輿の渡御。八睦会の神輿が北澤八幡神社に勢ぞろい。
| 北澤八幡神社例大祭 | |
 | 【場所】 北澤八幡神社 〒155-0032 東京都世田谷区代沢3丁目25−3 下北沢駅周辺 |
| 【時期】9月第1土曜日、日曜日 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 通称「北澤八幡秋まつり」で下北沢地区では最大級のお祭り。毎年氏子地域にある八つの睦会が順番に「年番」を担当しており、本宮では、各睦会の大小23基の神輿や太鼓が揃って宮入りするという壮大な景色が繰り広げられる。特に3年に一度行われる本社神輿(宮神輿)の渡御では、その勇壮な姿に多くの観客が沸き立つ。 境内でも、江戸神楽から雅楽、巫女舞、和太鼓など様々な催しが予定されており、下北沢一帯が祭りの熱気に包まれる例大祭。 13時からは代沢三差路に集った御神輿が北澤八幡神社に向かって宮入りへ、14時半から祭典式が齊行された後、各々の御神輿はそれぞれの地域に戻り、17時からは奉納演芸が行われる。 【2023年】 ●9月2日(土)宵宮 12:00 – 21:00 縁日 13:00 和太鼓・お囃子 14:00 – 20:00 奉納演芸 ●9月3日(日)例大祭 10:00 – 21:00 縁日 13:00 神輿宮入り 14:30 祭典式齊行 17:00 – 20:00 奉納演芸 2023年 北澤八幡神社例大祭 奉納演芸プログラム | |
春木だんじり祭 大阪府岸和田市のお祭り
昼の激しい「やりまわし」から一変。赤い駒提灯のだんじりを皆で楽しむ優しい祭。
| 春木だんじり祭り | |
 | 【場所】 大阪府岸和田市 春木駅周辺 |
| 【時期】9月第1日曜日 | |
| 【種類】山車・だんじり | |
| 【概要】 岸和田だんじり祭りの一つに数えられ、豪壮なだんじりが曳行されることで知られている。 12台のだんじりが春木駅前商店街などを練り歩き、特に「やりまわし」と呼ばれる、だんじりを勢いよく角で方向転換させるS字走行は見どころ満点。屋根の上に乗った「大工方(だいくがた)」の華麗な舞いと、曳き手たちの息の合った動きが一体となり、観客を魅了する。 夜には提灯に彩られただんじりが幻想的な雰囲気を醸し出し、昼間とは異なる趣を楽しめる。地域住民の熱気が一体となった、活気あふれる祭り。 | |
岸和田だんじり祭 大阪府岸和田市のお祭り
広い世代で統制された組織だからこそ曳きまわす事ができる「勇壮」と「危険」が隣り合うだんじり。
| 岸和田だんじり祭 | |
 | 【場所】 大阪府岸和田市岸和田城下およびその周辺 |
| 【時期】 試験曳き : 9月第1日曜日(ただし、第1日曜日が9月1日の場合は9月第2日曜日の9月8日に変更となる)・宵宮前日の金曜日 宵宮(宵祭) : 本宮前日の土曜日 本宮(本祭) : 敬老の日前日の日曜日 | |
| 【種類】山車・だんじり | |
| 【概要】 重さ4トンを超える豪華絢爛な「だんじり(地車)」を、数百人の曳き手が一丸となって豪快に曳行します。 最大の見どころは、だんじりを勢いよく走らせながら、直角の曲がり角をスピードを落とさずに曲がる「やりまわし」。大工方がだんじりの屋根で舞い、曳き手を指揮する姿は「祭りの華」と呼ばれ、観衆を魅了する。 億単位の資金を集めて用意されるだんじりは町民文化と儒教、道教、仏教、神道が融合された芸術品であり、施された彫刻が繊細なことでも知られている。 夜には約200個の提灯で飾られ、昼間とは異なる幻想的な雰囲気になる。 | |
目黒のさんま祭り 東京都品川区のお祭り
さんまは目黒にかぎる!古典落語から始まったさんまのお祭り。長蛇の列に並びながら気分は江戸のお殿様。
| 目黒のさんま祭り | |
 | 【場所】目黒駅駅前商店街 |
| 【時期】9月の第1または第2日曜日 | |
| 【種類】食 | |
| 【概要】 古典落語「目黒のさんま」にちなんで開催される、東京の秋の風物詩。 祭りの目玉は、宮城県気仙沼市や岩手県宮古市などから直送された新鮮なさんまを、炭火で焼いて無料で振る舞われること。大分県産のかぼすや栃木県産の大根おろしが添えられることもあり、長蛇の列ができるほどの人気。 焼きさんまの配布は事前申し込み制や抽選となることが多い。また、落語「目黒のさんま」の寄席や、地域の名産品が並ぶ「ふるさと物産展」、子供向けのイベントなども開催され、多くの人で賑わう。 | |
芝大神宮 だらだら祭り 9月東京都港区のお祭り
長くつづく事から名づけられた関東のお伊勢さまのお祭り。大東京のオフィスで行われる渡御。
| 芝大神宮 だらだら祭り | |
 | 【場所】 東京都港区芝大門1丁目12-7芝大神宮 |
| 【時期】9月11日-21日の11日間 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 毎年9月11日から21日までの11日間にもわたって行われる、期間の長さが特徴の例大祭。その長さから、江戸っ子たちが「だらだら祭り」と揶揄したことが名称の由来とされている。 江戸時代には「関東のお伊勢さま」として全国からの参拝客で賑わったため、多くの人が訪れられるよう祭礼期間が長くなったと言われている。 祭りの名物としては、邪気を払うとされる「生姜」が頒布される「生姜市」や、衣類が増え、良縁に恵まれる縁起物として知られる「千木筥(ちぎばこ)」の授与がある。期間中には、宮神輿や各町会神輿の渡御(隔年開催)も行われ、多くの人々で賑わう。 2023年だらだら祭りチラシ | |
石岡のおまつり(常陸國總社宮例大祭) 茨城県石岡市のお祭り
各町独自の幌をまとった巨大な獅子が石岡の街を練り歩く。石岡市民が1年で最も熱くなるお祭り。
| 石岡のおまつり(常陸國總社宮例大祭) | |
 | 【場所】 茨城県 石岡市中心部 常陸國總社宮、石岡駅周辺 |
| 【時期】9月15日と敬老の日を最終日とする3日間 | |
| 【種類】獅子 | |
| 【概要】 「正月やお盆には帰省しなくても、おまつりには帰る」と言われるほど、出身者にとっては思い入れのある祭りで関東三大祭の1つである。 最大の見どころは、約200名で担がれる格式高い「大神輿」、全国的にも珍しい大型の「幌獅子(ほろじし)」約30台、そして豪華な装飾が施された「山車」12台が町中を練り歩く壮観な光景。山車の上では「おかめ」「ひょっとこ」「きつね」などの踊りが石岡囃子に合わせて披露される。 ※「幌獅子」とは大きな獅子の頭と布の幌(胴幕)が掛けられた小屋でできた巨大な獅子。幌の色は通常2色で、布の色で町内が分かるように各町内独自の色を使用している。 毎年約50万人もの観光客が訪れ、市街地は熱気に包まれる。 石岡のおまつりポスター | |
鶴岡八幡宮流鏑馬神事 神奈川県鎌倉市のお祭り
源頼朝が催行したのがそのはじまり。その後、神事の武技として各地で奉納されるようになった流鏑馬の源。
| 鶴岡八幡宮流鏑馬神事 | |
 | 【場所】鶴岡八幡宮 〒248-8588 神奈川県鎌倉市雪ノ下2丁目1−31 |
| 【時期】9月16日 | |
| 【種類】流鏑馬・備射祭 | |
| 【概要】 源頼朝が1187年(文治3年)に始めたとされ、800年以上の歴史を持つ鎌倉を代表する伝統神事。流鏑馬の源として弓馬術礼法小笠原教場一門によって奉納される。 鎌倉武士さながらの狩装束に身を包んだ射手が、約250メートルの馬場を疾走する馬上から3つの的を次々と鏑矢(かぶらや)を射抜く勇壮な姿は圧巻。天下泰平や五穀豊穣などを祈願する意味合いがあり、武士文化を間近に感じられる貴重な機会として多くの観客を魅了する。射手が矢を放つ際の「イン、ヨー、イ」という独特の掛け声も特徴的。 | |
面掛行列 神奈川県鎌倉市のお祭り
爺、鬼、天狗、火吹き男など、10種類の面をかぶった男達が練り歩く鎌倉の奇祭。
| 面掛行列 | |
 | 【場所】 御霊神社(権五郎神社) 〒248-0021 神奈川県鎌倉市4 鎌倉市坂ノ下4−9 |
| 【時期】9月18日 | |
| 【種類】行列 | |
| 【概要】 疫病退散や五穀豊穣を願う祭礼で神奈川県の無形民俗文化財。 この行列では、神社の氏子たちが爺(じい)、鬼(おに)、異形(いぎょう)、鼻長(はななが)、烏天狗(からすてんぐ)など、10種類の面を被った人が古装束を身につけて練り歩く。特にユニークなのは、行列の途中で面をつけた人々が互いに顔を見せあったり、観客に話しかけたりする場面があること。 また、別名「はらみっと祭」とも言われ「おかめ」のお腹に触れると安産祈願となると言われている。 鎌倉時代から続く歴史を持つとされ、地域の人々にとっては欠かせない大切な祭りとなっている。 | |
吾妻神社馬だしまつり 千葉県富津市のお祭り
馬が砂浜を駆け抜ける勇壮な神事と、幻想的な雰囲気の中で神輿が担がれる神事。千葉県の無形民俗文化財。
| 吾妻神社馬だしまつり | |
 | 【場所】 千葉県 富津市 岩瀬海岸/吾妻神社 ※馬だしの神事は岩瀬海岸 |
| 【時期】9月中旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 馬だし、オブリ、神輿を中心とした神事が行われ、五穀豊穣や、海上の安全、大漁を祈願する。「馬だし」はオメシと呼ばれる神馬の鞍に神霊を移した幣束(へいそく)をつけ、2人の青年が馬の手綱を持ち両脇にしがみついて海岸を疾走する神事。 オメシが神輿に先立って神社から下山し、海岸を疾走した後、幣束を遺品の漂着地に埋める。その後、オメシは神社へ戻り、神輿が海へ入る「お浜出」が行われる。 ちなみに神霊を馬上に移し渡御する神事は飾り神輿のできる以前の祭りとして重要なもの。提灯が幻想的な雰囲気を出す19時半頃、神輿は吾妻神社に戻ってきて、祭礼が終了となる。千葉県無形民俗文化財に指定されている。 | |
雷門盆踊り 夢灯篭 東京都台東区のお祭り
雷門の目の前で、スカイツリーを見上げながら踊る盆踊り。アンコール曲は波乗りジョニー。
| 雷門盆踊り 夢灯篭 | |
 | 【場所】 浅草寺雷門前 |
| 【時期】9月中旬 | |
| 【種類】踊り | |
| 【概要】 浅草のシンボルである雷門を背景に、幻想的な盆踊りが繰り広げられる。 雷門盆踊り 夢灯篭は9月東京都台東区の雷門の目の前で、開催される盆踊り大会。 路地ではさまざまな表情の着物姿の美人画が描かれた約2メートルの絵どうろうが飾られる。スカイツリーを見上げられるロケーションで、東京音頭、大東京音頭、たいとう音頭、波乗りジョニーなど東京らしい曲目で盆踊りが行われる。 地域住民だけでなく国内外からの観光客も多く訪れ、国際色豊かな交流の場ともなっている。日本の夏の伝統文化と現代的な要素が融合した、唯一無二の盆踊り体験ができる。 | |
浅草サンバカーニバル 東京都台東区のお祭り
浅草の夏を締めくくる北半球最大のサンバカーニバル。バテリア隊、ダンサー、アレゴリア(山車)が浅草の町を練り歩く。
| 浅草サンバカーニバル | |
 | 【場所】 浅草 馬道通り-雷門通り |
| 【時期】9月中旬 | |
| 【種類】踊り | |
| 【概要】 1981年に始まり、本場ブラジルのリオのカーニバルを思わせる華やかさと熱気で知られている。 このカーニバルの最大の見どころは、煌びやかな衣装をまとったサンバチームによるパレード。各チームはテーマに沿ったフロートや楽器隊、ダンサーが一体となり、浅草の街を練り歩く。その情熱的な踊りとサンバのリズムは、観客を魅了し、浅草は一日中、熱狂的なお祭りの雰囲気に包まれる。 単なるイベントではなく、浅草の夏の風物詩として地域に深く根付いており、多くの人々がその開催を心待ちにしている。 | |
牛嶋神社大祭 東京都墨田区のお祭り
お牛様が曳く鳳輦が東京下町を巡行する。5年に一度、牛嶋神社の大祭。
| 牛嶋神社大祭 | |
 | 【場所】 牛嶋神社とその周辺 |
| 【時期】9月中旬 | |
| 【種類】行列 | |
| 【概要】 牛嶋神社で行われる例大祭で5年に一度は「大祭(本祭り)」として盛大に執り行われる。 牛が曳く鳳輦(牛車)を中心に手古舞、稚児などが加わった古式ゆかしい行列が、広大な氏子エリアを全行程約35キロメートルにわたって巡行される神幸祭が2日間をかけて行われる。 神幸祭2日目の夕方には「東京スカイツリーソラマチひろば」で「世界平和祈願祭」が執り行われる。 最終日の日曜日には、関東大震災や空襲の難を免れた名工の巧みな技術が活きた逸品も多く存在している、墨田区内の氏子各町約50基の大神輿が3組に分かれて集結し、牛嶋神社へ向かって渡御される連合神輿宮入が盛大に行われ、祭りは最高潮を迎える。 期間中は、各町会で子供神輿や山車の巡行、夜店、奉納踊りなども催され、地域全体が祭りの熱気に包まれる。本所地区の総鎮守である牛嶋神社の、歴史と伝統を感じさせるお祭り。 | |
金王八幡宮例大祭 東京都渋谷区のお祭り
渋谷の街に14基の神輿が繰り出す。若者の街で執り行う伝統行事。
| 金王八幡宮例大祭 | |
 | 【場所】 渋谷駅周辺 |
| 【時期】9月中旬 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 寛治6年(1092年)に創建された金王八幡宮の例祭として、五穀豊穣、街の繁栄、氏子崇敬者の無病息災を祈願して数百年間続けられてきた。 見どころは、渋谷の各町会から参加する14基の神輿がSHIBUYA109前に集結し、一斉に担ぎ上げられる連合渡御。迫力満点の光景は祭りの最高潮を迎え、多くの見物客で賑わう。また、境内では里神楽などの奉納行事や露店も多数出店し、国際都市渋谷ならではの多様な人々が祭りを盛り上げる。 | |
勝浦大漁まつり 千葉県勝浦市のお祭り
漁師町らしい威勢の良い掛け声が響く、力強く、活気あふれる千葉の海のおまつり。
| 勝浦市秋季合同祭(勝浦大漁まつり) | |
 | 【場所】 千葉県勝浦市中心部 |
| 【時期】9月敬老の日(9月第3月曜日)を最終日とする4日間 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 江戸時代後期に起源を持ち、千葉県の「ちば文化資産」にも選定されている。 この祭りの見どころは、各地区の神輿や江戸後期築造の屋台、山車の巡行です。特に2日目には墨名(とな)市営駐車場で「合同祭典」が行われ、各地区から集結した19基もの神輿が勇壮な「一斉担ぎ」を披露する。漁師町らしく威勢の良い、掛け声や「唄」、神輿を担いだまま跳ねる「揉み」が特徴。 最終日には勝浦漁港で神輿が船から船へと渡される「神輿の船渡し」が行われ、祭りのフィナーレを飾る。地元住民と観光客が一体となって盛り上がる、伝統と活気に満ちた祭り。 | |
ほろかけ祭り 埼玉県川越市のお祭り
「ヨイショ!」の掛け声に合わせてピンクのホロがクルクルと回転する。少年の成長と五穀豊穣を祈う埼玉県指定の無形民俗文化財。
| ほろかけ祭り | |
 | 【場所】古尾谷八幡神社 〒350-0002 埼玉県川越市古谷本郷1408 |
| 【時期】9月敬老の日の前日 | |
| 【種類】行列 | |
| 【概要】 少年の成長と五穀豊穣を願う伝統的なお祭り。 見どころは、小学生の男子が「ホロ」と呼ばれる、36本の竹ひごにピンク色の紙花をあしらった重い笠を背負い、神輿に供奉して練り歩く「お練り」。ホロの重さはかなりのもので、子供たちは「よいしょーっ」という掛け声に合わせてホロを揺らし、鈴の音を響かせながら独特の足取りで進む。この行事は、氏神に対する氏子入りの儀式であり、古くは元服式の意味合いも持つ。多くの見物客で賑わい、地域の歴史と文化を伝える貴重な神事で埼玉県指定無形民俗文化財にもなっている。 | |
大原はだか祭り 千葉県大原市のお祭り
「汐ふみ」の勇壮豪快、太平洋の大海原に神輿が入る。海の男たちの五穀豊穣・大漁祈願。
| 大原はだか祭り | |
 | 【場所】 千葉県いすみ市中心部 |
| 【時期】9月20日・21日 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 五穀豊穣と大漁を祈願する勇壮な祭り。大原地区の神輿十社は親神(おやがみ)である鹿島神社に参集し、法楽を施行し、午後大原漁港に向う。 東海・浪花両地区の神輿もそれぞれ地区の行事後大原漁港へ集結。十八社がそろって五穀豊穣・大漁祈願ののち怒濤の中で神輿が数社もみあう「汐ふみ」の行事にうつる。 夕闇のせまる頃、花火を合図に大原小学校校庭に集まり、神輿を高く上げて別れを惜しむ「大別れ式」が行われる。 地域の人々にとって、一年で最も重要な行事の一つであり、その歴史と伝統が今に受け継がれている。 | |
新宿十二社 熊野神社 例大祭 東京都新宿区のお祭り
大都会新宿で行われる神輿の渡御。都庁を背景に新宿の御神輿が威勢よく練り歩く。
| 新宿十二社 熊野神社 例大祭 | |
 | 【場所】 新宿十二社 熊野神社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目11−2 |
| 【時期】9月第3土・日曜日 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 江戸時代から続く伝統的なお祭りで、例年多くの参拝客で賑わう。 例大祭では、神事や雅楽の奉納、氏子による神輿の渡御などが行われる。特に、本社神輿の渡御は、十二社周辺や西新宿のオフィス街を練り歩き、多くの見物客を魅了する。 露店も多数出店し、お祭りムードを盛り上げる。伝統と現代が融合した、新宿ならではのお祭り。 | |
阿伎留神社例大祭 9月東京都あきる野市のお祭り
百貫を超える六角神輿が檜原街道沿いを練り歩く。あきる野市に秋を告げる3日間。
| 阿伎留神社例大祭 | |
 | 【場所】 阿伎留神社 〒190-0164 東京都あきる野市五日市1081 檜原街道沿い |
| 【時期】9月28-30日 | |
| 【種類】神輿 | |
| 【概要】 あきる野三大まつりの一つで全国でも珍しい百貫(約375kg)を超える六角神輿が五日市の町を練り歩くのが見どころ。 神輿の渡御のほか、露払いとして獅子舞が舞いを奉納する風習があり、近隣の囃子連による奉祝囃子や山車の巡行も行われ、祭りを盛り上げる。特に最終日の宮入は、多くの観客で賑わい、迫力満点。地域の人々が一体となり、活気あふれる秋の伝統行事として親しまれている。 阿伎留神社例大祭チラシ1 阿伎留神社例大祭チラシ2 | |
平井のお祭り 東京都西多摩郡日の出町のお祭り
金の鳳凰の冠と赤い頭巾を頭にかぶり、大太鼓を中心に舞いを行う。類例のない貴重な舞い。
| 平井のお祭り | |
 | 【場所】 東京都日の出町 平井地区 |
| 【時期】9月29日に近い土日曜日 | |
| 【種類】舞い | |
| 【概要】 春日神社と八幡神社で秋の例祭が行われ、この2つの神社のお祭り両方を合わせて「平井のお祭り」と呼ばれている。 この祭りの見どころは、5基の山車が平井地区を練り歩く様子と、平井宿通りで行われる山車同士のお囃子の競り合い。夜には提灯が灯され、一層賑わいを増す。 また、春日神社では国の重要無形民俗文化財に指定されている「下平井の鳳凰の舞」が奉納される。これは金の鳳凰の冠と赤い頭巾をかぶった舞手が、大太鼓を中心に勇壮に舞う、全国的にも珍しい民俗芸能で、元々は雨乞いや悪疫退散のために奉納されてきた。江戸の要素を含む「奴の舞」と、上方の要素を含む「鳳凰の舞」の二庭で構成される。町全体が活気に満ちあふれる、秋の風物詩として地域の人々に親しまれている。 平井祭チラシ | |
谷保天満宮例祭 東京都国立市のお祭り
十数基の花万灯が谷保駅に大集合。力自慢の男たちが谷保天満宮に向かって花万灯を優雅に回す。
| 谷保天満宮例祭 | |
 | 【場所】 谷保天満宮 〒186-0011 東京都国立市谷保5209 谷保駅周辺 |
| 【時期】9月下旬 | |
| 【種類】行列 | |
| 【概要】 五穀豊穣を願う秋の例大祭。見どころは平安時代から伝わる国指定無形民俗文化財「古式獅子舞」と、重さ100kgを超える色鮮やかな「万灯行列」。 万灯行列は各町会から一基ずつ参加し、子ども万灯も数基加わり 約12~13基が谷保駅ロータリーから谷保天満宮境内まで約2時間にわたり浴衣姿の男衆によって勇壮に練り歩く。 また、宵宮には氏子が提灯を持って参集し、高張提灯などを先導に本殿の周りを巡る神事も行われる。地域全体が一体となって盛り上がる、活気に満ちた伝統的なお祭り。 【2023年】 ● 9月15日(金)獅子迎えの儀 ● 9月23日(土)20:00- 獅子舞宵宮参り 古式獅子舞(宵宮参り終了後) ● 9月24日(日)12:00- 万灯行列 15:00- 古式獅子舞 | |
佃島の盆踊&入船三丁目町会盆踊り&八丁堀納涼大会 東京都中央区のお祭り
江戸の名残をとどめる指定無形民俗文化財。櫓を囲って地元住民がキレよく踊る盆踊り。
| 佃島の盆踊 | |
 | 【場所】佃公園・佃小橋たもと |
| 【時期】9月 | |
| 【種類】踊り | |
| 【概要】 江戸時代から300年続く祖先の霊を祀る念仏踊りで、都の無形文化財に指定されている。 櫓太鼓に合わせ仮設のやぐらの周りを踊る。唄も「秋の七草」「糸屋の娘」と情趣深い。 地域住民にとって夏の風物詩であり、先祖供養の意味合いとともに、地域コミュニティの絆を深める重要な行事となっている。地元の方々はもちろん、遠方からも多くの見物客が訪れ、その賑わいは夏の風物詩として親しまれている。 | |
| 入船三丁目町会盆踊り | |
 | 【場所】東京都中央区入船3丁目 NTT裏×Rico’s(旧ピアゴ)前 |
| 【時期】8月 | |
| 【種類】踊り | |
| 【概要】 東京都中央区入船三丁目の交差点で行われる、地域に根差した盆踊り大会。例年8月に開催され、交通規制をかけて交差点の真ん中にやぐらを建て、その周りを多くの人が囲んで踊る。 中央区の入船3丁目交差点で行われる盆踊り大会。入船3丁目町会が主催する会場で、中央区らしい曲目が楽しめる。地元の人々にとって夏の風物詩であり、アットホームな雰囲気で楽しめるのが魅力とされている。地域住民の交流の場として、また夏の思い出を作るイベントとして親しまれている。 | |
| 八丁堀納涼大会 | |
 | 【場所】京華スクエア 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目17−9 京華スクエア |
| 【時期】9月 | |
| 【種類】踊り | |
| 【概要】 京橋七の部連合町会が主催して行われる盆踊り大会。 会場となる京華スクエア前のスズラン通りは交通規制が行われ、多くの屋台が出店して賑わう。焼き鳥やフランクフルト、生ビールなどが楽しめ、地域住民だけでなく近隣で働く人々も大勢訪れる。 この大会の特徴は、東京音頭や炭坑節といった定番の盆踊り曲に加え、「大江戸八丁堀音頭」や「ホームラン音頭」といった地域にちなんだ個性的な曲も踊られる点。また、雨天時には敷地内の体育館で踊れるため、天候に左右されずに楽しめるのも魅力。最終日には提灯の電気が消され、花火が打ち上げられる恒例のフィナーレも人気を集める。 | |
以上、「9月のお祭り」でした。他の月のお祭りもまとめています。どうぞ以下からご覧ください。
1月のお祭り 2月のお祭り 3月のお祭り 4月のお祭り 5月のお祭り 6月のお祭り 7月のお祭り 8月のお祭り 9月のお祭り 10月のお祭り 11月のお祭り 12月のお祭り