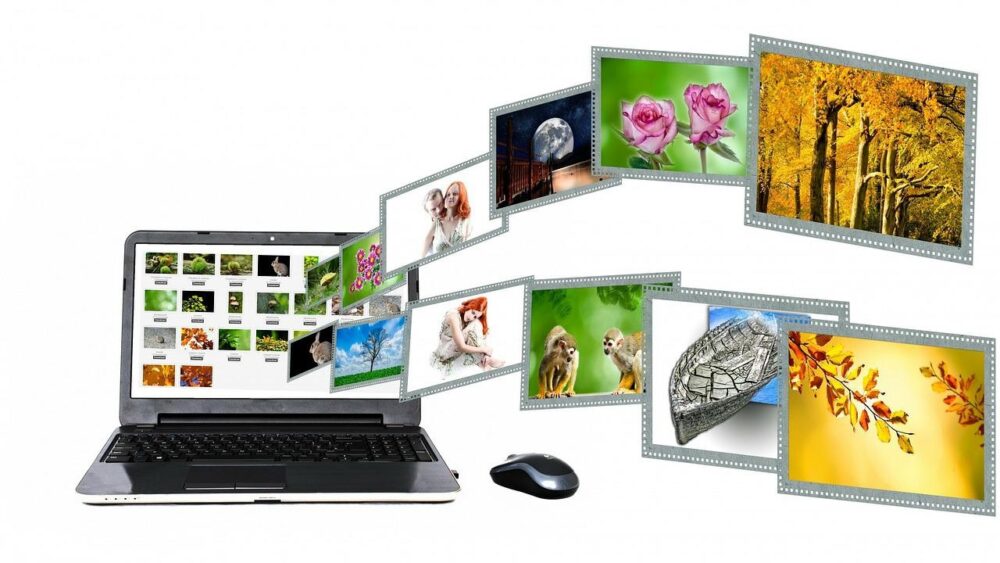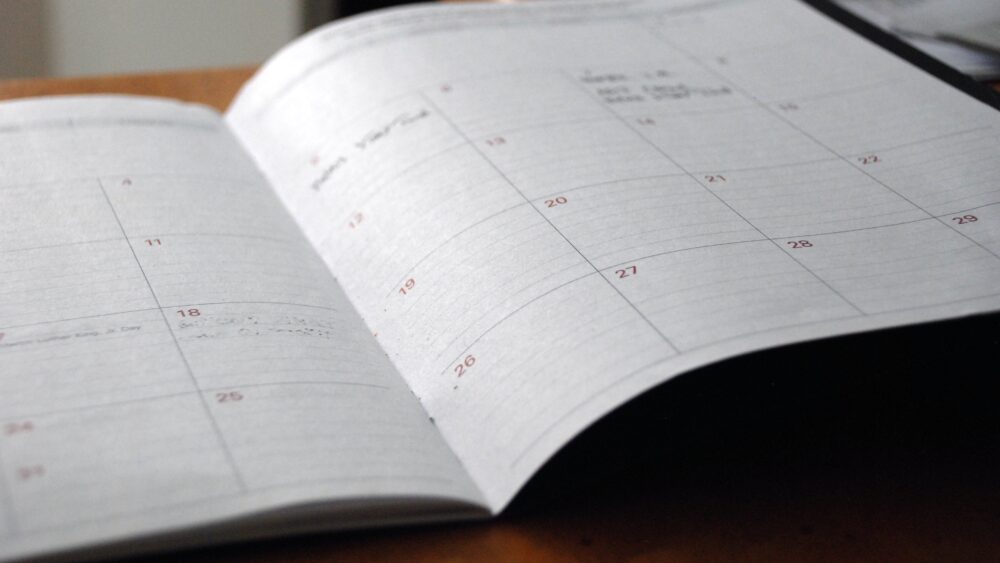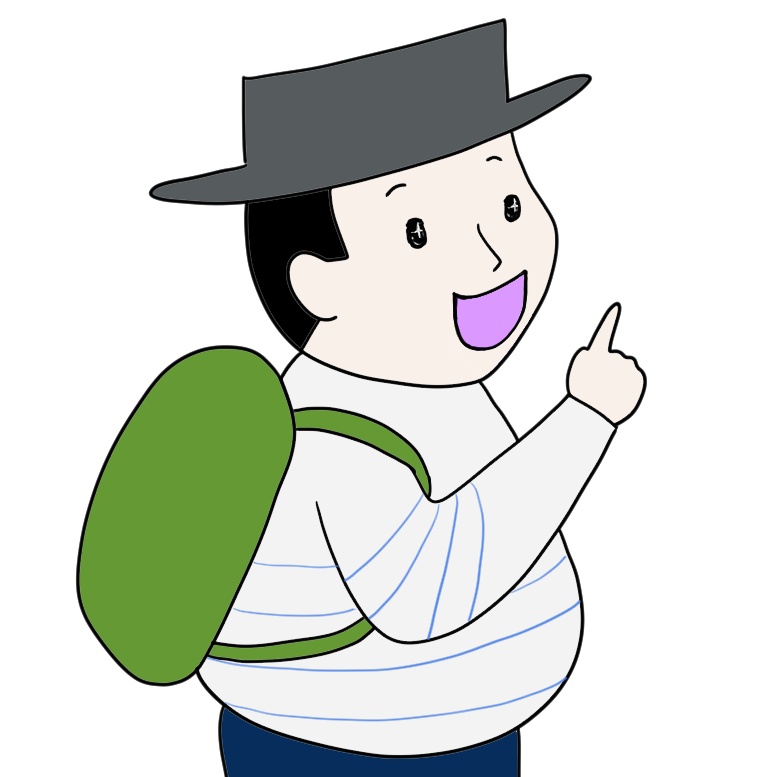ぽちゃま
10月のお祭りをまとめました。
詳細記事はリンクをクリックしてご覧ください。
目次
天草伊勢えび祭り 熊本県天草市のお祭り
天然新鮮!ぷりっぷりの伊勢えびを頂ける天草市の食のお祭り 。漁の解禁時期に合わせて設定される宿泊プランを利用して大満足の旅。
| 天草伊勢えび祭り | |
 | 【場所】 熊本県天草市内 |
| 【時期】8月中旬-12月 | |
| 【種類】食 | |
| 【概要】 天草の5つのエリアで、天然新鮮なぷりっぷり伊勢えびが楽しめる祭り。 祭りの期間中、天草市内の旅館や飲食店では、刺身、鬼瓦焼き、具足煮、味噌汁など、伊勢えびの旨みを最大限に引き出した様々な料理が提供される。新鮮でぷりぷりの伊勢えびは、その濃厚な甘みと弾力のある食感が特徴で、まさに海の恵みを堪能できる。 また、伊勢えび料理だけでなく、天草の特産品が並ぶ物産展や、郷土芸能の披露など、様々な催しが行われ、訪れる人々を楽しませる。美しい天草の自然と美味しい海の幸を同時に楽しめるため、多くの観光客で賑わう。 地元の人々にとっても、秋の訪れを告げる風物詩として親しまれており、天草の魅力を国内外に発信する重要なイベントとなっている。 | |
二本松の提灯祭り 福島県二本松市のお祭り
若連の威勢のいい掛け声で熱くなる。提灯をつけた太鼓台の曳き廻し。
| 二本松の提灯祭り | |
 | 【場所】 福島県二本松市中心地 |
| 【時期】10月の第1 土・日・月曜日 | |
| 【種類】行燈・提灯 | |
| 【概要】 約370年前の、丹羽光重公が二本松城主として入部してから始まったお祭り。最大の見どころは宵祭り。7つの町から高さ11mを超える巨大な太鼓台(山車)が繰り出し、それぞれ約300個、合計約2,100個もの紅提灯が飾られる。これらの提灯には二本松神社の御神火が灯され、夜空を赤々と染めながら、情緒豊かな祭り囃子にのせて市内を勇壮に練り歩く。 提灯は全てロウソクで灯されており、揺れで燃え尽きることもあり、若連による手際の良いロウソクの交換も見どころの一つ。その壮麗さから、日本三大提灯祭りにも数えられ、福島県の重要無形民俗文化財にも指定されている。 2023二本松提灯祭り 規制図 | |
鹿沼秋まつり 栃木県鹿沼市のお祭り
豪華な彫刻をまとった屋台たちの囃子競演。鹿沼市に秋を告げるユネスコ無形文化遺産。
| 鹿沼秋まつり | |
 | 【場所】 鹿沼駅、今宮神社周辺 |
| 【時期】体育の日以前の土日曜日 | |
| 【種類】山車・だんじり | |
| 【概要】 華麗な彫刻を施した囃子屋台が巡行する行事。江戸時代から約400年の歴史を持ち、国の重要無形民俗文化財、そしてユネスコ無形文化遺産にも登録されている。 この祭りの最大の見どころは、「動く陽明門」とも称される絢爛豪華な「彫刻屋台」。日光東照宮の造営に携わった職人の技術が結集したこれらの屋台が、市街地を勇壮に練り歩く。 特に圧巻なのは、複数の彫刻屋台が交差点で披露する「ぶっつけ」と呼ばれるお囃子の競演。激しいお囃子の音色が響き渡り、夜には提灯の明かりに照らされた屋台が幻想的な雰囲気を醸し出す。 34か町のうち屋台を持つ27か町から毎年20台ほどの屋台が参加する。祭り1日目は各町を出発した彫刻屋台が、列を連ねて今宮神社へと繰り込み、神前に囃子を奉納。 神事を執り行ったのち、境内で屋台に提灯を灯し、ふたたび各町内へと繰り出し帰っていく。参加台数により変動はあるが、概ね繰り込みには4時間程、繰り出しには3時間程を要する。 2日目には今宮神社の神輿が町内を巡る御巡幸と全町の屋台揃い曳きが執り行われる。 2023鹿沼秋まつりguidebook 2023鹿沼秋まつり_交通規制図 | |
御会式 東京都大田区のお祭り
日蓮聖人が御入滅された日に行う、3,000人もの万灯練行列。
| 御会式 | |
 | 【場所】 〒146-8576 東京都大田区池上1丁目1−1池上本門寺 |
| 【時期】10月11-13日 | |
| 【種類】行列 | |
| 【概要】 日蓮聖人の命日(10月13日)に合わせて毎年10月11日から13日に行われる、日蓮宗最大の報恩法要。 特に12日の夜に行われる「万灯練行列」が有名。桜の花で飾られた高さ数メートルの万灯を中心に、池上徳持会館から本門寺までの約2キロにわたって、総勢約三千人もの万灯練行列が池上の町を練り歩く。その日は深夜にいたるまで賑やかな一日となる。 この幻想的な行列には毎年30万人以上の参拝者が訪れ、境内や周辺には多数の露店が立ち並び、お祭りムードに包まれる。江戸時代から続く伝統的な行事で、俳句の秋の季語にもなるほど、その歴史と賑やかさで知られている。 | |
佐原の大祭 千葉県香取市のお祭り
水郷の町、佐原の中を「佐原囃子」を響かせて山車が進む。江戸時代の風情を今に残す伝統の祭。
| 佐原の大祭 | |
 | 【場所】 千葉県香取市佐原中心地 |
| 【時期】 八坂神社祇園祭:7月10日以降の金曜・土曜・日曜日 諏訪神社秋祭り:10月第2土曜日を中日とする金曜・土曜・日曜日 | |
| 【種類】山車・だんじり | |
| 【概要】 小江戸と呼ばれる佐原の町並み(国選定重要伝統的建造物群保存地区)で行われ、約300年の伝統を有するお祭り。 7月は八坂神社の祇園祭(夏祭り)、10月は諏訪神社の秋祭りとして開催され、合わせて「佐原の大祭」と呼ばれる。 関東三大山車祭りの一つに数えられ、2016年にはユネスコ無形文化遺産にも登録された。豪華絢爛な大人形を飾った山車が、小野川沿いの風情ある町並みを曳き廻される様子は圧巻。 日本三大囃子の一つである「佐原囃子」の調べが響き渡り、若衆による迫力ある「のの字廻し」などの曲曳きも披露され、多くの観客を魅了する。 | |
川越まつり 埼玉県川越市のお祭り
江戸の影響を受けて発展した川越のお祭り。向かい合う数台の山車が、共演する「曳っかわせ」は最高潮の盛り上がり。
| 川越まつり | |
 | 【場所】 埼玉県川越市街中心部 |
| 【時期】10月第3土曜日・日曜日 | |
| 【種類】山車・だんじり | |
| 【概要】 江戸天下祭を今に伝える貴重な祭事として、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 最大の見どころは、絢爛豪華な山車の巡行。精巧な人形を乗せた十数台の山車が、小江戸川越の町並みを曳き回される。夜には提灯の明かりが灯り、山車同士がすれ違う際に披露される「曳っかわせ」は、囃子方の競演と観客の熱気が一体となり、祭りの興奮が最高潮に達する。このほかにも、おいしい屋台が並び、多くの見物客で賑わう。 R5日本語版パンフ | |
日本橋べったら市 東京都中央区のお祭り
江戸時代から続くべったら漬けの露店売り。客引きの呼び声が秋の宝田恵比寿神社周辺で響き渡る。
| 日本橋べったら市 | |
 | 【場所】 宝田恵比寿神社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目10−11 |
| 【時期】10月19・20日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 この市の名前の由来は、糀で浅漬けにした大根の漬物「べったら漬け」が「べったら、べったら」という威勢の良い掛け声で売られたことによると言われている。 かつては翌日の恵比寿講(商売繁盛を願う行事)に供える品々を売る市でしたが、やがてべったら漬けが評判となり、その名が定着した。 現在では、べったら漬けの露店はもちろん、七味や飴細工、各地のグルメなど約300~500軒もの露店が軒を連ね、多くの人で賑わう。特に夜には提灯が灯り、独特の活気あふれる夜祭の雰囲気が楽しめる。仕事帰りの会社員や観光客など、幅広い層の人々が訪れる秋の風物詩。 | |
菊水祭 栃木県宇都宮市のお祭り
宇都宮市街で行われる勇壮な神事、流鏑馬。
| 菊水祭 | |
 | 【場所】 二荒山神社 〒320-0026栃木県宇都宮市馬場通り1-1-1 宇都宮市内中心部 |
| 【時期】10月最終土・日 | |
| 【種類】流鏑馬・備射祭 | |
| 【概要】 10月21日に行われる「秋山祭」の付け祭りとして発展した。 祭りの主な見どころは、祭神である豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)が神輿に乗って宇都宮のまちを練り歩く「鳳輦渡御」と、古式ゆかしく行われる「流鏑馬」。特に流鏑馬は、大鳥居内の特設馬場で行われ、勇壮な騎射が披露される。 数年おきには、かつて江戸時代に盛んであった山車や屋台が鳳輦渡御のお供として巡行し、祭りに華を添える。 この祭りは、江戸時代の寛文12年(1672年)に火災から免れたことへの感謝から始まり、重陽の節句(菊祭)の頃に行われるようになったため「菊水祭」と名付けられた。 | |
神田古本祭り 東京都千代田区のお祭り
世界最大の古書の街で行われる本のお祭り。神田神保町が古本と人で埋め尽くされる。
| 神田古本まつり | |
 | 【場所】 神田神保町古書店街(靖国通り沿い・神田神保町交差点他) |
| 【時期】10月下旬-11月上旬 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 130軒の古本屋が軒を連ねる世界最大の神保町古書店街、神田神保町。ここで100万冊もの古書が販売される青空掘り出し市。日本全国さらには海外からも多くの読書人が訪れ、街全体が本と人で埋め尽くされる。 神保町交差点を中心とした靖国通りに沿って「本の回廊」が出現し、数十万冊にも及ぶ様々なジャンルの古書が販売される。専門書から文学、美術書、絵本まで、普段お目にかかれないような希少本に出会える。 期間中は古書販売だけでなく、チャリティ・オークション、トークイベント、神保町を巡るスタンプラリーなど、本にまつわる多彩な催しが行われる。読書家はもちろん、古本初心者や家族連れも楽しめるイベントとして、多くの人で賑わう。本の魅力と古書店街の文化に触れる貴重な機会となっている。 神田古本まつりeventmap1 神田古本まつりeventmap2 | |
木場の角乗 東京都江東区のお祭り
江戸の貯木場としてで発展した木場の伝統芸能。祭り囃子のなか、水に浮かべた角材を回転させながら乗りこなす。
| 木場の角乗 | |
 | 【場所】 木場公園 〒135-0023 東京都江東区平野4丁目6−1 |
| 【時期】10月 | |
| 【種類】歌舞伎・舞台 | |
| 【概要】 木場の地名は、に材木問屋の貯木場があったことに由来している。木場の角乗は、江戸時代に木場の筏師(川並)が、水辺に浮かべた材木を、鳶口ひとつで乗りこなして筏に組む仕事の余技から発生した。これに数々の技術が加わり、民俗芸能として発達した。 角乗に用いられる材木は、角材を使用するため、丸太乗りより技術を必要とする。角乗の演技に合わせて、葛西囃子が速いテンポで、演奏される。 江東区では地域の民俗芸能を継承するため、区民まつりの一環として毎年木場公園で「江東区民俗芸能大会」を開催しており、そのなかで「木場の角乗」を公開している。 (演目)地乗り、相乗り、唐傘乗り、扇子乗り、手離し乗り、駒下駄乗り、足駄乗り、川蝉乗り、一本乗り、梯子乗り、三宝乗り、戻り駕籠乗り | |
以上、「10月のお祭り」でした。他の月のお祭りもまとめています。どうぞ以下からご覧ください。
1月のお祭り 2月のお祭り 3月のお祭り 4月のお祭り 5月のお祭り 6月のお祭り 7月のお祭り 8月のお祭り 9月のお祭り 10月のお祭り 11月のお祭り 12月のお祭り
ABOUT ME