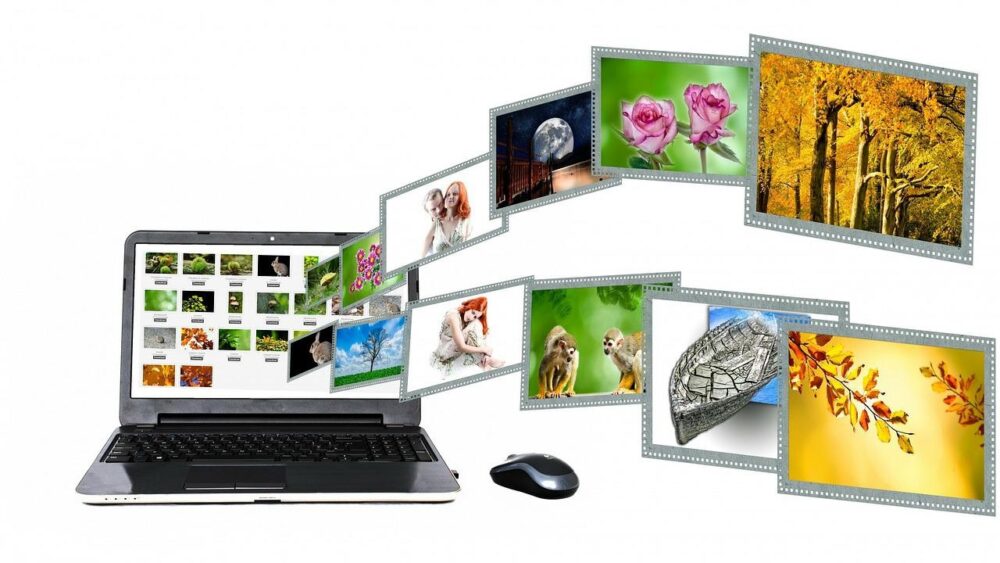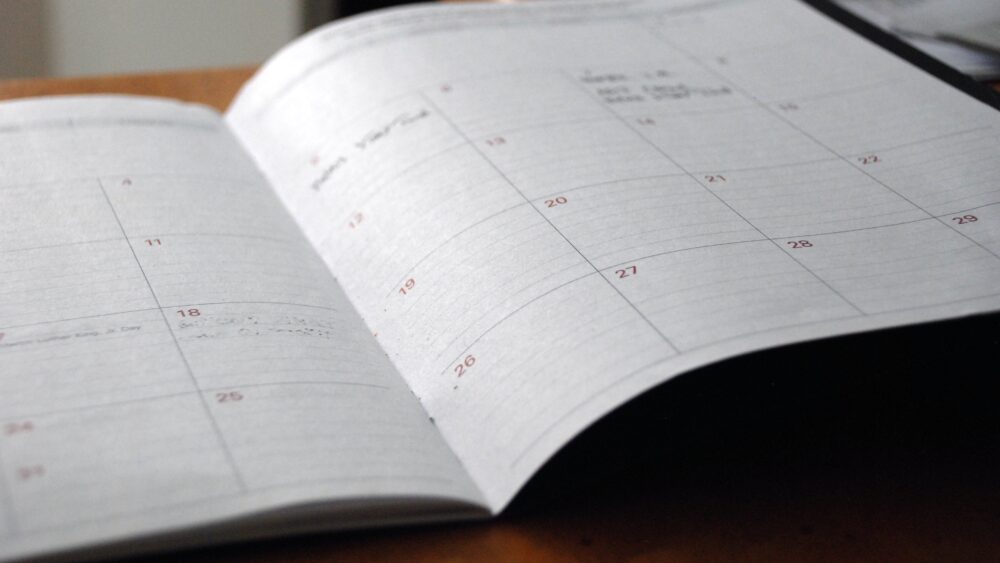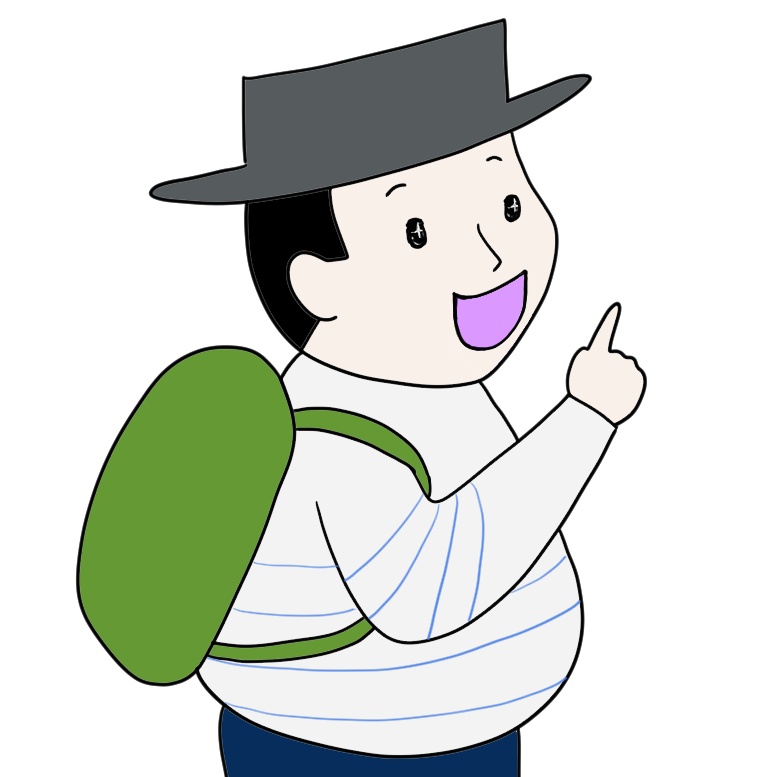お祭りと言っても神輿や山車を楽しむだけではなく、商売繁盛や無病息災を祈念した市もあります。季節を感じながら土地の風物詩を楽しめるのも、日本の祭りの楽しいところ。そんな市のお祭りをご紹介します。
詳細記事はリンクをクリックしてご覧ください。
目次
少林山七草大祭だるま市 1月群馬県高崎市のお祭り
だるま発祥の地で開かれる元祖だるま市。「七転び八起き」の縁起物に今年の思いを込める年の初めの市。
| 少林山七草大祭だるま市 | |
  | 【場所】 少林山 達磨寺 〒370-0868 群馬県高崎市鼻高町296 |
| 【時期】1月6・7日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 少林山七草大祭だるま市は、群馬県高崎市の少林山達磨寺で6日の午後から7日の夕方まで夜通しで開催される伝統的なだるま市。 約200年の歴史を持ち、縁起物の高崎だるまを求める人々で賑わう。七草大祭に合わせて行われ、本堂での祈祷やだるまの販売、露店などが並ぶ。特に7日の朝には本尊が降臨するとされ、多くの参拝者が訪れる。夜通し開催されるのも特徴で、活気あふれる新春の風物詩となっている。伝統的な能や狂言を観ることもできる。 | |
王子稲荷神社 凧市 2月東京都北区のお祭り
王子稲荷神社で「火防の凧(ひぶせのたこ)」を買い求める凧市。江戸時代から続く伝統行事。
| 王子稲荷神社 凧市 | |
 | 【場所】 王子稲荷神社 〒114-0021 東京都北区岸町1丁目12−26 |
| 【時期】2月午の日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 江戸時代から続く伝統的なお祭りで江戸時代は火事が多かったことから、「風を切って揚がる凧」が火事除けのお守りとして「火防の凧(ひぶせのたこ)」として授与されるようになり、定着した。 例年、お祭り当日は境内から旧参道にかけて多くの露店が立ち並び、火防の凧を求める参拝者や多くの人で賑わう。この凧を家に祀ることで、火難を免れ、無病息災や商売繁盛にご利益があると信じられている。 | |
厄除元三大師大祭・だるま市 3月東京都調布市のお祭り
東京に春を呼ぶ深大寺の恒例行事。大小様々なだるま店が出店し、多くの参詣者が願いを込める。
| 厄除元三大師大祭・だるま市 | |
 | 【場所】 深大寺 〒182-0017 東京都調布市深大寺元町5丁目15−1 |
| 【時期】3月3・4日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 比叡山延暦寺の中興の祖である慈恵大師(元三大師)の遺徳を讃える行事として始まった。 「日本三大だるま市」の一つに数えられ、境内には約300軒ものだるま店が軒を連ね、多くの参拝客で賑わう。購入しただるまには、僧侶が物事の始まりを意味する梵字「阿」を左目に、願いが叶った際には感謝の意を込めて「吽」を右目に書き入れてもらうことができる。 最大の見どころは3日、4日のそれぞれ午後2時に行われる「お練り行列」であるが、2021年は残念ながらコロナウイルスの影響を受け中止となった。深大寺の諸行事の中で最大の行事。 | |
清正公大祭 5月東京都港区のお祭り
加藤清正公にあやかった白金台の祭り。葉菖蒲の入った勝守(かちまもり)で勝負に勝つ。

| 名称 | 清正公大祭 |
| 概要 | 加藤清正公が祀られている覚林寺で行われる。武運の強かった清正公にあやかリ、「苦悩に打ち勝つ」という願いを込め「葉菖蒲入リのお勝守」が授与される。 祭りの時期は天神坂の上まで露店が並ぶ。 |
| 開催場所 | 〒108-0071 東京都港区白金台1丁目1−47 |
| 時期 | 5月4・5日 |
| 問合せ | |
| 参考 |
清正公大祭のくわしい記事
犬子ひょうたん祭 6月熊本県山鹿市のお祭り
夏の始まりに疫病を鎮めた子犬の守りを授与する。浴衣を着始める山鹿の風物詩。
| 犬子ひょうたん祭 | |
 | 【場所】 八坂神社 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿196 |
| 【時期】6月15日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 江戸時代に疫病が流行した際、子犬が神様の使いとして疫病を鎮めたという伝説に由来する。この祭では、米粉で作られたひょうたんを抱えた子犬の形をしたお守り「犬子ひょうたん」が授与され、無病息災を願う人々で賑わう。 また、山鹿ではこの日を「初かたびら」と呼び、浴衣を着始める風習がある。山鹿の夏の訪れを告げる風物詩として親しまれている。 犬子ひょうたんのご案内 | |
駒込富士神社 山開き大祭 6・7月東京都文京区のお祭り
富士山の山開きにあわせて行われる駒込富士神社の大祭。神竜(麦わら蛇)を疫病除けの縁起物として授与する。
| 駒込富士神社 山開き大祭 | |
 | 【場所】 駒込富士神社 〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目7−20 |
| 【時期】6月30日-7月2日 | |
| 【種類】花見 | |
| 【概要】 富士山の登山口が開かれることを祝うお祭り。初日の30日は「万灯まつり」として、朝から「万灯回り」が行われる(万灯を掲げた富士講の講員が地域を練り歩く)。2日目は例大祭の式典。 3日目の最終日は「納め」となる。 駒込富士神社は、文京区本駒込にある富士塚の上に建てられた神社で、江戸時代から庶民の富士信仰の中心地として栄えた。山開き大祭では、神事のほか、地元の人々によるお囃子や太鼓の演奏、露店などが立ち並び、多くの参拝者で賑わう。 富士山に見立てた富士塚の山頂には奥宮があり、参拝者は山頂まで登って安全な登山を祈願する。 期間中は縁起物である麦藁蛇(むぎわらへび)や限定で販売される麦らくがんを購入することができる。 ※麦らくがんは富士山の形をした美味しいお菓子。 ※麦藁蛇は「神竜」と呼ばれ、江戸時代中期の宝永年間の頃、江戸で疫病が蔓延した際に麦わら蛇を持っていた家には疫病を患う人がいなかったことから、疫病除けの縁起物として授与されてきた。蛇が枝に巻き付き舌を出している形をしている。台所の水回り付近に掛けてお祀りをする。 | |
入谷朝顔まつり 7月東京都台東区のお祭り
入谷の植木屋さんが朝顔を披露したのが起源。下町の夏を感じながら歩行者天国を歩く。
| 入谷朝顔まつり | |
 | 【場所】 入谷鬼子母神前の言問通り |
| 【時期】7月6-8日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 江戸時代後期、入谷鬼子母神の敷地内で植木屋が朝顔を披露したことがその起源といわれる。 現在では、入谷鬼子母神を中心として言問通りに約60軒の朝顔業者と約90軒の露店・屋台が立ち並び、朝早くから多くの人で賑わう。 江戸時代から親しまれてきた行事で、一時途絶えたが、戦後に地元有志の努力で復活した。毎年約40万人が訪れ、色とりどりの朝顔と露店の賑わいが、下町情緒あふれる初夏の風情を醸し出している。 入谷朝顔まつり案内図 2023朝顔まつり概要図 | |
四万六千日・ほおずき市 7月東京都台東区のお祭り
一生分の功徳を得られる特別な日に鮮やかな朱色のほおずきが威勢よく売られる。浅草の夏の風物詩。
| 四万六千日・ほおずき市 | |
 | 【場所】 浅草寺 〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−1 |
| 【時期】7月9日・10日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 毎年7月9日と10日に浅草寺で開催される縁日。この日に参拝すると、46,000日分のご利益があるといわれ、功徳日の中でも特に重要な日とされている。 この縁日に合わせて、境内で開かれるのが「ほおずき市」。数多くの露店が立ち並び、色鮮やかなほおずきの鉢植えが販売される。ほおずきは、古くから薬として用いられたり、提灯に見立てられ、お盆の迎え火・送り火として飾られたりする植物。 夏の風物詩として、多くの人で賑わい、参拝客はほおずきを買い求め、夏の到来を感じながら、日本の伝統文化を体験できる。 | |
川崎大師風鈴市 7月神奈川県川崎市のお祭り
日本全国から30,000個の風鈴が集まる川崎の夏の風物詩。「厄除だるま風鈴」が涼やかに音色を響かせる。
| 川崎大師風鈴市 | |
 | 【場所】 〒210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町4−48 川崎大師平間寺境内 |
| 【時期】7月中旬 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 全国各地から多種多様な風鈴が集まり、その数は約3万個、種類も900を超えると言われている。川崎大師オリジナルの「厄除だるま風鈴」をはじめ、ガラス製、金属製、陶器製、竹製など、素材も音色も様々な風鈴が境内に飾られ、涼やかな音色が響き渡る。風鈴の販売はもちろん、関連グッズや飲食の出店もあり、夏の風物詩として多くの人々で賑わう。風鈴の音色を楽しみながら、夏の暑さを忘れさせてくれるイベント。 | |
すもも祭 7月東京都府中市のお祭り
源頼義・義家父子の戦勝御礼詣りから始まったすもも市。五穀豊穣を願って「からす団扇」を頒布する。
| すもも祭 | |
 | 【場所】 大國魂神社 〒183-0023 東京都府中市宮町3丁目1 |
| 【時期】7月20日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 平安時代中期、武将の源頼義・義家親子が奥州での戦の前に戦勝祈願をし、成就後にお礼としてすももを奉納したことが起源とされている。 祭りの当日には、境内ですももが販売されるほか、「からす扇子」や「からすうちわ」といった縁起物が売られる。これらは害虫除けや厄除けになると言われ、多くの参拝客が買い求める。また、露店も多数出店し、賑わいを見せる。 午後には、重要無形民俗文化財である「江戸の里神楽」(えどのさとかぐら)の奉納を鑑賞できる。 | |
文京朝顔・ほおずき市 7月東京都文京区のお祭り
夏の真ん中に開催する朝顔・ほおずきの観賞会。小石川のまちなみを楽しみながら文京区のお寺を巡る。

| 名称 | 文京朝顔・ほおずき市 |
| 概要 | 趣きのある小石川のまちなみの中で開催される「朝顔市」「ほおずき市」。 「朝顔市」は徳川家ゆかりの傳通院、「ほおずき市」は「こんにゃくえんま」で知られる源覚寺がメイン会場。 期間中は、朝顔・ほおずきの鉢植え販売や伝統芸能のパフォーマンスをはじめ、江戸情緒を今に受け継ぐ珍しい変化朝顔の展示や朝顔の花合わせ会(品評会)、地元町会による模擬店など、町なかのサブ会場とともに様々なイベントが催される。 |
| 開催場所 | 【朝顔市会場】傳通院 〒112-0002 東京都文京区小石川3丁目14−6 【ほおずき市会場】源覚寺 〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目23−14 慈眼院 澤蔵司稲荷 〒112-0002 東京都文京区小石川3丁目17−12 善光寺 〒112-0002 東京都文京区小石川3丁目17−8 |
| 時期 | 7月下旬 |
| 問合せ | 文京区役所 アカデミー推進課観光担当 |
| 参考 |
文京朝顔・ほおずき市のくわしい記事
人形町せともの市 8月東京都中央区のお祭り
海路交通の拠点だった江戸時代の面影を今に残す、夏の風物詩。仕事帰りに手軽に立ち寄れるせともの市。
| 人形町せともの市 | |
 | 【場所】 水天宮交差点から人形町交差点までの歩道全域 |
| 【時期】8月の第1週の月火水の3日間 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 江戸時代、人形町一帯は、海路交通が便利だったことから、酒、砂糖、醤油、穀物など、生活物資の集積所として、たいへん栄えた。それらといっしょに陶磁器問屋が関東一円の家庭のうつわをまかなったことから由来している。 通りには全国各地の窯元や陶器店が軒を連ね、多種多様な陶磁器が販売される。 普段使いの食器から美術品まで、幅広い品揃えが特徴で、掘り出し物を求めて多くの来場者で賑わう。 初日の午後には、せとものへの感謝と将来の発展を祈願する神事が執り行われる。期間中は周辺店舗での協賛セールやイベントも開催され、人形町全体がお祭りムードに包まれる。 | |
日本橋べったら市 10月東京都中央区のお祭り
江戸時代から続くべったら漬けの露店売り。客引きの呼び声が秋の宝田恵比寿神社周辺で響き渡る。
| 日本橋べったら市 | |
 | 【場所】 宝田恵比寿神社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目10−11 |
| 【時期】10月19・20日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 この市の名前の由来は、糀で浅漬けにした大根の漬物「べったら漬け」が「べったら、べったら」という威勢の良い掛け声で売られたことによると言われている。 かつては翌日の恵比寿講(商売繁盛を願う行事)に供える品々を売る市でしたが、やがてべったら漬けが評判となり、その名が定着した。 現在では、べったら漬けの露店はもちろん、七味や飴細工、各地のグルメなど約300~500軒もの露店が軒を連ね、多くの人で賑わう。特に夜には提灯が灯り、独特の活気あふれる夜祭の雰囲気が楽しめる。仕事帰りの会社員や観光客など、幅広い層の人々が訪れる秋の風物詩。 | |
神田古本祭り 10-11月東京都千代田区のお祭り
世界最大の古書の街で行われる本のお祭り。神田神保町が古本と人で埋め尽くされる。
| 神田古本まつり | |
 | 【場所】 神田神保町古書店街(靖国通り沿い・神田神保町交差点他) |
| 【時期】10月下旬-11月上旬 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 130軒の古本屋が軒を連ねる世界最大の神保町古書店街、神田神保町。ここで100万冊もの古書が販売される青空掘り出し市。日本全国さらには海外からも多くの読書人が訪れ、街全体が本と人で埋め尽くされる。 神保町交差点を中心とした靖国通りに沿って「本の回廊」が出現し、数十万冊にも及ぶ様々なジャンルの古書が販売される。専門書から文学、美術書、絵本まで、普段お目にかかれないような希少本に出会える。 期間中は古書販売だけでなく、チャリティ・オークション、トークイベント、神保町を巡るスタンプラリーなど、本にまつわる多彩な催しが行われる。読書家はもちろん、古本初心者や家族連れも楽しめるイベントとして、多くの人で賑わう。本の魅力と古書店街の文化に触れる貴重な機会となっている。 神田古本まつりeventmap1 神田古本まつりeventmap2 | |
浅草酉の市 11月東京都台東区のお祭り
運を「かっ込む!」、福を「はき込む!」。年々大きな熊手に換えてゆく江戸っ子恒例の市。
| 浅草酉の市 | |
 | 【場所】 酉の寺 長國寺 〒111-0031 東京都台東区千束3-19-6 |
| 【時期】11月酉の日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 正月を迎える最初の祭りとされていた。始まりは、江戸近郊に位置する花又村(現在の足立区花畑にある大鷲神社)であるといわれ、祭りの形態も、当初は近在の農民が鎮守である「鷲大明神」に感謝した収穫祭であったと伝えられている。 市での代表的な名物は、縁起熊手。金銀財宝を詰め込んだ熊手で、運を「かっ込む」、福を「はき込む」といって開運招福・商売繁盛を願った、江戸っ子らしい洒落の利いた縁起物で翌年の更なる招福を願って、熊手守りは年々大きな熊手に換えてゆくのが良いとされている。 会場では大小様々な熊手が露店に並び、熊手を買うと手締め(家内安全や商売繁盛を願って手をたたくこと)が行われるのが風物詩となっている。 夜遅くまで活気に満ち溢れ、多くの参拝者や観光客で賑わう、東京の晩秋を彩る代表的な行事の一つ。 | |
深川酉の市(大鳥神社例祭) 11月東京都江東区のお祭り
運を「かっ込む!」、福を「はき込む!」。下町情緒を味わいながらゆったりと楽しめる深川の市。
| 深川酉の市 | |
 | 【場所】 大鳥神社(富岡八幡宮境内) 〒135-0047 東京都江東区富岡1丁目20−3 |
| 【時期】11月酉の日 | |
| 【種類】 | |
| 【概要】 家内安全や商売繁盛を願う下町の風物詩として親しまれている。 特徴は、福を「かきこむ」「取り込む」とされる縁起物「熊手」。大小さまざまな熊手が露店に並び、参拝者は威勢の良い手締めと共に、お守りの「かきこめ守り」や、枡や小判、おかめなどをあしらった縁起熊手を購入する。熊手守りは年々大きな熊手に換えてゆくのが良いとされている。 | |
松嶋神社 酉の市 11月東京都中央区のお祭り
運を「かっ込む!」、福を「はき込む!」。人形町でひっそりと行われる酉の市。
| 松嶋神社 酉の市 | |
 | 【場所】 松嶋神社 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目15−2 |
| 【時期】11月酉の日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 ご祭神に天日鷲神(あまのひわしのみこと)が祀られていることから、酉の市が開催され、「人形町のおとりさま」として地元の人々に親しまれている。 この酉の市は、かつて人形町が歓楽街として栄えていた江戸時代から続く歴史ある行事で、当時は大変な賑わいを見せたといわれている。現在でも、商売繁盛や開運招福を願う人々で賑わい、縁起物の熊手を買い求める光景が見られる。 日本橋地域で酉の市が行われるのは松嶋神社が唯一であり、長國寺や花園神社のような大規模な酉の市とは異なり、こぢんまりとした温かい雰囲気が特徴。 人形町がかつて芸者や役者が行き交う粋な街だった事にちなんでおかめがついている「かんざし熊手」がある。 | |
築地 酉の市 11月東京都中央区のお祭り
築地市場近くで行われる酉の市。開運熊手神符「かっこめ」で開運、商売繁盛を願う。
| 築地 酉の市 | |
 | 【場所】 波除稲荷神社 〒104-0045 東京都中央区築地6丁目20−37 |
| 【時期】11月酉の日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 江戸時代から続く行事で、開運招福や商売繁盛を願うものとして知られている。境内には、福をかき集める縁起物とされる熊手を売る露店が立ち並び、多くの参拝客で賑わう。 波除神社では、酉の市限定の特別な御朱印や、開運熊手神符「かっこめ」が授与され、これを受けた人は開運くじを引くこともできる(熊手は「かっこめ」「はっこめ」の囃子声のように、福運や財宝を掻きこむ、掃きこむという縁起から商売繁盛のお守りとなったと言われている)。 築地市場に隣接していることから、魚に因んだ塚が並ぶ珍しい光景も見られる。年末の風物詩として親しまれている。 | |
新宿花園神社 酉の市 11月東京都新宿区のお祭り
日本を代表する歓楽街で行われる秋の風物詩。新宿の商売繁盛を祈願する。
| 新宿花園神社 酉の市 | |
 | 【場所】 花園神社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目17−3 |
| 【時期】11月酉の日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 日本を代表する歓楽街がある新宿の花園神社で行われる酉の市。威勢の良い掛け声とともに、縁起物の熊手が販売される。熊手は「かっこめ」「はっこめ」の囃子声のように、福運や財宝を掻きこむ、掃きこむという縁起から商売繁盛のお守りとなったと言われている。この熊手は、商売繁盛や開運招福を願うもので、大小さまざまな熊手が境内に並ぶ。多くの露店も出店し、多くの人で賑わう。 特に、深夜まで活気が続くのが特徴で、仕事帰りの会社員や観光客など、幅広い人々が訪れる。 | |
十日市 12月埼玉県さいたま市のお祭り
武蔵一宮氷川神社で行われる酉の市。境内や参道に熊手や食べ物の露店が立ち並ぶ。
| 十日市 | |
 | 【場所】 武蔵一宮 氷川神社 〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1−407 |
| 【時期】12月10日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 氷川神社の神事である「大湯祭(だいとうさい)」に合わせて行われる「酉の市」で、福をかき集める縁起物の熊手や食べ物などの露店が、境内や参道周辺に約300店も立ち並び、多くの人々で賑わう。 特に、商売繁盛や開運招福を願う人々が、威勢の良い手締めの声が響く中で熊手を買い求める光景は、十日市の大きな特徴。夜遅くまで活気に満ち、新年を迎える準備の場としても親しまれている師走の風物詩。 2023年十日市交通規制略図 | |
十二日まち 12月埼玉県さいたま市のお祭り
サッカーの街で行われる師走の風物詩。かっこめ(ミニ竹熊手)を求めて多くの人が幸せを願う。
| 十二日まち | |
 | 【場所】 調神社 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町3丁目17−25 |
| 【時期】12月12日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 明治時代から続く「大歳の市」として知られ、新年の飾り物や正月用品を売る市が立つ。特に、福をかき込む縁起物とされる熊手(かっこめ)が数多く並ぶのが特徴。 調神社境内や旧中山道沿いに約600〜1,000店もの露店が立ち並び、熊手や神棚、食べ物などを買い求める多くの参拝客で夜遅くまで賑わう。浦和に年の瀬を告げる伝統行事。 | |
羽子板市 12月東京都台東区のお祭り
師走の浅草の風物詩。女子が誕生した家に羽子板を贈る微笑ましい風習。
| 羽子板市 | |
 | 【場所】 浅草寺 〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−1 |
| 【時期】12月17-19日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 江戸時代から続く伝統的な行事で、正月の縁起物である羽子板を販売する露店が多数出店し、多くの人で賑わう。 羽子突きの羽根は虫を食べるトンボに似ていることから、悪い虫(病気)を食べる、あるいは羽根の先端に付いている「豆」から、「まめに暮らすことができる」など、羽子板はもともと縁起物として扱われていたが、やがて女子が誕生した家に羽子板を贈る風習が盛んになり、羽子板が歳の市の主役になっていった。こうして歳の市は、やがて「羽子板市」と呼ばれるようになった。 歌舞伎役者の顔を描いた「役者羽子板」や、華やかな装飾を施した「押し絵羽子板」など、さまざまな種類の羽子板が並び、威勢のいい掛け声とともに、威勢のいい手締めが行われるのが特徴。新しい年を迎える準備として、家族の健康や子どもの成長を願って羽子板を買い求める人々で活気に満ち溢れる。 | |
世田谷ボロ市 12-1月東京都世田谷区のお祭り
400年以上続く世田谷の楽市が始まり。薬箱や教科書などのマニアックな商品が並ぶ歴史あるフリーマーケット。
| 世田谷ボロ市 | |
 | 【場所】 世田谷区世田谷1丁目にある「ボロ市通り」とその周辺 |
| 【時期】12月15・16日と1月15・16日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 400年以上の歴史を持つ伝統的な市。元々は農家の不要品を交換する「年の市」として始まり、後に古着や日用品を扱う「ボロ市」と呼ばれるようになった。 現在では、骨董品、古着、食料品、生活雑貨など、約700もの露店が軒を連ね、毎年数十万人もの人々が訪れる大規模な催しとなっている。特に、代官屋敷周辺の通りは多くの人で賑わい、独特の活気がある。くす玉開きや5年に一度の代官行列も有名。 東京都指定無形民俗文化財にも指定されており、その歴史と文化的な価値は高く評価されている。 世田谷ボロ市リーフレット | |
薬研堀不動尊納めの歳の市・歳末大出庫市 12月東京都中央区のお祭り
しめ縄などの正月飾りに加え問屋街ならではの格安衣料品が手に入る歳の市と出庫市の合同市。
| 薬研堀不動尊納めの歳の市・歳末大出庫市 | |
 | 【場所】 薬研堀不動院 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目6 |
| 【時期】12月26-28日 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 江戸時代に各地で開かれた「歳の市」の最後を飾ることから「納めの歳の市」と呼ばれ、現在は浅草寺の羽子板市と並び、都内に残る貴重な歳の市の一つ。 門松やしめ飾りといった正月用品が販売されるほか、地域の問屋街が主催する「歳末大出庫市」も同時開催され、衣料品や雑貨などが格安で提供される。獅子舞や太神楽などの伝統芸能も披露され、年の瀬の賑わいと活気で溢れる。 | |
人形町 歳の市 12月東京都中央区のお祭り
人形町通りを彩るしめ縄飾り。新年を清らかに迎えるための年末の風物詩。
| 人形町 歳の市 | |
 | 【場所】 人形町通り |
| 【時期】12月下旬 | |
| 【種類】市 | |
| 【概要】 しめ縄やお正月飾りなどの正月用品を販売する露店が約30店舗並ぶ。年末には人形町通りがお正月の飾りで彩られ、人形町交差点から水天宮前交差点の約500m区間に並ぶ330個の「謹賀新年」のちょうちんは必見の価値あり。 商店街の「からくり櫓」もライトアップされ、都内のクリスマスの賑わいとは一線を画した新年の準備ムードが高まる。 | |
以上市のお祭りでした。日本にはまだまだ面白いお祭りがいっぱい。種類の違うお祭りもご紹介していますのでぜひご覧ください。
「種類」からお祭りを探すはこちら