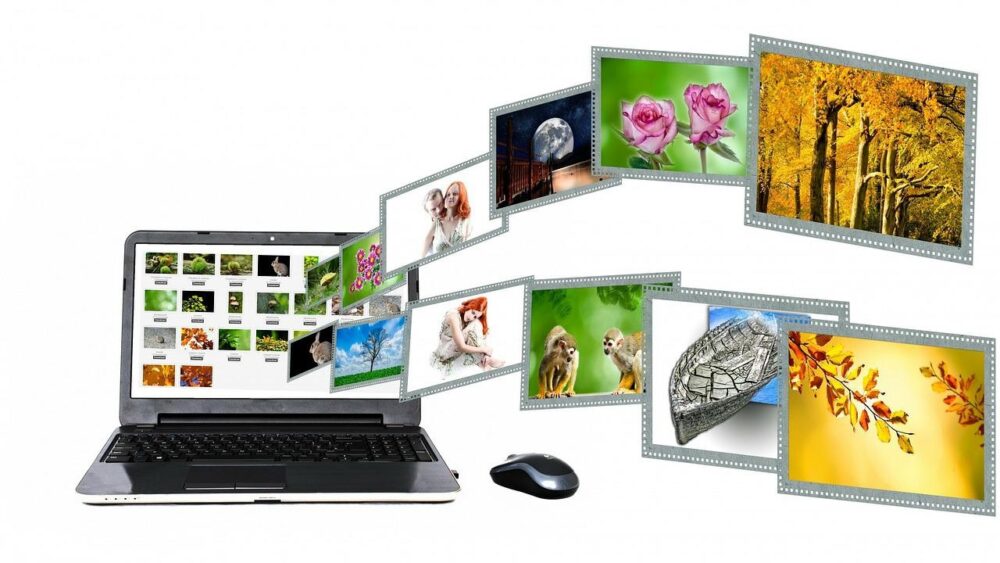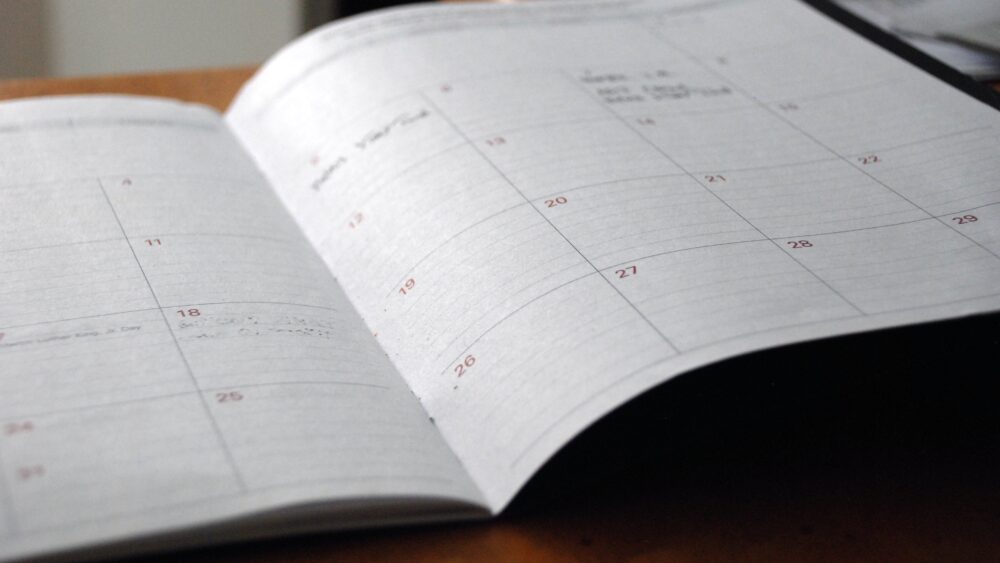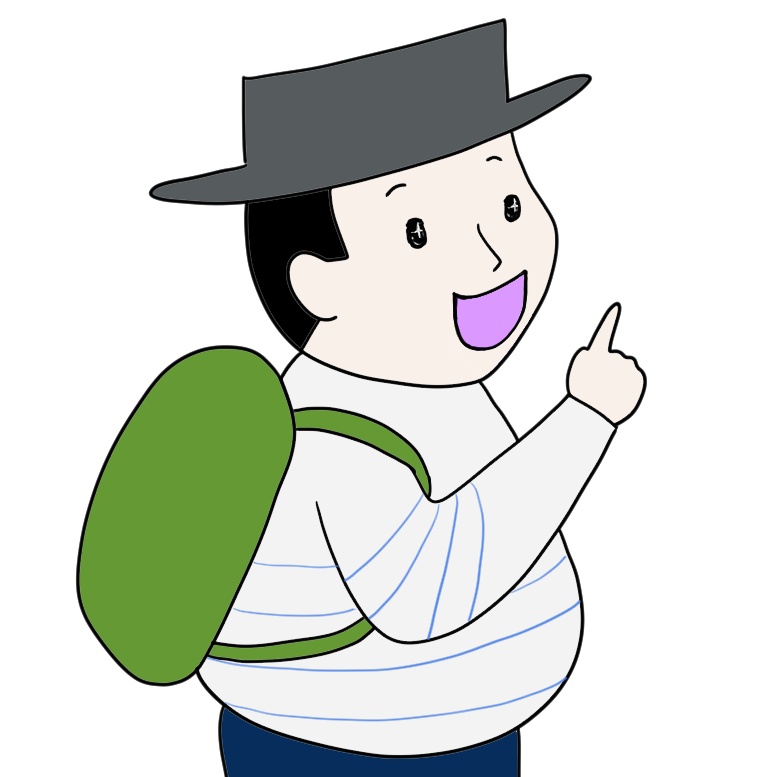ぽちゃま
お祭りの提灯の灯りや囃子の音に誘われて思わず体が動いてしまう「踊り」に対して、宗教的な意味合いが強く、神聖な雰囲気の中どちらかというと鑑賞する事が多い「舞い」。踊りよりも地域性が強く、歴史も長い印象があります。そんなおもしろ舞いのお祭りをご紹介します。
詳細記事はリンクをクリックしてご覧ください。
目次
浅草寺 白鷺の舞 4月/5月/11月東京都台東区のお祭り
優雅な笛、太鼓に合わせて白鷺達が浅草寺の境内を美しく舞う。浅草寺絵巻から生まれた貴重な舞い。
| 浅草寺 白鷺の舞 | |
 | 【場所】 浅草寺 〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−1 |
| 【時期】4月第2日曜日、5月三社祭、11月3日 | |
| 【種類】舞い | |
| 【概要】 昭和43年(1968)に明治100年記念(東京100年)行事として始められ、『浅草寺縁起』(寛文縁起)に描かれる「白鷺の舞」を再興した寺舞。 鷺舞の神事は京都八坂神社が起源とされ、浅草寺の舞はその鷺舞を参考に、寺舞保存会によって演じられている。 白鷺の装束をまとった踊子が舞い、武人、棒ふり、餌まき、楽人、守護童子などが、「白鷺の唱」を演奏しながら練り歩く。 舞は静かでゆったりとした動きが特徴で、笛や太鼓の音色に合わせて、優美な姿を見せる。 この舞は、浅草寺本堂裏の庭園や境内で行われ、毎年11月3日の文化の日に行われる例大祭「金龍の舞」とともに、浅草寺を代表する伝統行事となっている。 江戸情緒あふれる浅草の街並みに、白く美しい鷺が舞う姿は、訪れる人々を魅了し、浅草の秋の風物詩として親しまれている。 | |
鶴の舞 4月東京都練馬区のお祭り
雌雄の鶴を扮した演者2人が、羽ばたきながら舞う。3年に一度行われる珍しい民俗芸能。
| 鶴の舞 | |
 | 【場所】 氷川台氷川神社発祥之地 〒176-0002 東京都練馬区桜台6丁目32−18 及び 氷川台氷川神社 〒179-0084 東京都練馬区氷川台4丁目47−3 |
| 【時期】4月第2日曜日 3年に1度 | |
| 【種類】 | |
| 【概要】 江戸時代から伝わる鶴の擬態芸能。氷川神社の春祭り「お浜井戸の里帰り(神輿渡御行事)」で奉納される、子孫繁栄や五穀豊穣を願う古式ゆかしい舞。 雌雄一対の鶴に扮した2人の演者が、太鼓の音に合わせて羽ばたくように舞い、最後に交尾のしぐさをする。演者は竹の骨組みに白紙を貼った鶴の冠を被り、紋付の羽織を広げて舞う。 東京都練馬区の無形民俗文化財に指定されており、3年に一度行われる。 【2024年】 ●4月13日(土)18:00 前夜祭:カラオケ大会 ●4月14日(日)11:00 式典、宮宿による獅子の舞、鶴の舞奉納 ※開催場所は御浜井戸 | |
品川神社太々神楽 4月東京都品川区のお祭り
関ヶ原の戦いの勝利を祈願して奉納された舞い。楽師の奏でる音に合わせて6座が奉納される。
| 品川神社太々神楽 | |
 | 【場所】 品川神社 〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目7-15 |
| 【時期】4月15日以後の日曜日 | |
| 【種類】舞い | |
| 【概要】 徳川家康が関ヶ原の戦いの戦勝祈願として奉納したことに由来すると伝えられている。江戸時代から伝わる面をつけた舞手が、品川拍子と呼ばれる独自の曲に合わせて舞を演じる。 また、品川神社の太々神楽では楽師の奏でる音にあわせて、江戸時代から伝わる古い面をつけた舞人が12座の舞を演じ、春の大祭では四方拝(しほうはい)の舞、稲荷(いなり)の舞など6座(四方拝の舞、稲荷の舞、矢天狐の舞、花鎮の舞、翁の舞、幸替の舞)が奉納されている。 | |
明治神宮 春の大祭(崇敬者の大祭) 4月/5月東京都渋谷区のお祭り
新緑の美しい明治神宮で、日本伝統芸能の最高峰の人々が熟練の技を奉納する。
| 明治神宮 春の大祭(崇敬者の大祭) | |
 | 【場所】 明治神宮 〒151-8557 東京都渋谷区代々木神園町1−1 |
| 【時期】4月下旬-5月3日 | |
| 【種類】舞い | |
| 【概要】 明治神宮崇敬会の会員多数参列のもとに行われる崇敬者の大祭で明治天皇と昭憲皇太后の御霊を慰め、そのご事蹟を偲ぶ。 祭典では、神楽「浦安の舞」が奉納されるほか、能・狂言、舞楽、邦楽邦舞など、日本の伝統芸能の最高峰とされる数々の奉祝行事が境内の神前舞台で披露される。これらの奉納行事を通じて、日本の伝統文化の神髄に触れることができる貴重な機会となっている。 | |
相模国府祭 5月神奈川県中郡大磯町のお祭り
「暴れ神輿」「鷺の舞」「チマキ撒き」と特長豊かな神事が目白押し。平安時代から続く神奈川県の無形民俗文化財。
| 相模国府祭 | |
 | 【場所】 六所神社、神揃山、馬場公園 〒259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷 |
| 【時期】5月5日 | |
| 【種類】舞い | |
| 【概要】 1000年以上の歴史を持つ神奈川県の無形民俗文化財。相模国(現在の神奈川県)の国司が天下泰平と五穀豊穣を祈願したのが始まりとされ、「端午祭」「天下祭」とも呼ばれる。 見どころは、相模国の一之宮から五之宮、そして総社である六所神社の神輿が一堂に集まること。特に、相模国成立時の席次争いを儀式化した「座問答」は県の無形民俗文化財に指定されており、見応えがある。また、大矢場(馬場公園)では、国司祭や三種類の舞(鷺の舞・龍の舞・獅子の舞)が奉納される。 | |
野田のつく舞 7月千葉県野田市のお祭り
雨乞いから始まった野田のアクロバティックな舞い。暗闇に映える白装束の技。
| 野田のつく舞 | |
 | 【場所】 千葉県野田市内上町地区、仲町地区、下町地区 ※開催場所はその年により異なる。 |
| 【時期】7月中旬 | |
| 【種類】舞い | |
| 【概要】 上・仲・下町の野田三か町の夏まつり(7月中旬)の中日に演じられる民俗行事で、水神信仰にもとづく雨乞の神事。太鼓や笛の音に合わせて、花笠をかぶった若者たちが勇壮に舞い踊る。先端に一斗樽をかぶせた、高さ14.5メートルの白木綿で巻かれた柱を立てて、「ジュウジロウサン」と呼ばれる白装束に雨蛙の面を被った演者が、柱や樽の上、柱から張った綱の上などで軽業を演じる。 演じられる場所は、上・仲・下町の「津久年番」によって変わる。千葉県の『無形民俗文化財』、国の『選択無形民俗文化財』。 | |
平井のお祭り 9月東京都西多摩郡日の出町のお祭り
金の鳳凰の冠と赤い頭巾を頭にかぶり、大太鼓を中心に舞いを行う。類例のない貴重な舞い。
| 平井のお祭り | |
 | 【場所】 東京都日の出町 平井地区 |
| 【時期】9月29日に近い土日曜日 | |
| 【種類】舞い | |
| 【概要】 春日神社と八幡神社で秋の例祭が行われ、この2つの神社のお祭り両方を合わせて「平井のお祭り」と呼ばれている。 この祭りの見どころは、5基の山車が平井地区を練り歩く様子と、平井宿通りで行われる山車同士のお囃子の競り合い。夜には提灯が灯され、一層賑わいを増す。 また、春日神社では国の重要無形民俗文化財に指定されている「下平井の鳳凰の舞」が奉納される。これは金の鳳凰の冠と赤い頭巾をかぶった舞手が、大太鼓を中心に勇壮に舞う、全国的にも珍しい民俗芸能で、元々は雨乞いや悪疫退散のために奉納されてきた。江戸の要素を含む「奴の舞」と、上方の要素を含む「鳳凰の舞」の二庭で構成される。町全体が活気に満ちあふれる、秋の風物詩として地域の人々に親しまれている。 平井祭チラシ | |
高千穂の夜神楽 11-2月宮崎県西臼杵郡高千穂町のお祭り
町内約二十の集落で夜通し奉納される神楽。三十三番を通して日本の神々が総出演する。
| 高千穂の夜神楽 | |
 | 【場所】 高千穂 町内約二十の集落 |
| 【時期】11月中旬-2月上旬 | |
| 【種類】舞い | |
| 【概要】 里ごとに氏神様を神楽宿と呼ばれる民家や公民館にお招きし、夜を徹して三十三番の神楽を一晩かけて奉納する、昔から受け継がれてきた神事。 例祭日は集落によって異なり、毎年11月中旬から翌年2月上旬にかけて、町内約二十の集落で奉納される。各集落の夜神楽は天照大神をはじめ、日本の神話や伝説の中に登場する神々が総出演する。 夜を徹して三十三番の神楽を奉納する「高千穂の夜神楽」は、昭和53(1978)年に国の重要無形民俗文化財に指定された。 各集落では舞う順番などが前後したり、題目が変わったり、それぞれの集落で舞いものが異なる。同じ夜神楽でも違った趣があり、いくつかの夜神楽を見るのもまた違った面白さがある。 | |
以上 舞いのお祭り でした。日本にはまだまだ面白いお祭りがいっぱい。種類の違うお祭りもご紹介していますのでぜひご覧ください。
「種類」からお祭りを探すはこちら

「種類」からお祭りを探す
ぽちゃま
日本のお祭りは神輿を担いだり、山車を曳いたり、獅子や龍が出たかと思いきや行燈や提灯で幻想的な雰囲気を楽しむものなど実に様々...
ABOUT ME