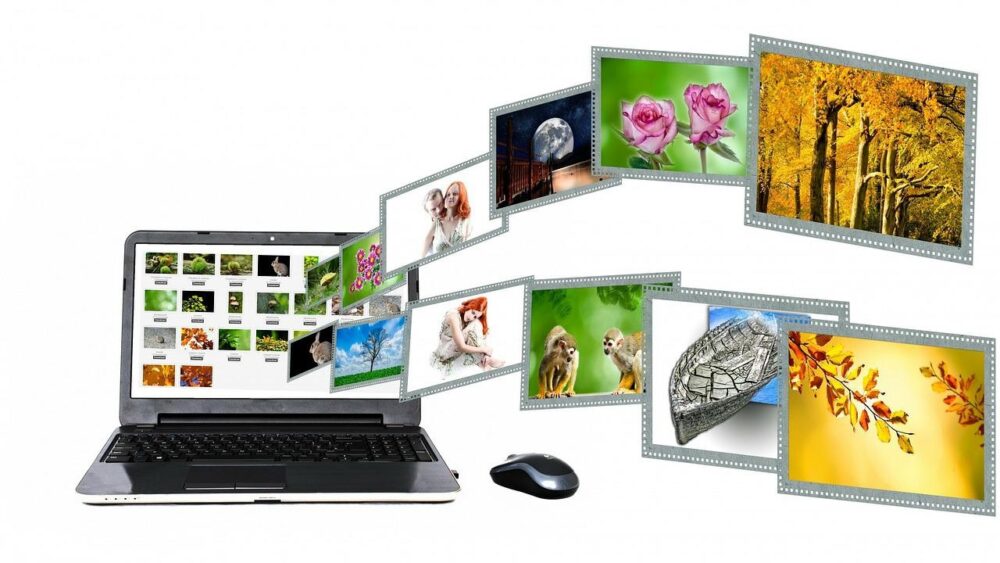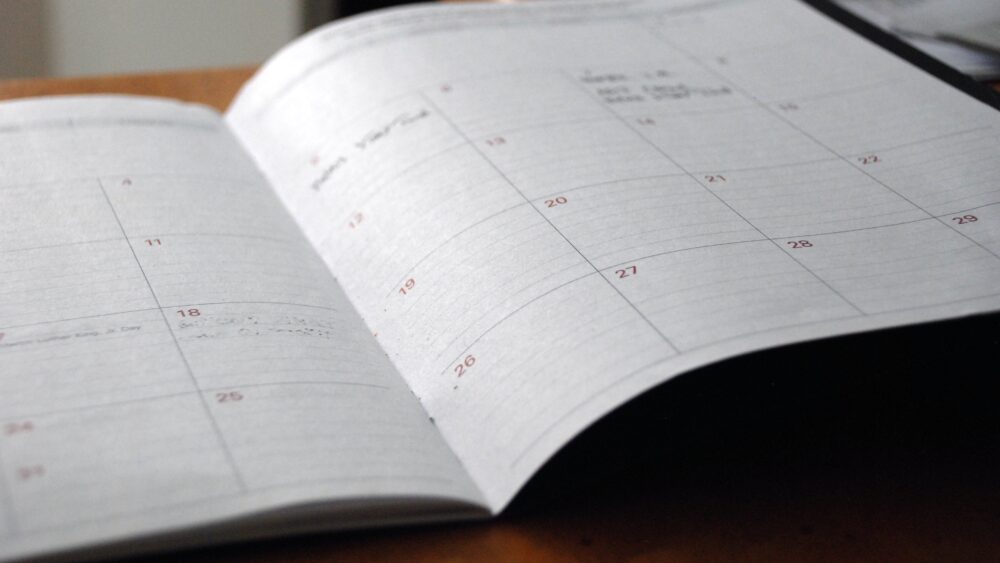キーワード検索
カテゴリーからを探す
最近の記事
- 平方のどろいんきょ 7月埼玉県上尾市のお祭り 場所・時期・観光スポットもご紹介
- 住吉神社例大祭 7月北海道小樽市のお祭り 場所・時期・観光スポットもご紹介
- 日本の美術館・博物館 おススメをご紹介
- 東京大神宮七夕祈願祭 7月東京都千代田区のお祭り 場所・時期・観光スポットもご紹介
- 熊谷うちわ祭 7月埼玉県熊谷市のお祭り 場所・時期・観光スポットもご紹介
- 下町七夕まつり 7月東京都台東区のお祭り 場所・時期・観光スポットもご紹介
- 節分のお祭り
- 狸まつり 7-8月北海道札幌市のお祭り 場所・時期・観光スポットもご紹介
- 人形・装飾のお祭り
- みたままつり 7月東京都千代田区のお祭り 場所・時期・観光スポットもご紹介
- HOME
- 松明あかし